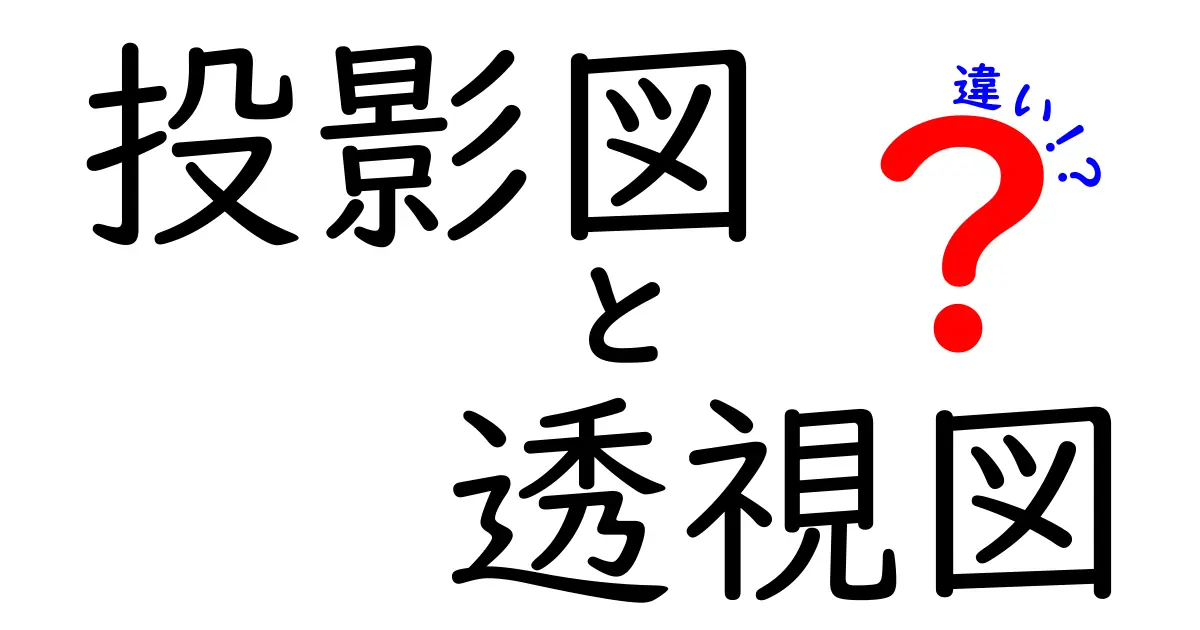

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
投影図とは何か?基礎をしっかり理解しよう
投影図は、物体の形や寸法を正確に表すために使われる図面の一つです。
例えば、建築での設計図面や工学の図面でよく利用されていて、対象物を複数の面から見た平面や側面の図が主です。
投影図では物を実際の目線ではなく、ある決まった方向から『まっすぐ』に見たときの形が描かれます。つまり、遠近感や角度によるゆがみがなく、寸法通りに描かれるため、正確さが求められる場面で役立ちます。
例えば、上から見た図(平面図)、横から見た図(側面図)、前から見た図(正面図)などがあります。これによって立体的な物の形を理解しやすくなります。
投影図は学校の図工や技術の授業でも使われることが多く、その考え方は製品デザインや建築設計など現場でも基本となる知識です。
要は“物体の各面の正確な形状・寸法を平面に表したもの”と覚えておくと良いでしょう。
透視図とは何か?リアルに見せるための表現技法
一方、透視図は人間の目で見える物の見え方に近い形で立体を表現する図です。
遠くの物が小さく、近くの物が大きく見える「遠近法(パースペクティブ)」を使うので、図面が実際の光景に似た印象になります。
例えば、道路が遠くで細くなっていく様子や、建物が手前に大きく感じられる効果は透視図の特徴です。
主にイラストや建築の完成予想図、ゲームや映画の背景制作で使われ、見る人にリアルなイメージを伝えたい時に適しています。
ただし透視図は正確な寸法を表すのには向いていません。物の形が見た目優先で描かれ、寸法が変わって見えるからです。
だから、「完成イメージを伝えるための見た目重視の図」と考えるのがポイントです。
投影図と透視図の違いをわかりやすくまとめると?
両者の違いは主に目的と表現方法の違いです。
投影図は『物体の正確な形と寸法を伝えること』が目的なので、角度や遠近感は考慮せずに描かれます。
透視図は『人が見たときのリアルな印象を伝えること』が目的で、遠近法を使って立体感や距離感を演出します。
以下の表で比較してみましょう。
このように、使う場面や目的に応じてどちらの図を使うかが変わります。建築や機械の設計段階では投影図が欠かせませんが、完成イメージを見せる時は透視図が重宝されます。
両方の違いを知ることで、図面やイラストの見方がぐっと深まり、さらに自分で描くときの役立つ知識にもなりますよ。
投影図の面白いところは、見た目のリアルさよりも正確さを重視していることです。
例えば、飛行機の設計図を描くときに、遠くの翼が小さく見えると困りますよね。
それを防ぐために、投影図は目で見たままの形ではなく、あくまで物体の各面を『真横から見たように』 描くんです。
描くんです。
だから、時にものすごく不自然に見えてしまうこともありますが、それが設計には重要なんです。
この視点に立つと、『リアル=正確』ではないことが分かりますね。ものづくりや建築の世界の重要なルールの一つなんですよ!
前の記事: « 斜視図と透視図の違いとは?初心者でもわかる簡単解説!





















