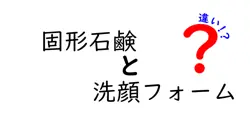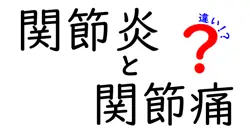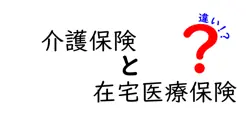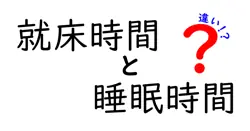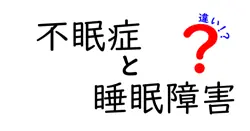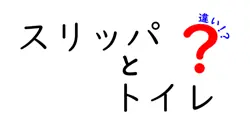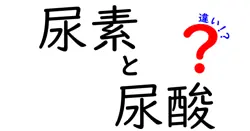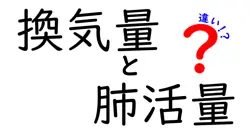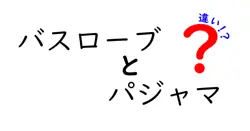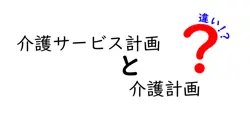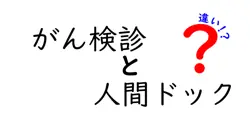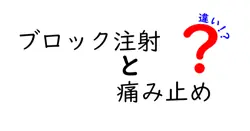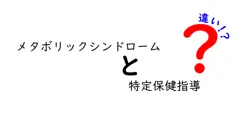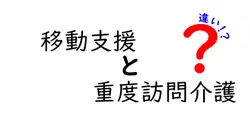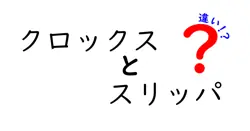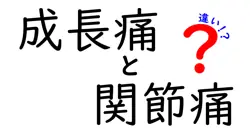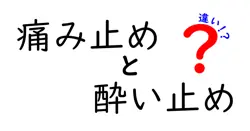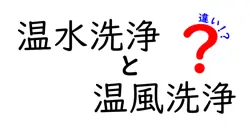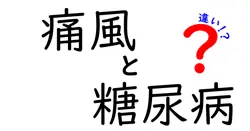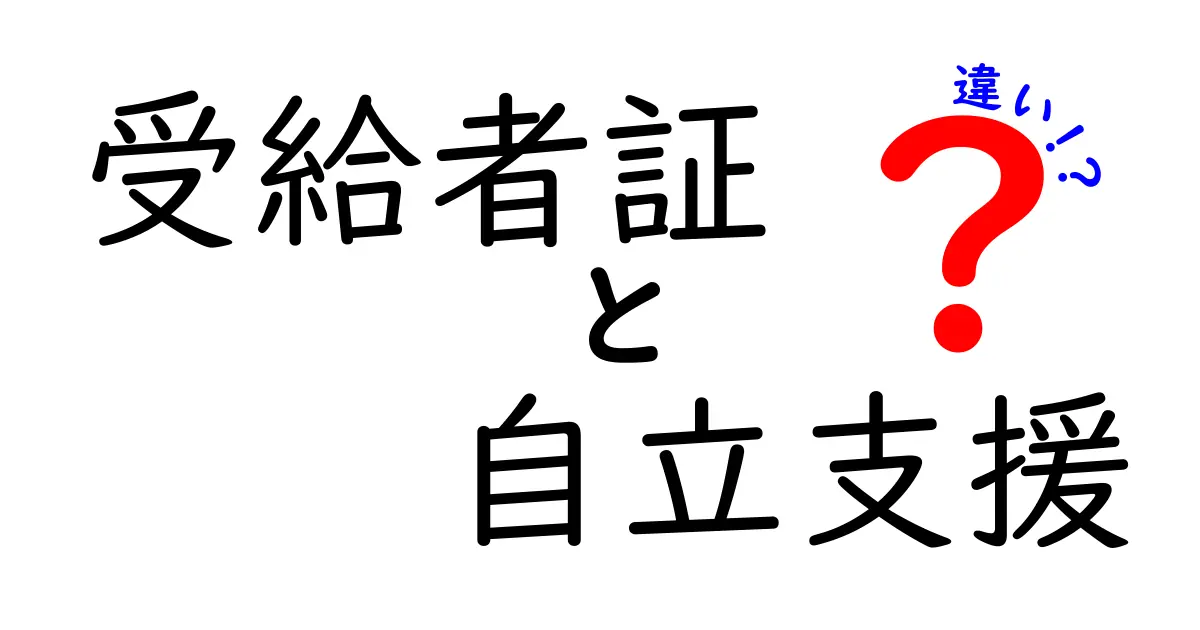
受給者証とは何か?
受給者証は、障害者手帳を持っている人や特定の条件を満たした人が、自立支援医療や介護保険などのサービスを利用するときに必要な証明書のことです。
この証明書があれば、医療費の自己負担が軽くなったり、支援サービスを受けやすくなります。
つまり、受給者証はその人がどの支援を受けられるのかを示す証明書と考えると分かりやすいです。
受給者証は、市区町村の役所や福祉事務所で申請が可能で、申請には申請者の身体状況や収入などの情報が必要です。
受給者証を持つことで、医療費の負担が軽減され、障害者の方や支援が必要な方が安心して生活できる環境づくりに役立っています。
自立支援医療とは何か?
自立支援医療は、障害のある人が医療費の負担を軽くして、安心して治療を続けられるようにするための制度です。
精神障害者や身体障害者、難病患者など、医療が長期にわたる人が対象となります。
この制度を使うと、医療費の自己負担が原則1割になり、経済的な負担が大幅に軽くなります。
制度を利用するには、医師の診断書や申請書を市区町村の窓口に提出し、受給者証を取得する必要があります。
また、自立支援医療は単にお金の負担を減らすだけでなく、本人が自立した生活を目指しながら医療を受けられるよう支援する仕組みでもあります。
受給者証と自立支援医療の違い
受給者証と自立支援医療は、よく一緒に語られますが、それぞれ役割や意味が違います。
簡単に言うと、受給者証は支援を受けるための証明書で、自立支援医療は実際に医療費の負担を軽減する制度です。
つまり、自立支援医療を受けるためには、まず受給者証をもらうことが必要です。
以下の表でそれぞれのポイントをまとめました。
| ポイント | 受給者証 | 自立支援医療 |
|---|---|---|
| 意味 | 支援や医療を受けるための証明書 | 医療費の負担を軽減する制度 |
| 取得方法 | 市区町村窓口で申請 | 医師の診断書と受給者証が必要 |
| 利用目的 | サービス受給の証明 | 医療費の1割負担など負担軽減 |
| 対象者 | 障害者手帳保持者など | 精神障害や身体障害、難病患者など |
このように受給者証は、自立支援医療をはじめとしたいくつかの福祉サービスを利用する際に必須の書類です。
一方で自立支援医療は、実際に医療費の負担を減らすための具体的な制度であり、自立支援医療を受けるには受給者証が必要となります。
そのため、両者はセットで理解するとよいでしょう。
まとめ
今回は受給者証と自立支援医療の違いについてわかりやすくご説明しました。
受給者証は福祉サービスを受ける際の証明書、
自立支援医療は医療費を安くするための制度という違いがあります。
両方を正しく理解し、必要なサポートを受けて健康で安心できる生活を目指しましょう。
もし制度の利用を考える場合は、住んでいる地域の福祉事務所に相談することをおすすめします。
それぞれの制度には細かい条件もありますので、まずは専門家に相談してくださいね。
自立支援医療って聞くと、「なんか難しそう」と思う人もいますよね。でも実は、これは医療費の負担を減らす国のサポート制度なんです。例えば病院にかかるたびにかかるお金がぐっと減るから、長い間治療が必要な人にはとても助かる存在です。しかもこの制度があるおかげで、安心して医療を受けられて、回復に向かう手助けにもなるんですよ。知っておくと家族や友達にも教えてあげたくなるような、役立つ制度ですね!
前の記事: « 生活援助と生活支援の違いとは?簡単にわかる基本ポイント解説