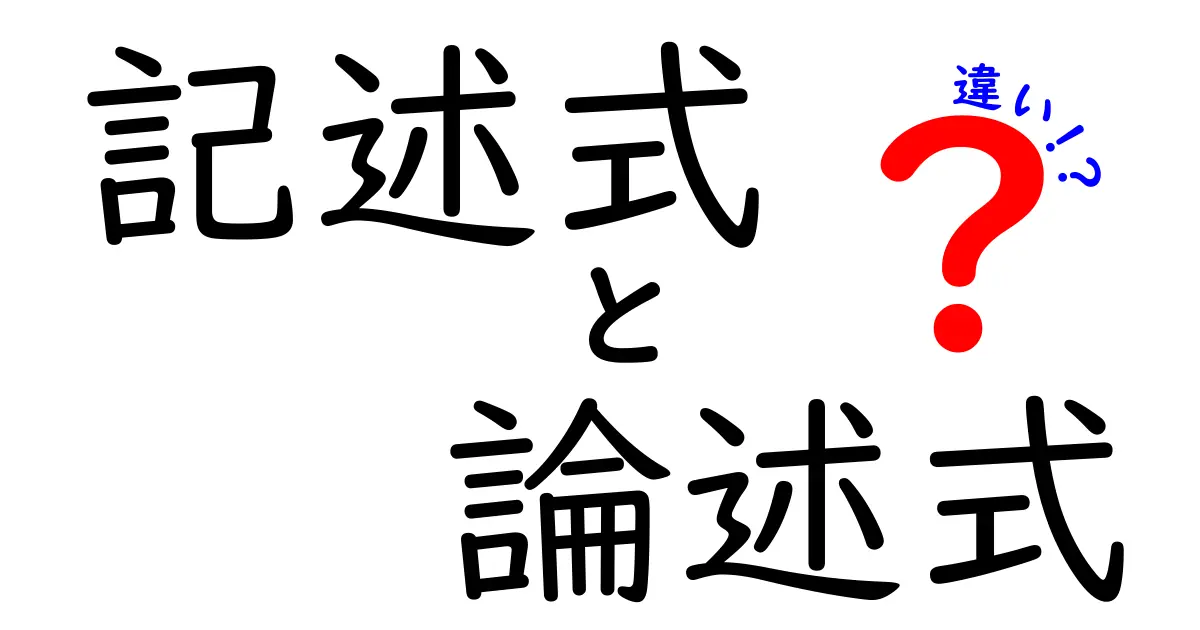

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:記述式と論述式の違いを知る意味
現代の学校や受験で「記述式」と「論述式」はよく登場します。どちらも文章を作る力を評価しますが、求められる内容の性質や評価の基準が大きく異なります。これを知っておくと、テストの対策だけでなく日常の作文にも役立ちます。
記述式は自由に書く余地が広く、具体的な描写や事実の整理を丁寧に行うことが大切です。反対に論述式は論理の筋道を考え、結論へつながる理由や根拠を順序立てて示すことが求められます。
この区別を理解するには、設問をどう読み取るかが鍵です。たとえば説明を求める設問なら記述式寄り、意見や評価を求める設問なら論述式寄りになることが多いです。
目的をはっきりさせることと伝え方を選ぶことが、よい解答の第一歩です。
記述式とは何か?特徴と用途を詳しく見る
記述式は、自由回答の形式の中でも事実の説明や場面描写を長文で表すスタイルです。評価の軸は大きく分けて二つあり、一つは内容の正確さと豊かさ、もう一つは表現の工夫です。自由度が高いぶん、読み手に伝わるように工夫する力が問われます。
例えば歴史の説明では、いつどこで誰が何をしたのかという事実の整理と、場面描写を組み合わせて伝える練習が役立ちます。人物の気持ちや背景を描くときは具体的な場面描写や比喩を使うと伝わりやすくなります。
また字数制限がある場合には、不要な表現を省く機能も評価のポイントです。自由度の高さは正確さと読みやすさの設計を同時に求めるという点で、書く人の工夫力を試す機会になります。
記述式のコツは、まず伝えたい内容を箇条書きにしてから、それを自然な文章に組み立てる練習です。読み手に伝える順序を意識すると、長い文章でも要点がぶれにくくなります。導入・本論・結論という大きな流れを意識して、各段落の役割を明確にしましょう。
論述式とは何か?特徴と用途を詳しく見る
論述式は主張を明確にし、その主張を支える理由や根拠、具体例を組み合わせて伝える解答形式です。評価のポイントは「論旨の一貫性」と「根拠の適切さ」です。導入で主張を提示し、本論で理由を並べ、最後に結論でまとめるという道筋を作るのが基本形です。
この道筋を守ることで、読者はあなたの考えの理由を追いやすくなります。論述式では、反論を想定して自分の意見を補強する工夫も大切です。
主張を支える根拠は、事実、データ、具体例、専門的な説明など、信頼できる情報を選びます。曖昧な言葉を避け、どの根拠がどの主張を支えるのかを明確に結びつけましょう。
論述式のコツは、まず「私の主張は何か」を短くはっきり書くことです。次に、その主張を支える三つの理由を並べ、各理由に対して具体例を添えます。反論の可能性を考え、それに対する反論も追加すると説得力が増します。論理の筋道を崩さず、段落ごとに役割を割り当てることを意識しましょう。
違いのポイントを整理して使い分けるコツ
ここでは記述式と論述式の違いを一目で理解できるよう、要点を整理します。両者の違いは「目的」「構成の組み方」「評価の視点」に現れます。
目的は記述式が事実や描写の正確さ・幅を問うのに対し、論述式は結論へ導く論理の筋道を問います。
構成は記述式が自由度の高い記述を許す一方、論述式は導入・主張・根拠・例・結論の順序を意識します。
評価の視点は、記述式が内容の豊かさと表現の適切さを重視するのに対し、論述式は論旨の一貫性と説得力を重視します。
以下の表は、基本的な違いをざっくりと比べたものです。項目 記述式 論述式 意味 事実・描写の説明を自由に長文で表現 結論と理由を筋道立てて説明 評価軸 内容の正確さと表現 論旨の一貫性と根拠 構成 自由度が高い 決まった導入本論結論の流れ 例 説明文・描写・定義など 論説・エッセイ形式の長文
記述式と論述式は、トレーニングのしかたを変えると、書く力を同時に伸ばせます。まずは設問の指示を読み分け、目的に合わせて解答の構成を決める練習をしましょう。
日常的には、記述式の練習としては日記や説明文の作成、論述式の練習としては小さな主張と理由を組み立てる文章づくりを繰り返すのが効果的です。
また読み手の立場を意識して、伝えたいポイントを先に示す訓練も役立ちます。
雑談形式の小ネタとしての深掘りです。友達と机を囲みながら、記述式と論述式の違いをどう伝えたら伝わりやすいかを話し合いました。記述式は事実と描写の豊かさを競うように意識するのがコツ、論述式は結論へ導く筋道と根拠の組み立てを重視する点がポイントだと実感しました。私たちは、日常の作文にもこの考え方を取り入れて、読み手の立場で伝える順序や根拠の示し方を意識する練習を始めました。もし授業でこの二つの書き方を同時に練習する機会があれば、最初は簡単な題材から始め、段落ごとに役割を決めて書くと、全体の構成が見えやすくなります。最後に友だちはこう言いました。記述式は自由度の広さを活かして自分らしさを表現する力、論述式は論理の筋道をしっかりと伝える力。どちらも磨けば、相手に伝わる文章を作ることができるのです。
次の記事: 仕入先と発注先の違いを徹底解説!購買の混乱を減らす3つのポイント »





















