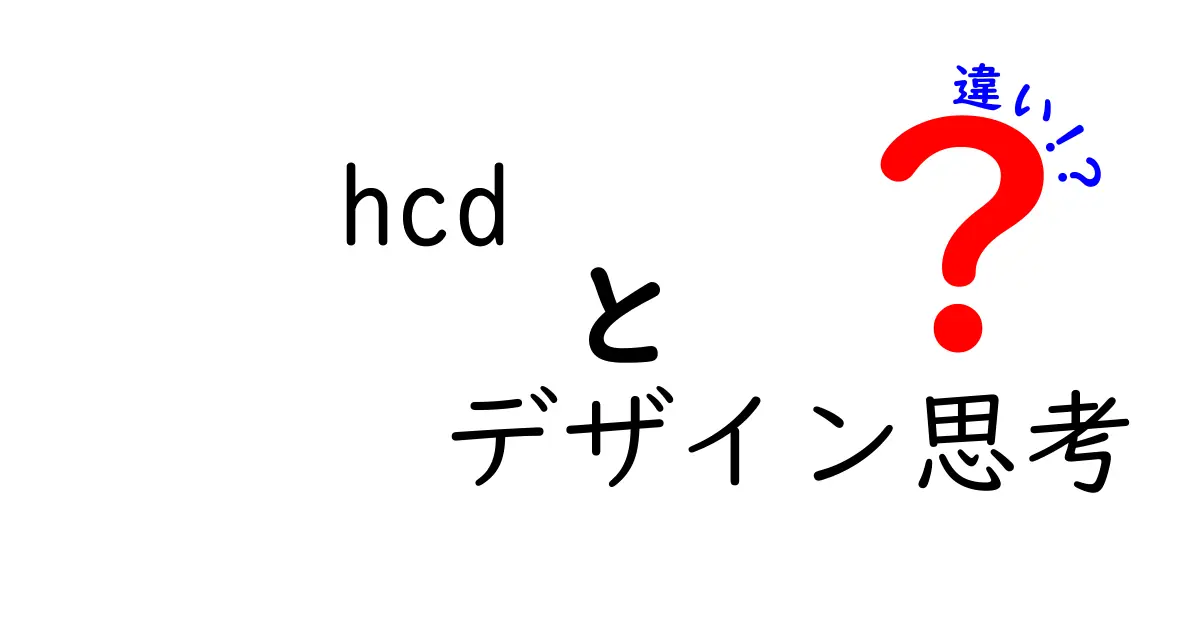

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
hcdとデザイン思考の違いを正しく理解するための基礎
ここではまず hcd とは何か デザイン思考とは何かを基本的な意味から丁寧に解説します。hcd は Human-Centered Design の略であり人間を中心に置く考え方です。社会の中で人の行動や感情、ニーズを最優先に置くことで、使いやすく役立つサービスや製品を作ろうとします。一方デザイン思考は問題を解決するための実践的な思考法であり、共感・定義・発想・プロトタイピング・テストという段階的なプロセスを指します。これらの要素は似ているようで、焦点をどこに置くかという点で異なります。ここから先は具体的な違いの軸をいくつか並べて理解を深めていきます。まず前提として重要なのは「人を中心に置く」という発想の有無です。人間中心の設計は人の体験や感情を最初に考えますがデザイン思考は課題解決の道具箱としての手順や思考法を重視します。人を中心に置くかどうかが全体のデザイン方針を動かす大きな分岐点になります。
ここでの基本的なポイントは三つです。まず一つ目は対象領域の広さと深さです。HCDは人間の物語や文脈を深く掘り下げることを求め、デザイン思考は問題を複数の視点から分解して新しい解を探す技法です。
二つ目は成果物の性質です。HCDの成果物は利用者の体験を語るエスノグラフィー的な成果物やペルソナ、ジャーニーマップなどのドキュメントが中心です。
三つ目は適用の場面です。HCDはサービス設計や教育、医療など人と直に関わる分野で使われやすく、デザイン思考は製品設計やソフトウェア開発のプロセスとして広く活用されます。
違いを理解するだけでなく似ているところも学べば実務で役立ちます。
以下のポイントを実務での使い分けのヒントとして整理します。まず共感フェーズを丁寧に行いユーザーの声を拾い、次に定義と発想の段階で複数視点のアイデアを広げ、最後に試作と検証で現実性と有効性を確かめます。
この流れは人間の体験を中心に置く HCD の根幹と反復と創造性を重視するデザイン思考の実践を結びつけます。実務ではこの二つを組み合わせて使う場面が多く、組織の特性に合わせて柔軟に運用します。顧客のニーズを深く理解しつつ市場や技術の制約も同時に考えることで、過剰設計を避けつつ価値の高い解を見つけ出せます。ここでは実例としてサービスの新機能や教育プログラムの改革を想定し、共感と発想の部分を強調する手法と、検証と反復で確実性を高める手法を対比することで実務の設計力を高めます。
実務での使い分けのヒントと事例
実際のプロジェクトで HCD とデザイン思考をどう使い分けるかのヒントを紹介します。まず初めに「共感フェーズ」を丁寧に行い、ユーザーの困りごとを言語化します。次に「定義と発想」の段階で複数の視点を取り入れてアイデアを広げ、最終的に「試作と検証」で現実性を確かめます。
この流れは 人間の体験を中心に置く HCD の根底と、 反復と創造性を重視する デザイン思考の実践を結びつけます。具体的な事例として、オンライン教育の新機能を設計する場合を想定します。ユーザーインタビューから始め、授業の難しさを噛み砕き、どの機能が本当に必要かをアイデア出しで絞ります。
その後プロトタイプを作って実際の使い勝手を検証し、改善を繰り返します。最後に成果を共有する場を設け、実装後も継続的な改善を続けることが重要です。
この表は実務での違いを視覚的に並べるためのものです。理解の補助として役立ててください。表の後には、結論として両方の強みを活かす連携の考え方を紹介します。現場では混在した要件を一つの設計思想に統合する力が求められます。
要約すると HCD は「人に寄り添う設計の哲学」であり、デザイン思考は「アイデアを生み出し検証する実践的な方法」です。両者を適切に組み合わせることで、使いやすく意味のある体験を生み出すことが可能になります。
友達と喋っているとき、デザイン思考って難しそうに聞こえるけど実は身近な実践なんだと気づく。まず人の困りごとを観察して共感する、次にたくさんのアイデアを出してみる、そして試作品を作って実際に使えるかを試す。学校のイベントでも同じ順序で動かすと失敗を減らせる。アイデアを押し付けず、使う人の視点を回す小さな実験を繰り返すだけで、企画の質はぐっと高まる。





















