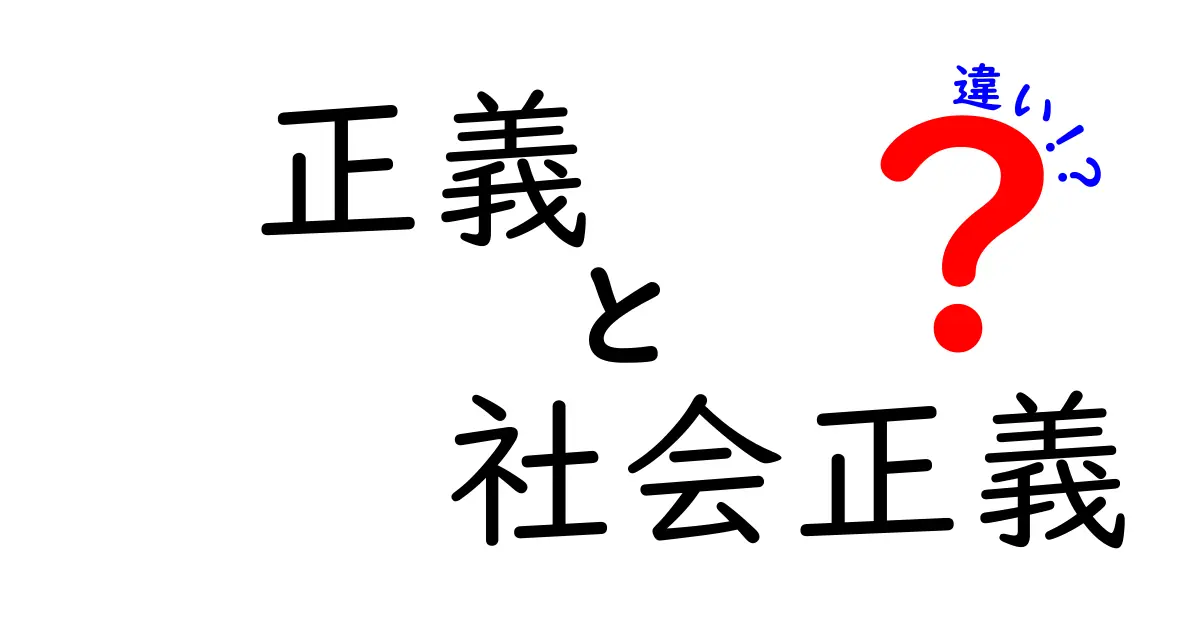

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
正義と社会正義の違いをざっくり理解するクリック必須の入門ガイド
正義という言葉を耳にすると、つい個人の感覚や直感で判断したくなる場面が多いです。一般には、善悪の判断を正しく行い、悪いことを正す力としてとらえられます。
ただし現実の対話でよく出てくるのは、もう一歩大きな枠組みを指す表現である社会正義という言葉です。ここでの主語は個人ではなく社会全体、つまり私たちが生きる国や地域のしくみや制度になります。
社会正義とは機会の平等や資源の公正な配分、弱い立場の人を守る制度の存在を意味します。もし教育や雇用の場で機会格差が長く続くと、多くの人が努力しても報われないという状況が生まれます。そこに対して社会的なしくみを変えることで、より公正な社会を目指すのが社会正義の発想です。
このように正義は心の内面の判断、社会正義は社会の仕組みや制度の公正さを意味する点が大きな違いです。両者は別々の話題のように見えますが、実は互いを補い合う関係にあります。
具体例で分かる正義と社会正義の相違点
次に、違いを具体的な場面で見ていくと理解が深まります。例えば、学校でのいじめを見つけたとき、正義の観点では“いじめをなくすことは正しい行いだ”という個人的な判断が働くでしょう。これが正義の内面的な側面です。一方で社会正義の観点からは、どうすれば全員に平等に教育機会が行き渡るか、どうやって制度を整えていくかという視点が必要になります。
例えば奨学金の拡充、地域間の教育資源の不足を埋める政策、教員の配置の見直しなどが挙げられます。
このような制度改変を伴う解決策は、一人ひとりの行いだけでは成り立ちません。社会が機能する仕組みに働きかける必要があります。
つまり正義の実践には個人の心の動きと社会の制度設計の両方が必要であり、それぞれが互いに影響を及ぼし合います。
このように正義と社会正義は別々の話題のように見えますが、現代社会では両方が同時に必要です。
私たちの暮らしをよりよくするためには、個人の倫理観を大切にしつつ、制度の設計を見直す働きかけを行うことが大切です。
地域のルール作りや学校の取り組み、企業の透明性など、さまざまな場面で両者の力を合わせることが、長い目で見て公正さを高める道になります。
友人とカフェで正義について雑談していたとき、彼は社会正義の話になるとつい制度の話ばかりに走りがちだと言いました。私はそこでこう返しました。社会正義は制度の公正さを作る作業であり、現場の人の感じ方を無視して制度だけを変えると新しい不公平が生まれることもある。だから私たちは日常の体験と制度設計の両方を結びつけて考えるべきだと。こうした雑談を通じて、正義と社会正義は対立するものではなく、互いを補い合う二つの視点だと気づくのです。結局のところ、誰もが安心して暮らせる社会を作るには、心の善意と制度の公平さを同時に育てる努力が必要だと、そんな結論に落ち着きます。





















