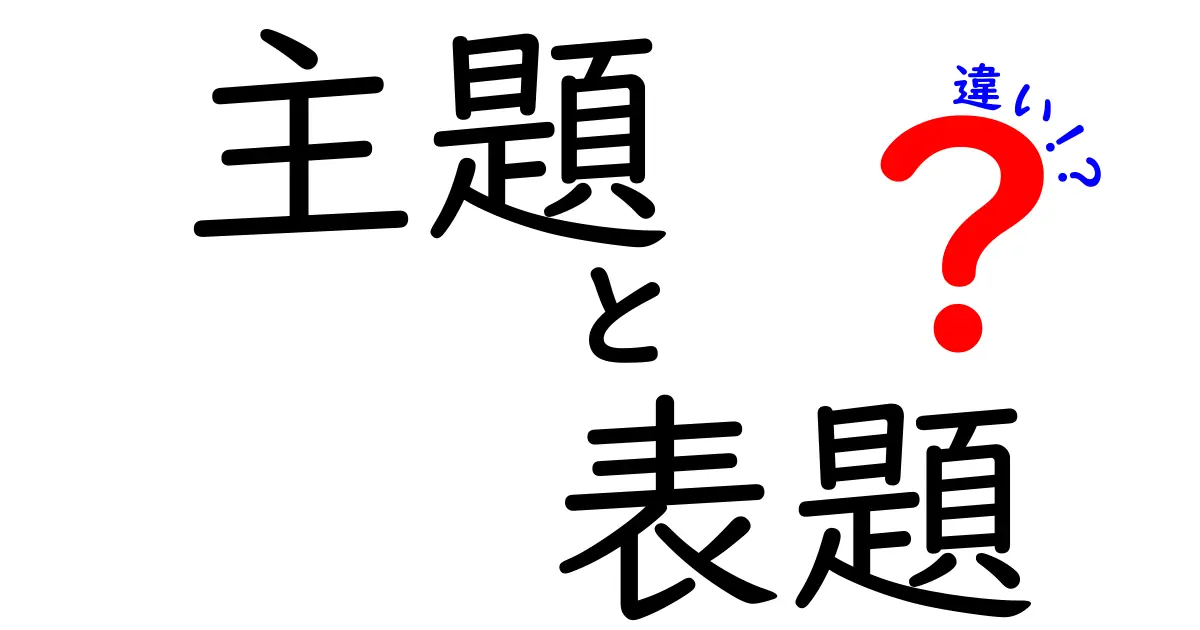

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:主題と表題と違いの基本を整理する
この話題は文章を読むときだけでなく、作文を書くときにも役に立つ基本スキルです。
主題とは作品の中心になる考えやメッセージを指します。
表題とはその主題を外部へ伝えるための名前や見出しのことです。
違いを正しく理解することで、読み手に伝わる情報の順序や焦点が変わります。
以下の章で、それぞれの意味を具体的な例とともに丁寧に解説します。
読みやすさのコツも紹介します。
さあ、ひとつずつ見ていきましょう。
この話の重要なポイントは主題は内側の意味、表題は外側の名前という点です。
主題とは何か
主題という言葉は、作品や文章の「核となる考え」や「伝えたいメッセージ」を指します。
たとえば学校の作文で「友情の力」というテーマがあるとします。物語の登場人物が困難を乗り越える過程を通して、なぜ友情が大切なのかを伝えたいとき、これが主題になります。
主題を見つけるコツは、登場人物の行動や作者の語り口の中にある共通の考えを探すことです。
具体的には、物語の最初と終わりを比べて「何が変わったのか」を考えるとよいでしょう。
主題は必ずしも一言で表現できるとは限らず、短い文や何かの메ッセージとして現れることもあります。
この段落では、主題を理解するための実践的な手順をいくつか紹介します。まずは作品全体をざっと読むとき、「この話は何について伝えたいのか」という基本的な問いを自分に投げかけることが大事です。次に、登場人物の言葉や行動、起こる出来事を時系列で整理してみましょう。最後にその整理を一言で言い換えたとき、それが主題の候補になるはずです。こうした練習を重ねると、作文を書くときにも自分の主題が自然と見えてくるようになります。
また、主題は読者の心に響く力を持っています。読み手が「この文章は自分にも関係がある」と感じられるようにするには、自分の経験や身近な出来事と結びつけて表現すると効果的です。例えば「友情の力」という主題なら、友だちが困っている場面を思い出し、そこから学べる教訓を自分の言葉でつづると説得力が増します。
このように主題は作品の内面にある核であり、読者に伝えるべき核心情報を指します。
表題とは何か
表題は読者に最初に届く情報です。
読者は表題を見ただけで「どんな話なのか」「何を伝えようとしているのか」をおおよそつかみます。表題は短く、魅力的で、誤解を招かない表現であることが理想です。
たとえば「友情の力」という主題をある物語の中心に据えた場合、表題は「ともだちと越える坂道」や「夜明けの約束」といった、情景や感情を呼び起こす言葉を選ぶと読者の興味を引きやすくなります。
表題の良し悪しは、読者が本文を読み始める踏み台になる点で重要です。
また、冗長になりすぎず、設問や課題の趣旨に沿って表現することも大切です。
表題は外見の名前なので、表現の工夫次第で読者の期待感をコントロールできる点が魅力です。
この段落では、良い表題を作るためのコツをいくつか紹介します。まず第一に、本文の主題を1文で表す短いフレーズを作ることを心がけます。次に、そのフレーズを少しひねって興味を引く言い回しに変えてみましょう。最後に、表題に難解な語を使いすぎず、文章の意味が読み手に伝わるようにすることが基本です。
こうしたポイントを押さえると、表題はただの名前以上の、本文の入口となる強力な武器になります。
なお、表題は主題を裏付けるものでなければなりません。表題と主題の間にズレがあると、読者は本文の内容と表題の関係を混乱してしまいます。
違いを理解する実務的なコツ
主題と表題を正しく使い分けるには、実務的なコツをいくつか覚えておくと便利です。まずは読み手の立場で考えること。
読者が何を知りたいのか、どんな感想を持ってほしいのかを想像します。次に、文章を分解してみること。長い作文でも、段落ごとに主題がどう動くか、表題がどの部分を引き立てるかをチェックします。
さらに、下記の表を参考にすると、主題と表題の関係の把握がしやすくなります。
最後に、文章全体の流れを意識して、主題と表題が協力して読者へ情報を伝えるよう整えます。
このコツを日常的に練習すれば、テストの記述問題だけでなく、普段の授業ノートや日記、ブログの投稿作成にも役立ちます。
かつて作文の課題で主題と表題の区別が曖昧だった友人がいました。彼は「人を傷つけないで笑いを取る方法」という題をつけましたが、本文は友情と誤解の話で、主題を読者に伝えるには表題が少し強すぎたのです。私は、読書感想文を書くときには、まず主題を決めてから表題を決めると便利だと伝えました。例えば主題が「協力することの大切さ」なら、表題は「みんなで乗り越える力」のように、短く魅力的にする。こうした工夫が読者の興味を引き、本文の理解を深めます。
次の記事: 作成と執筆の違いを徹底解説!中学生にも分かる使い分けガイド »





















