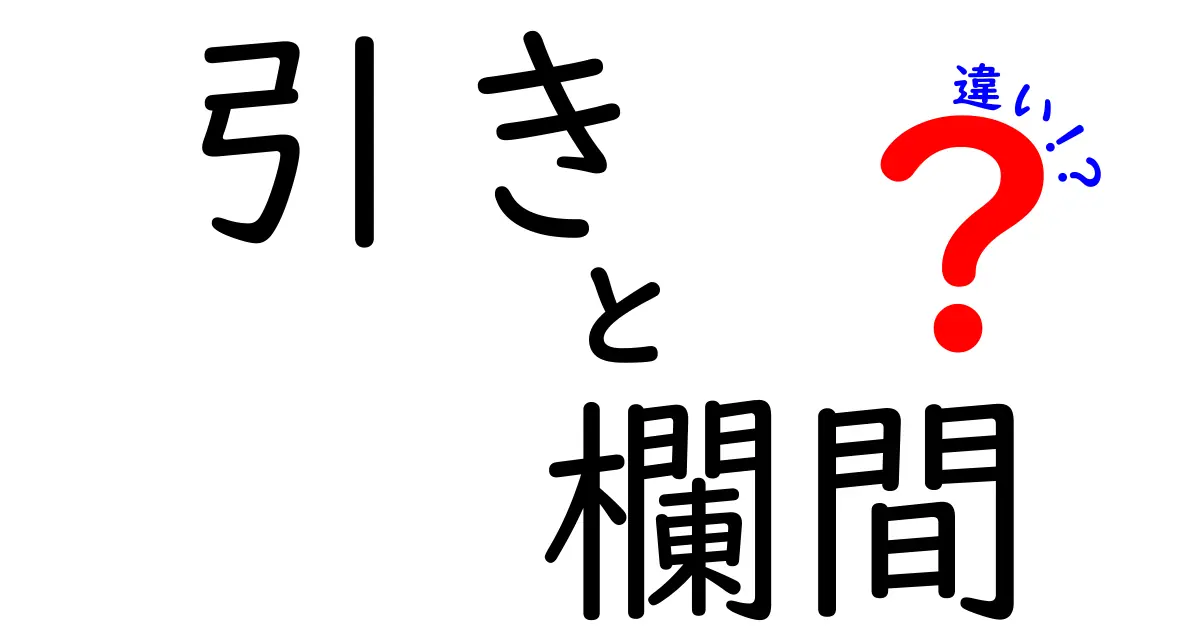

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
引き戸と欄間の基本的な違い
日本の伝統的な建築でよく見かける「引き戸」と「欄間」は、どちらも家の内装や外装で使われていますが、その役割や見た目にははっきりとした違いがあります。まず、引き戸は部屋の出入りをスムーズにするための扉の一種で、横にスライドして開け閉めをします。
一方、欄間(らんま)は、部屋の壁や扉の上に設置される格子状または彫刻された装飾的な部分です。主に通気や採光を目的としていて、部屋同士の空気や光を通す役割があります。
つまり、引き戸は動く扉で出入り口になり、欄間は動かない装飾的な空間部分と覚えておくとわかりやすいです。
引き戸の特徴と使われ方
引き戸は日本の家屋で古くから使われてきた扉のタイプで、狭い空間でも場所を取らずに開閉できるのが大きな特徴です。
例えば、和室の襖や障子も引き戸の一種で、部屋を簡単に区切ったり開放したりできます。
建具としての引き戸は様々な素材で作られており、木材だけでなくガラスやプラスチックを使ったものもあります。
さらに、引き戸は部屋の出入りをスムーズにし、空間を有効に活用する工夫として利用されています。今では洋風の住宅でも引き戸を採用するケースが増えています。
欄間の役割とデザイン
欄間は古くから日本建築の伝統的な要素として使われていて、扉や壁の上にある小さな空間部分に設けられた装飾的な窓のようなものです。
これには通気性の向上や採光効果があり、閉め切りがちな和室の空気を循環させ、明るさをプラスします。
さらに、欄間は装飾的な役割も持ち、木彫りや格子状の美しいデザインが多く、家の雰囲気を格上げします。
現代住宅では欄間を設けない場合もありますが、伝統的な和風建築やお寺などでは今も大切な要素です。
引き戸と欄間の違いをまとめた表
まとめ
「引き戸」と「欄間」は見た目や使い方が異なるものの、どちらも日本の住宅に欠かせない伝統的な要素です。
引き戸は部屋の出入りを便利にし、空間を有効活用できる扉である一方、欄間は空気と光を通して快適さと美しさを加えます。
それぞれの役割や設置場所、デザインに注目すると、家の中での存在感や使い勝手がよく理解できます。
これから家づくりやリフォームを考えている方も、引き戸と欄間の違いを知っておくと参考になるでしょう。
欄間という言葉を聞くと、ただの窓のように思いますが、実はとても深い意味があります。昔の日本家屋では、欄間は通気や採光だけでなく、家族の健康を守るための重要な役割も果たしていました。空気の流れを良くして湿気を防ぎ、快適な室内環境を作る工夫なんです。現代では装飾的な意味合いが強くなりましたが、昔の知恵が詰まった素晴らしい技術だと感じますね。
前の記事: « 【これでスッキリ!】座席と座敷の違いをわかりやすく解説
次の記事: 棗と茶器の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »





















