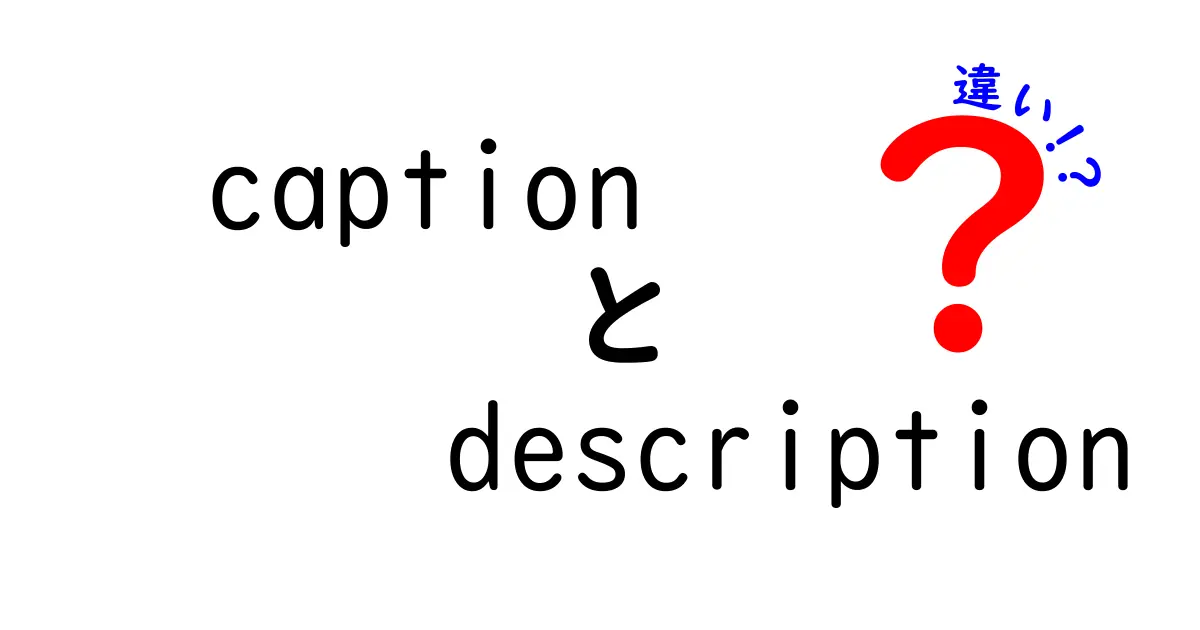

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
captionとdescriptionの基本を知ろう
このセクションでは、写真や文章に添える“caption”と、ウェブページに付随する“description”の基本的な意味と役割を、初心者にも分かりやすく解説します。
キャプション(caption)は主に画像のすぐ下に表示される短い説明文のことを指し、写真の内容を補足したり、感情を呼び起こしたり、作品の雰囲気を伝えるために使われます。
一方、ディスクリプション(description)は記事やページ全体の要約・説明として機能する長めの文章やメタ情報のことを指します。SEO対策として検索結果に表示される要約文や、画像のalt属性に用いられる説明文など、検索エンジンや読者に対して内容を伝える役割を持ちます。
この二つは「長さ」「場所」「目的」が異なり、適切に使い分けることで伝えたい情報をより効果的に伝えることができます。
ポイントは“適切な長さと焦点”を意識すること。 captionは短く、視覚的な情報を補足する。descriptionは詳しく説明し、文脈を補完する。この記事では、具体的な使い分けのコツと実例を紹介します。
また、実務での活用例として、SNS投稿と記事ページの両方を意識した表現の方法を紹介します。
captionとは何か
caption(キャプション)は写真・イラスト・動画などの映像と一緒に表示される短いテキストです。
その主な役割は「何を伝えたいのか」を一言で示すことと、映像だけでは伝わりにくい情報を補足することです。
具体的には以下のような要素を含むことが多いです。
・写真の場所・時間・状況の補足
・感情や雰囲気を伝える言葉
・投稿の意図やCTA(行動を促す言葉)
キャプションは短く簡潔で、読者の視線を誘導する力が強いのが特徴です。
読み手に強い印象を与えたいときや、写真の“意味づけ”を明確にしたいときに有効な手段です。
ただし、あまり長すぎると本来の映像の魅力を損なうことがあるため、読みやすさと要点の明確さを両立させる工夫が必要です。
descriptionとは何か
description(ディスクリプション)はページ全体の要約や説明として機能する長めの文章です。
ウェブサイトでは検索エンジンがこの情報を読み取り、検索結果に表示される要約文として使われることが多く、SEOにおいて非常に重要な役割を果たします。
また、画像のalt属性や記事のメタデータとしても使われ、視覚に障害のある人への補助情報としての役割も持ちます。
ディスクリプションは、読者に「このページで何が得られるのか」を明確に伝え、クリックを促す目的があります。
結果として、検索順位の改善だけでなく、ページへの訪問後の離脱を減らす効果も期待できます。
要点は“要約力と説明力の両立”。150字前後の短い説明を超え、必要な情報を過不足なく伝えることが理想です。
captionとdescriptionの違いを分けるポイント
captionとdescriptionは似ているようで、役割と表示場所が異なります。
以下のポイントを意識すると、使い分けが上手になります。
- 目的:captionは視覚コンテンツの補足と雰囲気づくり、descriptionは情報提供と検索エンジンへの訴求。
- 長さ:captionは短く、descriptionはやや長め。
- 場所:captionは映像の直下やSNS投稿内、descriptionは検索結果の要約欄やページのメタ情報。
- 表現の焦点:captionは“感情・背景のニュアンス”を重視、descriptionは“内容の要点と価値”を明確化。
この3つの点を頭に入れると、伝えたい情報がブレず、読み手にとってわかりやすい表現になります。
使い分けの実例
実務での具体的な使い分けのコツを、実例で見ていきましょう。
例1:写真付きの記事を公開する場合
・captionは写真の直下に配置し、写真の状況・感情・一言コメントを添える。
・descriptionは記事全体の要点を要約し、SEOキーワードを適切に散りばめる。
例2:SNS投稿とブログ記事をセットで運用する場合
・SNSのキャプションは短い一言コメントとハッシュタグ中心、視覚的インパクトを優先。
・ブログ記事のディスクリプションは長文で要点・背景・メリットをまとめ、読み手のクリック意欲を高める。
これらの運用を一つの流れとして整えると、読者の理解度とエンゲージメントが高まります。
表で比較するキャプションとディスクリプション
以下の表は、主な違いを視覚的に整理したものです。表を見れば、用途・場所・長さ・目的の違いが一目で分かります。
| 項目 | caption | description |
|---|---|---|
| 主な用途 | 写真や映像の補足・雰囲気づくり | ページの要約・SEO補助 |
| 表示場所 | 映像の直下、SNS投稿内 | 検索結果の要約欄、メタ情報 |
| 長さの目安 | 短め(1〜3行程度が一般的) | 中〜長め(数十〜百文字以上) |
| 目的の焦点 | 感情・背景の伝達 | 情報伝達・検索性の向上 |
まとめと使い分けのコツ
キャプションとディスクリプションは、目的・場所・長さの観点から使い分けるのが基本です。
まずは“読者に何を伝えたいのか”を明確にし、次に“どこに表示されるのか”を確認します。
そのうえで、 captionは短く刺激的な一文、descriptionは要点を網羅した説明文として作成します。
文章のトーンを整えることも重要です。フォーマルな記事にはディスクリプション、クリエイティブな投稿にはキャプションといった具合に、場面に応じたトーンを選ぶ練習を重ねましょう。
最後に、仮に同じ内容を別の媒体で使う場合でも、重複表現を避け、媒体ごとの特徴に合わせて言い換える工夫を持つと、より効果的な表現になります。
実務で使えるポイントまとめ
・写真の下には短いキャプション、記事には説明的なディスクリプションを用意する。
・SEOを意識してディスクリプションはキーワードを適切に配置する。
・SNSと記事で表現を変えることで、情報の受け取り方を最適化する。
・読み手の動線を考え、キャプションで興味を喚起し、ディスクリプションで深掘りを促す。
koneta: 友だちとカフェでキャプションの話をしていたとき、彼女が一言『写真にはキャプション、記事にはディスクリプションがいるんだね』とつぶやいた。私はスマホを触りながら、キャプションは“この一言で読者の気持ちを動かす短い合図”、ディスクリプションは“読み終えた後まで残る説明の匂い”だと説明した。雑談の中で、実務のヒントを得た気がして、二人は次の投稿計画を練り直す。結局は、伝えたいことをどう伝えるか、場に応じて言葉を選ぶことが最も大事だと改めて感じた。





















