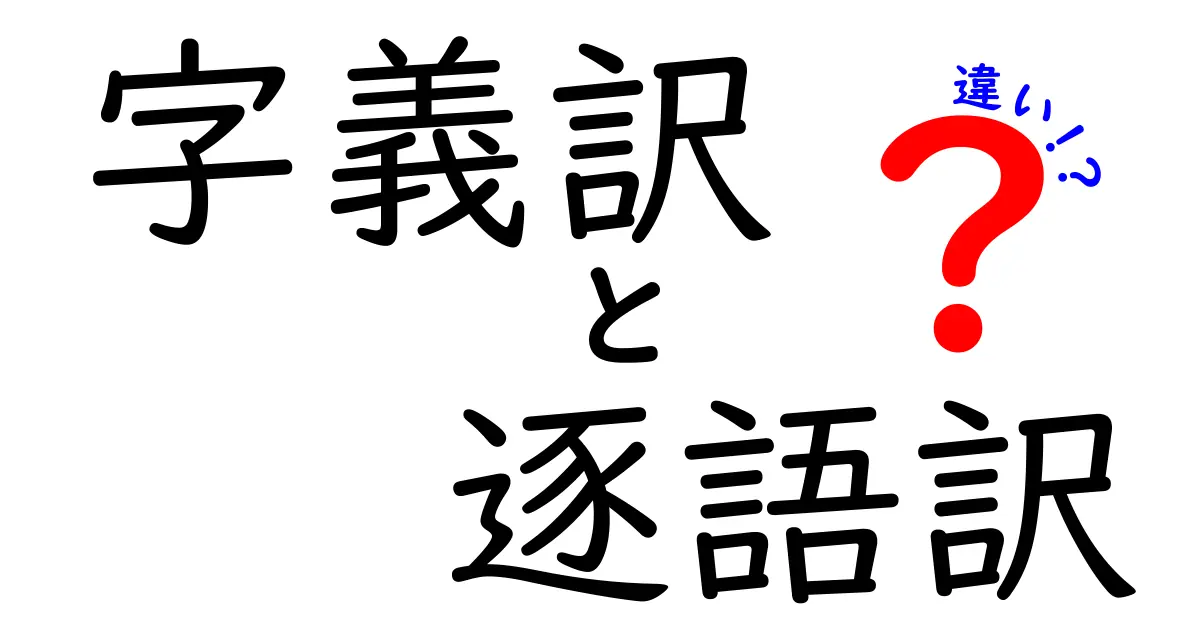

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
字義訳と逐語訳の基本を押さえる
字義訳は、辞書の意味を中心に語を選び、語の形や意味の細かな差を拾います。これにより、原文の意味が厳密に伝わる一方で、日本語としての自然さが低下することがあります。逐語訳は、語を一語ずつ、元の語順に近い形で並べ替えようとする視点です。文法構造の理解には役立つものの、自然な日本語としては読みづらいことが多いのが実情です。両者の長所と短所を理解することが、翻訳の第一歩です。
例えば、日常の文章では字義訳と逐語訳のバランスを取り、意味の正確さと文の流れを両立させる意味訳へとつなげることが多いです。
この考え方を把握しておくと、辞書を引くときの姿勢が変わり、翻訳力の土台がしっかりします。
実際の作業では、字義訳は辞書的な意味の正確さを保つのに適しています。対して逐語訳は、文法の構造を把握する訓練として効果的です。
どちらか一方に偏るより、意味を崩さず自然さを守る“意味重視の訳”を組み合わせるのが現場の常道です。
この理解が深まると、翻訳の幅が広がり、さまざまな文体にも対応できるようになります。
実例で違いを深掘り
英語の慣用表現や比喩は、字義訳だけでは意味が伝わりにくい代表例です。例えば、put up withは字義訳では「持ち上げて耐える」となる可能性がありますが、実際の意味は「我慢する・受け入れる」です。逐語訳では直訳の危険があり、場面に応じた意訳が必要になります。もう一つの例として、break the iceは直訳すると「氷を壊す」です。日常会話では場を和ませるという意味で使われます。このようなケースでは、意味と文脈を合わせる意味訳へ移行することが重要です。
このような判断を練習するためには、原文の文法構造を分析し、意味の中心を探してから、自然なターゲット言語の表現を選ぶ訓練を繰り返すと良いでしょう。
さらに、学習の現場では、字義訳と逐語訳を対比させる演習を行うと、語彙のニュアンスや文法の崩れに気づく力が養われます。
この訓練を通じて、読者に伝わる文章を作る能力が向上します。
使い分けのコツ
結論として、翻訳の場面に応じて使い分けることが大切です。正式な文書や辞書的正確さが求められる場では字義訳を基準にします。文学作品や日常の会話のように表現の自然さが重要な場合には、意味訳を軸に、必要に応じて逐語訳の要素を取り入れるのが現実的です。ポイントは、第一に意味の核、第二に文法の自然さ、第三に文化的背景を意識することです。
この三点を意識して練習を重ねれば、読者に伝わる翻訳が安定して作れるようになります。
初心者には、字義訳と逐語訳の枠組みを頭に入れつつ、意味を崩さずに自然さを保つ訓練を繰り返すことをおすすめします。
逐語訳を深掘りする小ネタ: 友だちと翻訳アプリで遊ぶとき、私は逐語訳は勉強の道具だと話します。実際には、逐語訳を通じて文の構造を理解する力がつく一方、意味が歪む場面も体験します。その時は意味を伝える別の言い回しを思いつく練習をします。最近は慣用表現の直訳に引っかかりやすい子どもたちのために、まず意味を拾ってから自然な日本語の言い回しを探す練習が大切だと話しています。





















