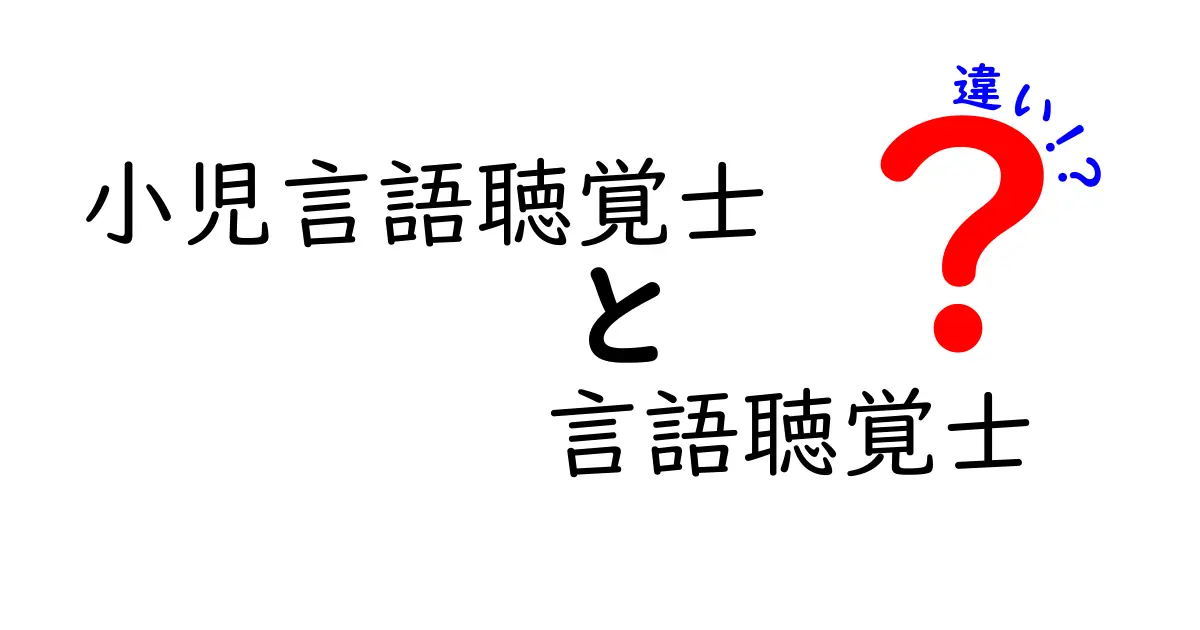

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
小児言語聴覚士と言語聴覚士の違いとは何か
"このページでは小児言語聴覚士と言語聴覚士の違いを、中学生でもわかるように丁寧に説明します。まず大切なのは呼び方の問題ではなく、対象となる人の年齢層や場面、介入の目的がどう異なるかという点です。一般には言語聴覚士という専門職の正式名称があり、子どもを対象とする時にもこの資格を持つ人が中心となりますが、実務の場面で「小児言語聴覚士」という表現が使われることがあります。
要するに、違いは職種自体ではなく活動の中心と対象者の範囲にあると考えると理解しやすいです。
この記事では、具体的なケースから仕事の流れ、学び方、現場での連携までを順を追って解説します。
対象者と場面の違い
小児言語聴覚士は主に0歳〜18歳前後の子どもを対象に、発達段階に合わせた評価と介入を行います。学校や保育園、児童発達支援センターなど、子どもの日常生活の場面での言語・コミュニケーションの課題を見つけ、早期の支援につなげることが多いです。一方、言語聴覚士は高齢者や成人の言語障害、吃音、発声の問題、嚥下障害など幅広い年齢層を扱います。臨床現場では、救急医療やリハビリ施設、在宅ケア、学校内の支援など、さまざまなフィールドで活躍します。こうした場面の違いは、医療チームの連携の仕方にも影響します。
子どもの場合は保護者との関わりが特に大切で、保護者に対して家庭での練習方法や日常の声掛けの工夫を丁寧に伝える必要があります。成人の場合は本人の理解と生活の質を高めることが優先され、生活リズムやキャリア、社会参加の観点が重視されます。
この区分は必ずしも硬い答えではなく、施設や地域によっては境界があいまいになることもあります。しかし目的は共通して、言語能力の改善と生活の質の向上です。
業務内容の違い
医療や教育の現場での業務内容には差があります。小児言語聴覚士が関与する業務の中心は、言語発達の遅れや吃音、発音の不明瞭さ、言語理解の難しさといった子どもの課題を見極め、個別の支援計画を作成し、家庭や学校と連携して進めることです。この過程では、発達心理学の知識や遊びながら学ぶ指導法、保護者への指導、児童との信頼関係づくりが不可欠です。成人の言語聴覚士が扱う場面は、脳卒中後のリハビリや嚥下訓練、発声訓練といった機能回復のリハビリに関わることが多く、評価ツールや治療アプローチの選択が異なります。学校現場では言語教室や個別支援の計画作成、他の専門職との連携が日常的です。
介入の方法も違いが見える点で、評価の観点、介入の目標設定、評価時の道具選びなど、現場のニーズに合わせて調整します。
なお、実務においては双方が同じ国家資格を持つ専門職であることを忘れてはいけません。ですから、「小児専門」や「高齢者専門」といった肩書きは、主に専門領域を示す表現にすぎません。そのため、現場での役割は所属する施設やチームの構成次第で決まります。
表面的な呼び名よりも、実際の介入内容と成果を確認することが大切です。
実務で役立つ比較表
この表を見れば、どの場面でどちらの専門職が主役になるかが分かります。現場によっては子どもの介入を行う言語聴覚士がチームのリーダーになることもあり、また全般を広く担当する言語聴覚士が存在します。
小児言語聴覚士という言葉は、正式な国家資格の名称とは異なる場面で使われることが多い表現です。私の周りにも、子どもの言語発達を専門に扱う人は多く、彼らは日々、遊びを通して言語能力を育てる仕事をしています。たとえば、指先を使った遊びや絵本の読み聞かせを通じて、言葉の発生を促す練習をします。このとき大切なのは、子どもが楽しく取り組める雰囲気づくりと、親御さんへの具体的な家庭での練習提案です。大人の言語障害を扱う人と仕事の流れは似ているところもありますが、子どもの場合は家庭と学校の連携が特に大事になる点が特徴です。長い目でみて、子どもの成長を信じ、毎日の小さな進歩を見逃さず支える姿勢が求められます。





















