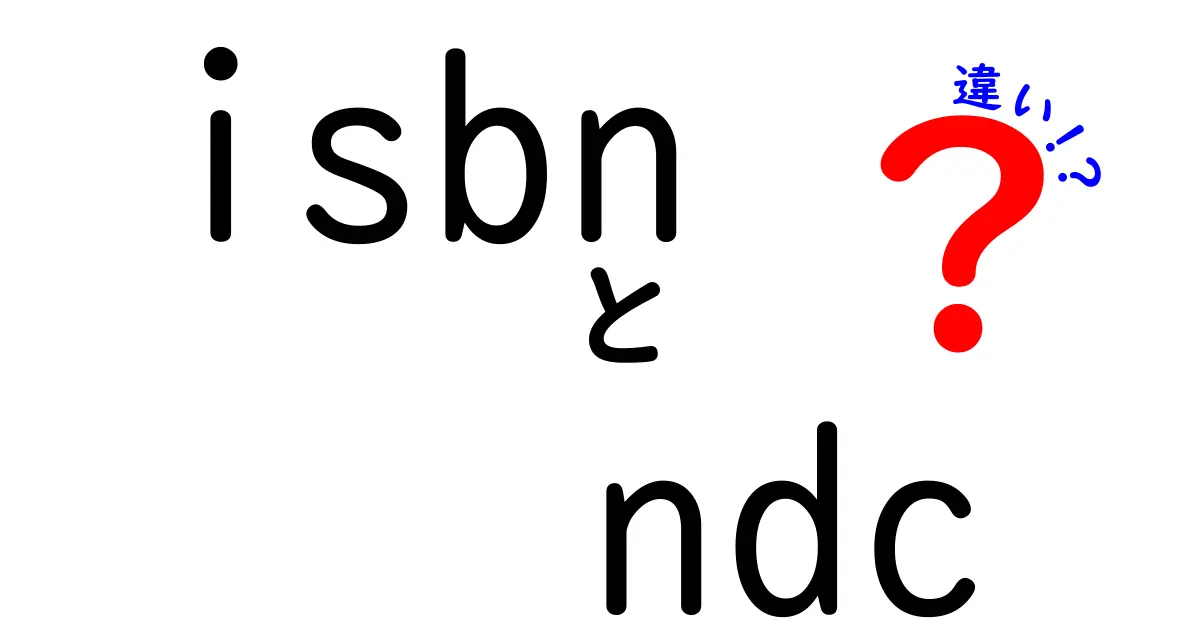

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ISBNとNDCの基本的な役割と成り立ち
ISBNはInternational Standard Book Numberの略で、世界中の本を「1冊ずつ識別」するための番号です。現在は13桁の数字で表され、出版者コード・作家・題名・版の情報を組み合わせて割り振られます。
この番号は同じ題名の別の版でも別のISBNが付く仕組みになっており、どの版を指しているのかを一目で区別できます。
一方でNDCはNippon Decimal Classificationの略で、日本の図書館が本を「どんな科目に属するのか」という点で整理するための分類コードです。
NDCは主題そのものを示す数字で、例えば文学・科学・歴史などの分野ごとに大きな区分があり、さらに細かなサブカテゴリへと階層的に分かれています。
つまり、ISBNは版を特定する番号で、NDCは本の内容・科目を示す分類番号です。
この二つは同じ本に対して同時に使われますが、役割が異なります。
本を購入したり配送したりする場面ではISBNが重要視され、図書館で棚を探す・同じ科目の本を探すときにはNDCが役立ちます。
また、ISBNは出版社が新たな版を出すときに新しい番号を付与する仕組みですが、NDCの変更は主に学術分野の整理方針の見直しに伴います。
この点を押さえると、書店と図書館の現場で何を基準に本を扱っているのかがわかりやすくなります。
ISBNは販売・物流・在庫管理の現場での意思決定を支え、NDCは棚の配置と検索の効率化を担います。
本当に大切なのは、二つの番号が別々の目的で使われているという事実を理解することです。
本の世界では、ISBNとNDCの役割を分けて覚えると混乱を避けやすいです。
ISBNは本そのものを特定する識別子、NDCは本の分類・科目を示すコードという基本を頭に入れておけば、検索も購入も棚の整頓もぐっと楽になります。
さらに、現場の運用をイメージすると、ISBNは出版者が版を売るための“顔”であり、NDCは図書館が知識を体系的に並べる“地図”だと捉えると理解しやすいです。
どちらも bibliothèqueの世界を支える大切な鍵であり、それぞれが別の目的を持ちながら相互補完的に働いています。
この話をまとめると、ISBNとNDCは同じ本を指す番号ではあるものの、役割が異なることで本の取り扱い方にも違いが生まれます。
「本をどう探すのか」「どう売るのか」「どう棚に並べるのか」という3つの観点で見ると、それぞれの番号の意義がよく分かります。
以下に、ISBNとNDCの違いを簡単に整理した表を添えておきます。
この表を見れば、どの場面でどちらを重視すべきかがすぐ分かるようになります。
実務的なポイントの要点
- ISBNは本そのものの識別子で、版・言語・著者ごとに別番号が割り当てられる。
- NDCは本の主題・科目の分類コードで、図書館の棚の並び方に影響する。
- ISBNは販売・在庫管理・配送の際に重要、NDCは検索・棚整理・学術分類の場面で重要。
友だちと図書館の棚を眺めていたとき、ISBNが同じでも版が違えば別の本として扱われることに気づいた。出版社が新しい版を出すたびに新しいISBNをつけるのは、在庫の混乱を避け、読者が正しい版を手にできるようにするためだ。私はその仕組みを深掘り、ISBNは“本そのものを指す識別子”であり、同じ題名の別版を区別するための番号だと理解した。つまり、号数が違えば同じ著者でも全く別の書店体験になる。学校の図書室の古い本と新しい版を比べると、背表紙の番号が違うことに気づく。そんな体験がきっかけで、“情報は番号で走る”と感じた。これから書店や図書館を使うとき、ISBNとNDCをセットで見ると、本の多様性と整理の両方を尊重できる気がする。
前の記事: « 連体形と連体詞の違いを徹底解説!中学生にもわかるやさしい日本語で





















