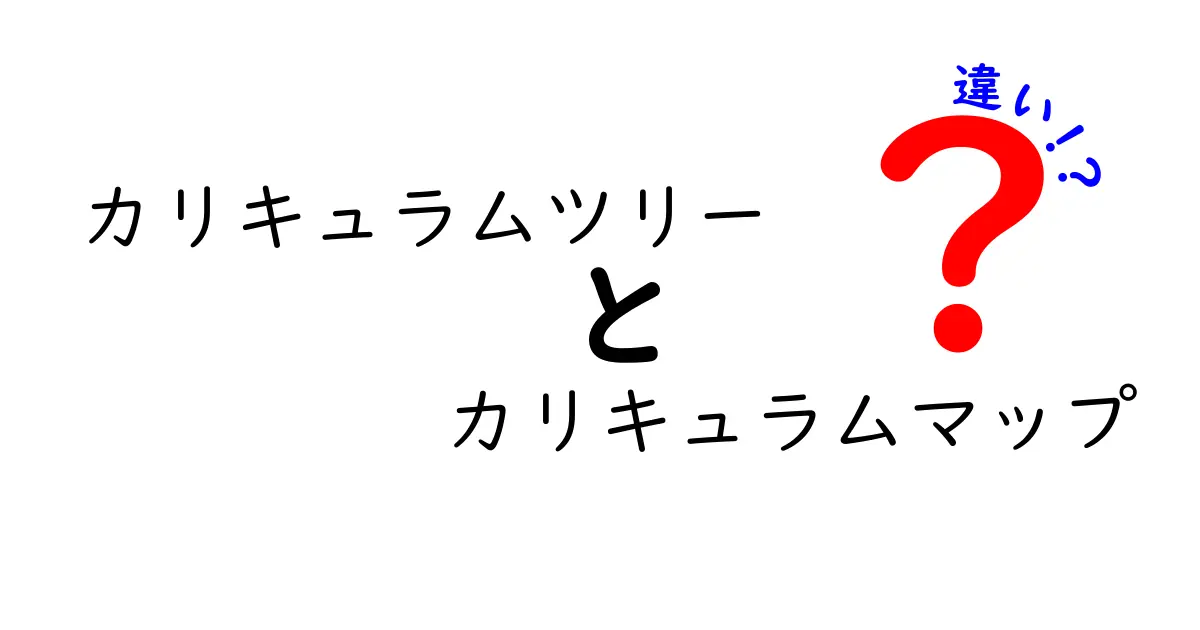

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カリキュラムツリーとカリキュラムマップの基本を押さえる
ここではまず「カリキュラムツリー」と「カリキュラムマップ」という二つの用語の基本を丁寧に解説します。両者は教育設計の現場でよく出会う考え方ですが、役割が異なる点を知ることが大切です。
カリキュラムツリーは内容の階層構造を指すことが多く、学習項目を上から下へつながる木のように並べます。子どもたちがどの科目でどの知識が前提となるのかを可視化するのに向いています。
一方カリキュラムマップは学習の道筋を地図のように描き、いつどの順番で何を学ぶかを時系列や関連性とともに示します。
この二つの違いを正しく説明できれば、授業や課題の設計がぐっと分かりやすくなります。
以下では「定義の違い」「目的の違い」「実務での使い分け」の三つの観点から詳しく見ていきます。
重要ポイントは次のとおりです。ツリーは「階層と前提の関係」を重視します。マップは「道のりと関連性」を重視します。
この点を押さえると授業計画の取り組みが変わることが多いです。
それでは具体例を見ながら理解を深めましょう。
違いを整理する三つのポイントと実例
まず第一のポイントは視点です。ツリーは「上位の概念から下位の要素へつながる階層」を前提とします。これにより学習内容の必須順序が見えやすく、苦手科目が出やすい領域も把握できます。次にマップは「学習の旅路」を描くことで生徒の学習計画を理解しやすくします。二つ目のポイントは目的の違いです。ツリーは「内容の全体像と前提条件の整合」を保つことを目的とし、マップは「学習の進捗と到達点の把握」を目的とします。三つ目のポイントは実務上の使い分けです。授業設計ではツリーを教科横断の連関を示す手がかりとして使い、マップは学年進行や評価計画の設計に用いると効果的です。
具体的な例として、国語の文章読解のカリキュラムをツリーで考えると「語彙力>読解力>批評力」という階層が見えます。一方マップでは「1学期に読む作品と学習順序」「読解演習と評価のタイミング」を時系列で整理します。
このように目的と使い方を分けて設計することで、教師も生徒も道に迷いにくくなります。
ねえ、カリキュラムツリーとカリキュラムマップの話、実はつまずきポイントが多いんだ。ツリーは木の幹から枝へ分かれていく感じで、前提条件が見えやすい。マップは旅の道のりのように、いつ、誰に、何を学ぶかを順番に示す。実はこの二つの視点を一緒に使うと、授業の設計と生徒の学習計画が自然につながるんだ。ツリーは“何が大事かの順序”を示し、マップは“いつまでに何を達成するかの計画”を示す。私たちはこの二つを併用することで、学習の全体像と日々の活動をリンクさせられる。





















