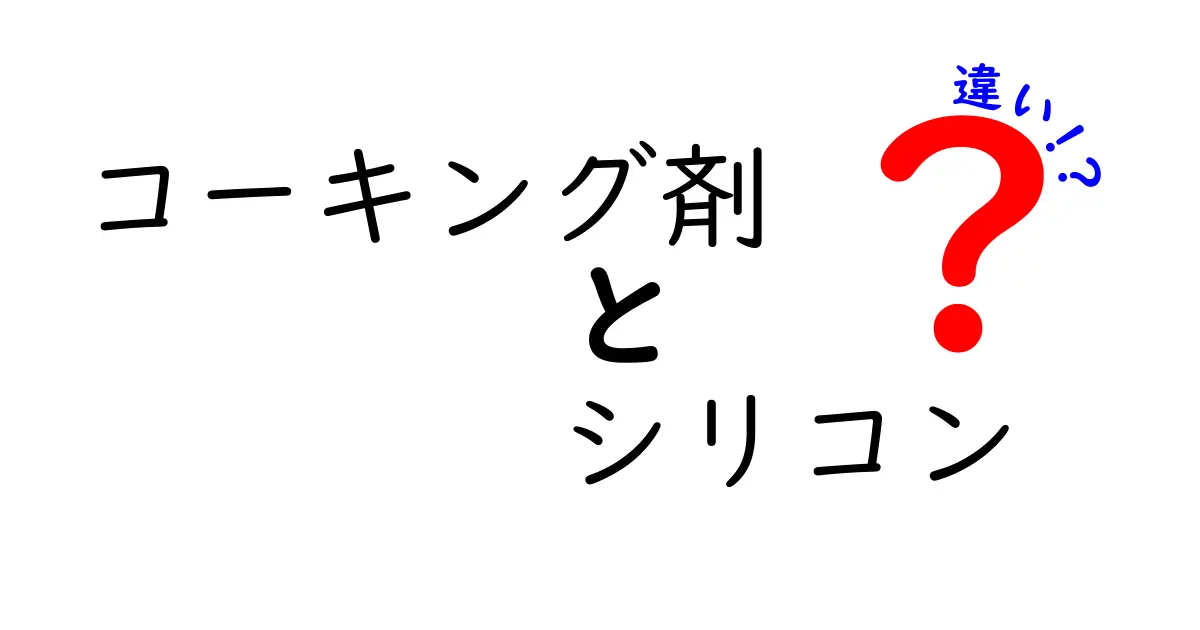

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:コーキング剤とシリコンの違いを正しく理解する
コーキング剤とシリコンは家庭の修繕やDIYでよく耳にする言葉ですが、混同されがちな点が多くあります。まずは用語の整理から始めましょう。コーキング剤は「隙間を塞いで水分の侵入を防ぐ目的で用いられる接着・充填の材料全般」を指します。これにはシリコン系だけでなく、ポリウレタン系、アクリル系など複数の素材が含まれます。対してシリコンは材料の名称であり、耐水性・耐熱性・柔軟性に優れた樹脂系の代表格です。日常の現場では「シリコン系のコーキング剤」という表現をよく見かけますが、正確には「シリコン系コーキング剤」もその一種です。つまり、コーキング剤は使い方のカテゴリであり、シリコンはその中の素材の候補のひとつと考えるのが適切です。
この区別を理解しておくと、場所ごとに適した材料を選べるようになり、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。たとえば水回りや外部の接合部では防水性が高い材料が求められ、木材や金属の結合部では下地処理や塗装との相性を確認することが重要です。コーキング剤の世界には湿気によって硬化するタイプなどさまざまな仕組みがあり、湿気によって硬化するタイプ、耐候性を重視したタイプ、塗装との相性を考えたタイプなどが存在します。これらを理解することでDIYの成功率は格段に高まります。
このガイドではコーキング剤の主要な種類とシリコンの特性をわかりやすく比較し、用途別の選び方や施工時の注意点、長期的な維持管理のポイントを丁寧に解説します。読み進めるうちになぜあの場所にはあの素材が適しているのかが見えやすくなり、実際の作業で役立つ知識が身についていきます。
ここからは具体的な違いのポイントと使い分けのコツを詳しく見ていきましょう。
用途と素材の違い:どう使い分けるべきか
コーキング剤には主にシリコン系、ポリウレタン系、アクリル系などがあり、それぞれ特性が異なります。シリコン系は防水性と耐候性が高く、浴室やキッチンの水まわり外部の接合部にも適しています。ただし塗装が必要な場合には密着性の注意が必要で塗料の種類を選ぶ必要があります。ポリウレタン系は接着力と柔軟性が高く、木材やコンクリートなど表面が動く場所に適していますが、耐水性はシリコン系に比べて劣ることがある点に注意です。アクリル系は室内の目地補修に向いており扱いが容易ですが、基本的には防水性能や耐候性が低いため屋外には適しません。
用途ごとに求められる性質は異なります。水回りでは防水性と長寿命を、外部では耐候性と耐久性を重視します。環境条件が厳しい場所では表面の下地処理や密着剤の選択が作業結果を大きく左右します。次の表は代表的な素材の特徴と適した用途の目安を整理したものです。
| 項目 | 素材の種類 | 主な特徴 | 用途の例 |
|---|---|---|---|
| 耐水性 | シリコン系 | 高い防水性と長期耐候 | 浴室のシーリング、外部窓回り |
| 接着力 | ポリウレタン系 | 高い接着力と弾性 | 木部とコンクリートの接着部 |
| 作業性 | アクリル系 | 水性で扱いやすい | 室内の隙間補修 |
正しい選び方と使い方のコツ:現場で役立つポイント
まずは現場の条件と目的を整理します。水回りか外部か、動きが大きい箇所か小さい箇所か、そして仕上げで塗装をするかどうかを確認します。次に製品ラベルを読み、耐水性・耐候性・密着性・充填量などのキーワードを比較します。温度と湿度の条件も重要で、暑すぎたり湿度が高いと硬化時間が長くなることがあります。施工前には下地を清掃して油分を完全に取り除き、乾燥させてから作業を開始します。下地の状態が悪いとせっかくのコーキング剤も剥がれやすくなるためです。塗装面に密着させたい場合は塗装適合のある製品を選び、塗料との相性テストを行いましょう。
施工のコツは養生と均一な充填です。隙間が広いときは充填剤を段階的に押し込み、ヘラで均一に整えます。養生テープを使って余分な粘着を防ぐと美観が保てます。硬化時間中は水やほこりを避け、養生期間を守ることが長期耐久につながります。仕上げは指やヘラの滑りを良くするために少量の水または専用の滑り止め剤を使うと、縁がきれいに整います。
最後にメンテナンスの観点です。定期的に状態を点検し、ひび割れや黒ずみが見られたら早めに補修します。特に浴室や台所など水分が多い場所はカビの発生にも注意が必要です。清掃と換気を日常的に行い、長期的な耐久性を保つことが美観と機能を保つ秘訣です。
友達との雑談風に話すとこんな感じだ。シリコンという材料は確かに水に強く長持ちするけれど、場所によっては密着性が悪くなることもあるんだ。浴室のような水回りではシリコン系が頼りになる。だけど木の床や塗装面の上では別の材料を選ぶ必要がある。つまり 何を貼り付けるのか どのくらい動くのか 乾燥時間はどうか こうした条件を一つ一つ確かめないと失敗する。だから素材の違いを知っておけば、現場での迷いが減り作業もスムーズになる。それと最初の準備が大事だよ。下地をきれいにしておくと、仕上がりがぐんと良くなるんだ。





















