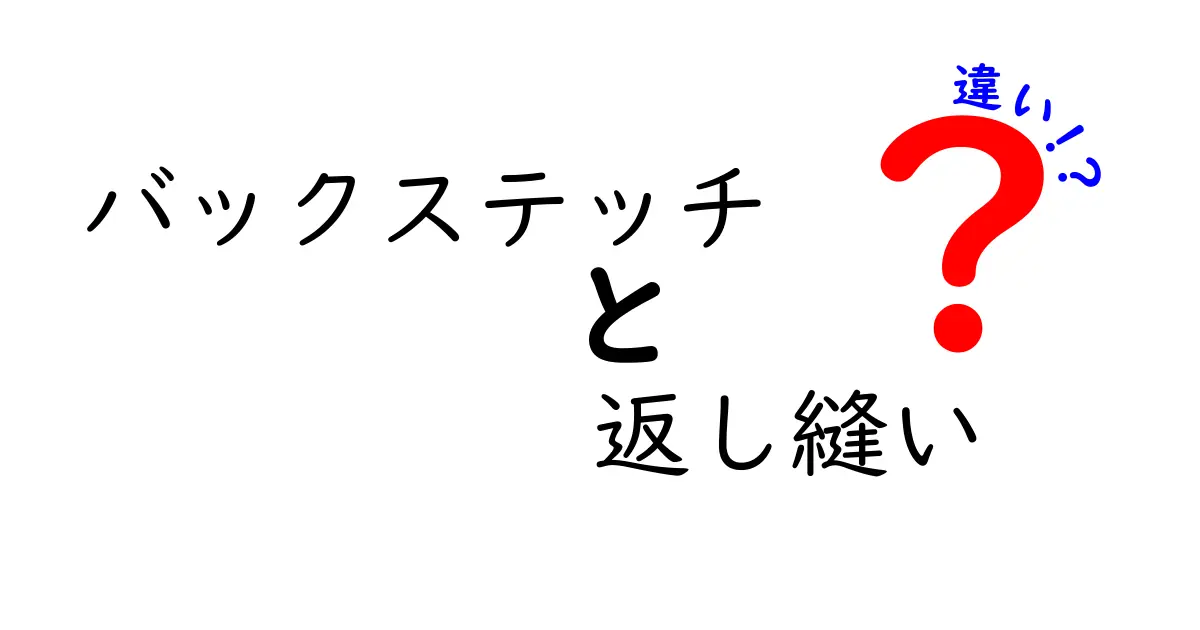

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バックステッチとは何か、どんなときに使うのか
バックステッチは、糸を前進させてから後ろに1針戻るように縫う、連続して短い針目を作る縫い方です。主に輪郭やアウトラインをはっきりと描くために使われ、布地の端を止めるのにも活躍します。初心者でも練習しやすく、表から見える線を美しく整えるのが特徴です。返し縫いと混同されることもありますが、本来の使い方には大きな違いがあります。バックステッチが終わっていれば、縫い目は滑らかで、布の繊維の向きに対して垂直になるように揃えやすくなります。
このセクションでは、基本的な手順とコツ、道具の選び方について詳しく説明します。
用語の整理として、バックステッチは「輪郭を作る線」や「強い縫い目の形成」に適している点をまず押さえましょう。糸の色を生地と同じ色にすると縫い目が目立たず、逆にコントラストをつけたい場合は糸の色を変えると見た目がはっきりします。縫い方としては、針を布の表側で出し、次に裏側へ戻るとき少しだけ布の裏側で新しい目を作るのが基本パターンです。この動作を連続して行うと、1本の線が途切れずに続く“実用的なライン”を作ることができます。
道具としては、針は細身で先が鋭いもの、糸は布地の耐久性と色味に合わせて選ぶと良いでしょう。
最後に、バックステッチをうまく見せるコツをまとめます。均一な目の大きさを保つためには、縫い目の長さを一定にする練習が欠かせません。糸のテンションは緩すぎても強すぎてもダメで、適度な張りを保つことが美しい縫い目につながります。実際の作品では、縫い始めと縫い終わりをしっかりと固定するための“返し縫い風の停止”を使い分けると、実際の線が崩れず長持ちします。さあ、次のセクションでは返し縫いについて詳しく見ていきましょう。
返し縫いの役割と実践方法
返し縫いは、布を縫い合わせるときの端部を確実に固定するための止まりの縫い方です。縫い目の末端を「戻る動作」でしっかりと止めることにより、布がほどけるのを防ぎます。特に衣類の縫い目の端やファスナー周り、裾の処理などで活躍します。返し縫いは、縫い始め・終わりの処理としてだけでなく、細かい箇所の追加の固定にも使われます。プロの現場では、縫い代の処理をすませた後、数目を戻って再度進む“短い戻し”で結び目を作る方法が一般的です。
このセクションでは、基本手順と注意点を詳しく解説します。
手順のポイントとしては、(1) 糸の張りを均等に保つこと、(2) 布の表と裏の見分けを正しく行うこと、(3) 端の処理は小さな縫い目で終わらせることです。実際には、布端に沿って小さくU字状の戻り縫いを作る、または末端の1〜2針を“返し縫い”として重ねる方法がよく使われます。いずれも「布がほどけにくい」という目的を最優先に設計されています。練習としては、布をあらかじめ仮止めしてから糸をかけ、端を数センチだけ返し縫いしてみると良いでしょう。
返し縫いは、基本の縫い方を安定させるための“保険の縫い”と考えると理解しやすいです。
注意点としては、過度に長く返し縫いをしすぎると布の厚みを逆に押し広げてしまうことがある点です。布地の素材に合わせて、1〜3針程度の短い戻りを繰り返すのが無難です。また、縫い目が乱れる原因として、糸を引く力が強すぎる場合があります。締めすぎないように、針と糸の角度を直角に近づける練習を重ねてください。こうした小さなコツが、最終的な仕上がりの堅牢さを大きく左右します。
違いをはっきりさせる比較表と使い分けのポイント
ここではバックステッチと返し縫いの“使い分けの理由”を、分かりやすく整理します。写真で見比べると、バックステッチは細く連続した線として表面に現れ、返し縫いは端の固定性を重視して末端を留める役目を果たします。見た目の違いだけでなく、目的・強度・使う場面にも差があります。表を使って、どの状況でどちらを選ぶべきかを整理します。
以下の表は、初心者にも一目で分かるように作成しています。
このほかのポイントとして、布地の種類や糸の太さによって最適な縫い方は変わります。混在させて使う場面も多いので、実際の作品で違いを体感しながら覚えるのが最も効率的です。練習用の小さな布で、2種類を交互に縫い比べると、目の大きさや縫い目の安定感の差が体感できます。最後に、実際の仕上がりを美しくするコツとして、縫い始めと終わりをしっかり固定すること、糸の色を生地と合わせるか、コントラストをつけるかを選ぶこと、これらを習慣づけることをおすすめします。
まとめと覚えておくポイント
本記事では、バックステッチと返し縫いの基本的な違い、使い分けのポイント、実践時のコツを詳しく解説しました。
初心者の方はまず、バックステッチで輪郭を練習し、次に返し縫いの固定を確実にできるよう練習します。両方の縫い方は、布の種類や用途によって最適な組み合わせが変わるため、同じ作品内で使い分ける技術を身につけることが大切です。
文章だけでなく、手元の布と糸を見ながら実際に指で縫う感覚をつかんでください。
この知識を元に、あなたの作品に合った縫い方を選べるようになると、仕上がりがぐんと安定します。
ねえ、返し縫いについてもうひと押しだけ深掘りしてみよう。返し縫いって、ただ布の端を止めるだけの作業と思われがちだけど、実は作品の“安全装置”みたいな役目もあるんだ。初めて見たときは、どうしても笑っちゃうくらい端っこの小さな動作だけど、その一つ一つの戻り針を丁寧にやると、縫い目の端がほどけにくくなる。僕らが布小物を作るとき、糸のテンションが強すぎると布が伸びて縫い目が波打つことがある。それを防ぐためには、返し縫いの戻りを“短く”設けて、最後にもう一度前に進むリズムを作るのがコツ。さらに、素材によって返し縫いの長さを調整する柔軟性も大事。例えばデニムのような厚手の布では、戻りを2〜3針程度にしておくと後の縫製が楽になる。返し縫いは練習次第で感覚が身についてくる技術なので、最初は少し時間をかけて、端をしっかり固定できる感覚をつかもう。こうした地道な積み重ねが、作品の完成度を大きく左右するんだよ。
次の記事: 芯地と裏地の違いを徹底解説!初心者にも分かる洋裁の基本 »





















