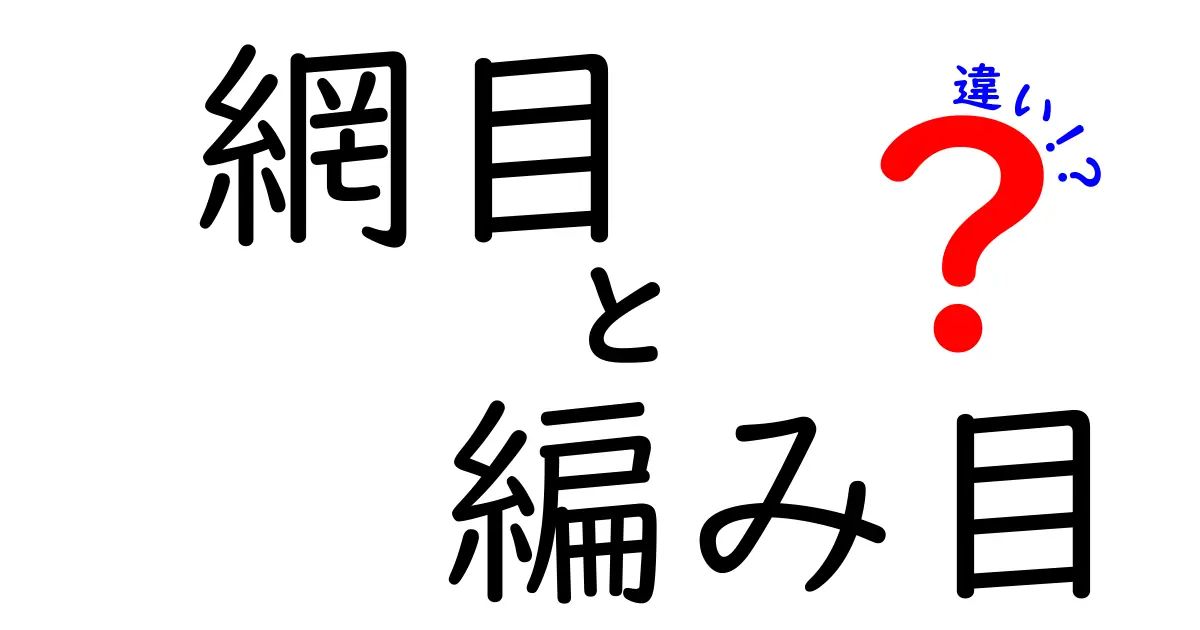

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
網目と編み目の違いを理解する
日常生活で『網目』と『編み目』は混同されがちですが、意味と使われる場面には大きな違いがあります。まずは基本を整理します。網目は“網の目の連なり”をイメージする言葉で、布の穴や格子状の構造そのものを指すことが多いです。対して編み目は糸を編む工程で生まれる「目(ひとつのループ)」を指す語で、編み方の技術的な要素を示します。網目は全体の形状や透け感、強さといった性質を説明する言葉として使われ、編み目は個々の目の形状、配置、密度を指す言葉として使われます。例えばニット製品の表面を見たとき、細かくねじれた小さな穴の連なりが網目の特徴として目立つ場合は、それが網目の“外観”です。一方で同じニットでも、初めの目をどのように作るか、何段編むかといった工程の説明には編み目という語が自然に出てきます。ここでのポイントは、網目が材料の物理的な“つくり方の結果”を指し、編み目がその作業の“手の動きと設計”を指すという点です。中学生にも伝えやすくするなら、網目は布の“網の目”そのもの、編み目はその網の目を作るときの「1つずつの目のこと」と覚えるとよいです。さらに、言い換えのコツとして、網目と編み目を置き換えて文にしてみる練習をしてみてください。たとえば「この生地は網目が大きい」→「この生地の網目は大きいが、編み目はどのくらいかは別問題です」と言い換えると、意味の違いを体感できます。
このような理解を土台に、次のポイントを押さえると説明がスムーズになります。第一に網目は布全体の疑似的な地図のように表現でき、透かしや強度の話題にも直結します。第二に編み目は糸のピッチ、目の大きさ、段の数といった“作業の設計図”を思い起こさせる語です。第三に実際のテキスタイルを説明するときは、網目の雰囲気と編み目の技術的な要素を分けて考えると、伝える情報が整理されて伝わりやすくなります。以上を踏まえれば、作品の特徴を相手に正しく伝えられ、授業ノートや手芸クラブの説明もスムーズになります。
見分け方と実践ポイント
このセクションでは、網目と編み目を日常の手芸・衣料の中でどう見分け、どう使い分けるかを具体的に解説します。まず第一のコツは「穴の形と連なりを観察すること」です。網目は格子状の穴が連なる構造で、布の表面から透けたり重なったりする雰囲気を作ります。逆に編み目は連続するループのつながりでできており、布の厚みや柔らかさは編み目の密度と段数で決まります。第二のコツは用途を確認することです。網目の低密度な布地は透け感を活かすファッション・インテリア用品、網戸のような機能性の場面に適しています。編み目はセーターやマフラー、帽子といった着衣用の生地に使われ、保温性や手触りを調整する鍵になります。第三は技術用語の使い分けを意識することです。編み物の説明書では「編み目」「目数」「段数」などの用語が頻出します。実際の作業では、編み目の細かさを変えると全体の網目感にも影響します。ここまでを理解しておくと、設計図を思い描きながら作品を作り、友人に説明するときも誤解なく伝えられます。具体例として、薄手の夏物のセーターを作る場合は編み目の密度を調整して通気性と肌触りを両立させます。一方で厚手のブランケットや帽子を作る場合には網目の穴のサイズを意識して、保温性を高める工夫をします。こうした設計意図を言葉に置き換えると、友人や先生に作品の特徴を伝えやすくなります。
編み目を深掘りたいと思います。私が初めて編み物教室に通って感じたのは、先生の一言『編み目は糸の呼吸だ』という言葉でした。細い糸を使って小さな編み目を作ると肌触りが柔らかくなり、逆に太い糸で大きな編み目にすると風通しが良く涼しく感じます。編み目の密度は見た目だけでなく着心地にも影響します。高校生の頃、友人とマフラーを編んだとき、目数を多くして長さを作る案と、ピッチを小さくしてぎゅっと詰まった生地にする案で意見が分かれました。結局はデザインと機能のバランスで決定しました。編み目の話題は数学的な規則性と感性の両方を育ててくれ、日常の雑談にも微妙な違いを感じ取る力を与えてくれます。例えば帽子を誰かに贈るとき、編み目の大きさを変えるだけで印象が大きく変わることを友人と発見した瞬間は、手仕事の楽しさを再認識するきっかけでした。今では、糸選びから編み方、段の数まで、編み目の一本一本を観察する習慣が私の創作の土台になっています。





















