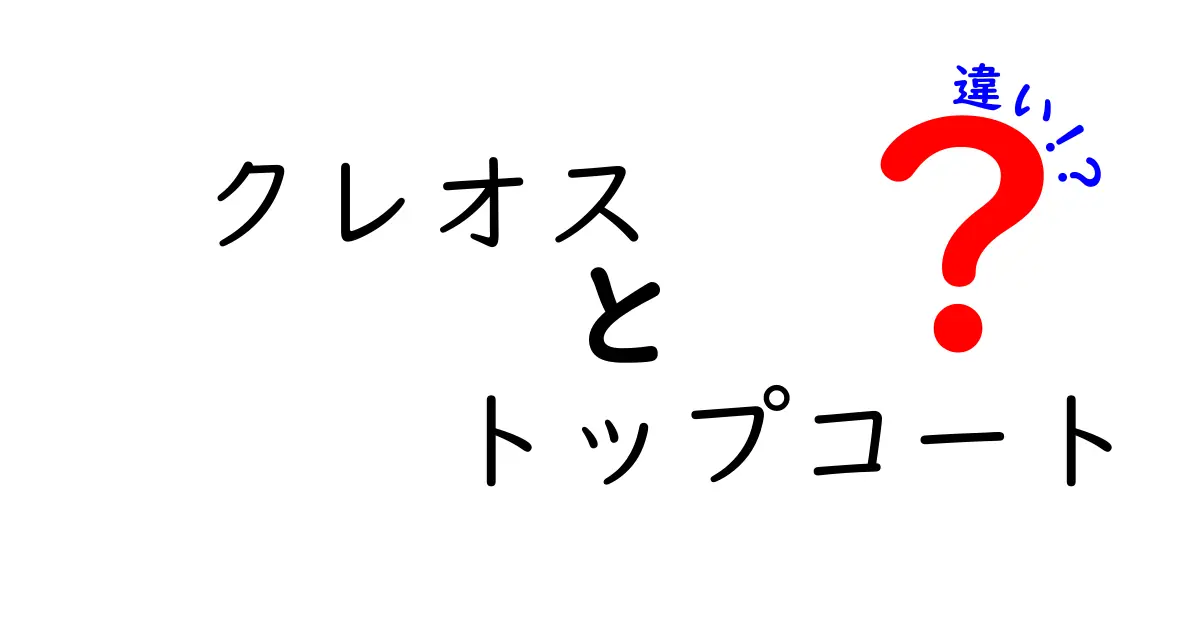

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クレオスのトップコート違いを徹底解説する理由
プラモデルの仕上げで最終段階に使うトップコートは、作品の見た目と耐久性を大きく左右します。クレオスは多彩なトップコートをラインナップしており、艶有り・半光沢・つや消しなどの仕上がりだけでなく、溶剤系・水性系・硬化時間・塗布の厚さにも違いがあります。この違いを理解して適切なタイプを選ぶことで、塗膜のヒビ割れを減らしたり、長期間きれいな状態を保つことができます。特に写真を撮る人には艶の有無が写真映りを左右しますし、実車のような質感を出したい場合は半光沢が効きます。この記事では、初級者にも分かりやすいように、代表的な種類と使い分けのコツを、実際の塗布手順を想定しながら順を追って解説します。購入前に確認すべきポイントを押さえれば、後悔せずに作品に合ったトップコートを選べます。
また、トップコートは乾燥時間や取り扱いのルールも異なります。薄く重ね塗りをする場合と厚く塗る場合で乾燥時間が変わり、温度・湿度が影響します。湿度が高いと白化になりやすく、風通しが悪い場所では粉体が残ることがあります。使い方のコツとしては、まず基底塗装が完全に乾燥してから重ね塗りをする、薄い層を数回重ねることで均一な仕上がりを作る、という点を意識すると良いでしょう。
また、薄い層を重ねると美しい艶加減を保ちつつ、耐久性も上がります。
この表は代表的なタイプの比較を quick に確認するためのものです。実際の製品名やシリーズ名によって微妙に性質が変わることがあるので、購入時には最新の商品情報を確認してください。
トップコートの主な種類と特徴
クレオスのトップコートには、艶有り・半光沢・つや消しの基本3種に加え、水性と溶剤系という塗膜成分の違いがあります。艶有りは光を反射して美しい仕上がりを作りますが、傷が目立ちやすい、写真映りが強すぎるという欠点も。つや消しは陰影を自然に出し、ウェザリングの効果を引き出します。半光沢は両者の中間で実車の質感に近づけやすい、現場での万能型です。水性は匂いが控えめで換気の条件が厳しくても使いやすい反面、乾燥時間がやや長いことがあります。溶剤系は乾燥が早く硬度が高い一方、換気と手袋の着用を忘れずに、部屋の換気を十分に行う必要があります。
使い分けのポイントとして、写真映えを重視する場合は艶有り、質感と陰影を重要視する場合はつや消しや半光沢を選ぶと良いです。ウェザリング後の仕上げにはつや消しを組み合わせることで、汚れの再現性が高まります。水性と溶剤系の違いは、作業環境によって決めるのが鉄則です。室内で換気が難しい場合は水性を選ぶと便利ですし、乾燥を早めたいときは溶剤系を選ぶと効率が良いでしょう。こうした判断材料を一覧にしておくと、初めての人でも迷いにくく、失敗を減らせます。
- 水性トップコートは匂いが控えめで、換気条件が厳しい場所でも扱いやすい。
- 溶剤系トップコートは乾燥が速く、耐摩耗性・耐候性が高い傾向がある。
- 塗布のコツは、薄く何度も重ね塗りすること。厚塗りは乾燥ムラの原因になることがある。
- 作業温度や湿度に敏感。夏場は乾燥が早く、冬場は乾燥が遅くなることがある。
使い分けのコツと実践的な選び方
実際の現場では、仕上がりのイメージと塗膜の強度のバランスを見ながら選ぶのが基本です。例えば、完成後に写真を多く撮影する作品なら艶有りで映えを狙い、ウェザリングを活かしたリアル系ならつや消しを主体にして陰影を強調します。裏を返せば、どのタイプを選んでも基礎の塗装が乾燥していないと美しく乗りません。そこで、基礎塗装が完全に乾燥してからトップコートを塗る、薄膜を重ねる、温度管理を徹底する、という基本を守ることが重要です。さらに、パーツの素材(プラスチック、金属、樹脂など)によって吸い込み方が変わることがあるため、少量の試し塗りを最初に行うと安心です。
塗装現場の小さな工夫として、保護マスキングを使って塗料のはみ出しを避ける、乾燥中は埃を避けるため風を送りすぎない、などの点も覚えておくと良いです。最終的には、自分の作品のコンセプトと、見る人がどう感じるかを想像しながら選択することが、最も大事なコツと言えるでしょう。
僕が初めてクレオスのトップコートを選んだとき、艶有りとつや消し、どちらが新しい表現になるのか悩んだんだ。結局、艶有りを選んで写真を撮ると、反射光が強くて細部が見えなくなることも。そこで半光沢で陰影を保つ方法を試したら、ウェザリングの質感が生きて作品が立体的になった。結局、大事なのは“何を強調したいか”を決めてから塗ることだと分かった。その場の空気感で最適解は変わる。夏の夕焼けみたいに柔らかい光を出したいときは半光沢、夜の模型写真なら艶有りが映える。つまり、同じ塗料でも光の条件や写真の撮り方でベストな選択が変わる。次回はウェザリングの質感とトップコートの組み合わせをさらに実験して、作品の世界観をどう変えるかを詳しく深掘りしてみたい。
前の記事: « アクリル塗料とエナメル塗料の違いを徹底解説!使い分けのコツと実例





















