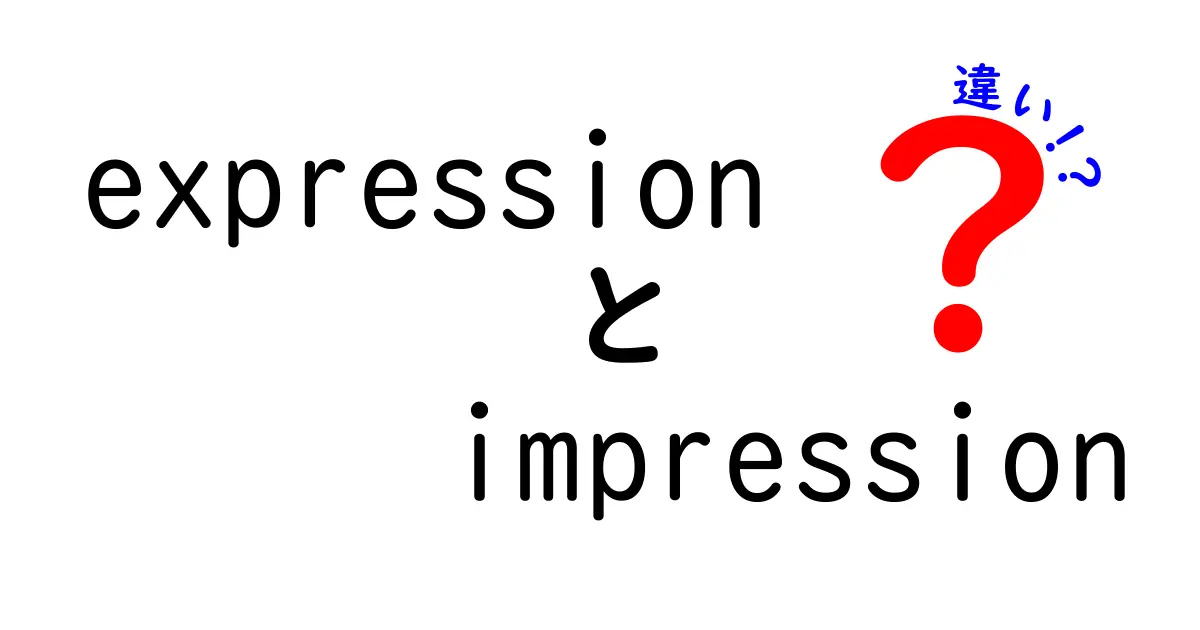

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
expressionとimpressionの違いを理解する基本
「expression」と「impression」は、日常の会話や英語の学習でよく混同されがちな言葉です。しかし、意味と使い方はしっかりと区別する必要があります。expressionは発信側の行為そのものであり、言葉・表情・身振り・文章・作品など、外へ向けて伝える具体的な表現のことを指します。一方でimpressionは受け手が感じる印象や感想のことです。つまりexpressionは伝える行為の内容、impressionは受け取る側の心の反応を表します。
この違いを理解すると、伝えたいことをどう表現するかと、相手にどう伝わっているかを別々に考えられるようになります。
例を挙げると、教師が黒板に丁寧に文字を書き、分かりやすい例を並べる行為そのものがexpressionです。生徒がその字の読みやすさや色の見え方を通して受ける印象がimpressionです。
また、絵画や音楽でも同じ考え方が使えます。絵の技法や色使いはexpression、見た人が感じる雰囲気はimpressionです。こうして、発信と受信の役割を分けて考えると、伝わりやすさを高めるコツが見えてきます。
この後のセクションでは、使い分けの実践的方法と具体的な例文を紹介します。
日常での使い分けのコツと実例
英語の学習だけでなく、日本語の感覚でも、expressionとimpressionの使い分けは練習で身につきます。まず大切なのは表現の対象をはっきりさせることです。expressionの対象を明確にすることで、impressionがどう生まれるのかを想像しやすくなります。具体的には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
1) 伝えたい内容の表現を選ぶときはexpressionを重視する。何をどう伝えるかを最初に決める。
2) 相手に与える印象を予測するときはimpressionを考える。声のトーン、表情、間の取り方などが影響します。
3) 英語での用法では、expressionは「表現する手段」や「表現力」という意味で使われ、動詞のexpressと結びつきます。impressionは「印象」という意味で名詞として使われ、形容詞派生語のimpressiveなどと組み合わせることが多いです。
日常の会話や作文にもこの二つの視点を取り入れると、伝わり方がぐんと変わります。例えば、文章の表現を工夫することで読み手に伝わる“印象”をコントロールできるのです。最後に、実践的な練習として、毎日一つの出来事を自分の表現と相手の印象の二つの視点で振り返る習慣をおすすめします。以下の表も、使い分けの感覚を養うのに役立ちます。
放課後のカフェで友だちと話していたときのこと。私はまさにexpressionとimpressionの会話をしていたんだと思う。友だちが新しい文章を読んでくれたとき、私が伝えたい意味をどう表現したのかがexpression。反対に、友だちがその文章を読んで受け取った感じがimpressionだ。私は自分の表現をもう少し分かりやすくするにはどう直せばいいか、友だちはその表現が伝わっているかをどんな風に感じているかを一緒に考えてくれた。だから、言葉の選び方一つで相手の印象は大きく変わるってことを、改めて実感したんだ。





















