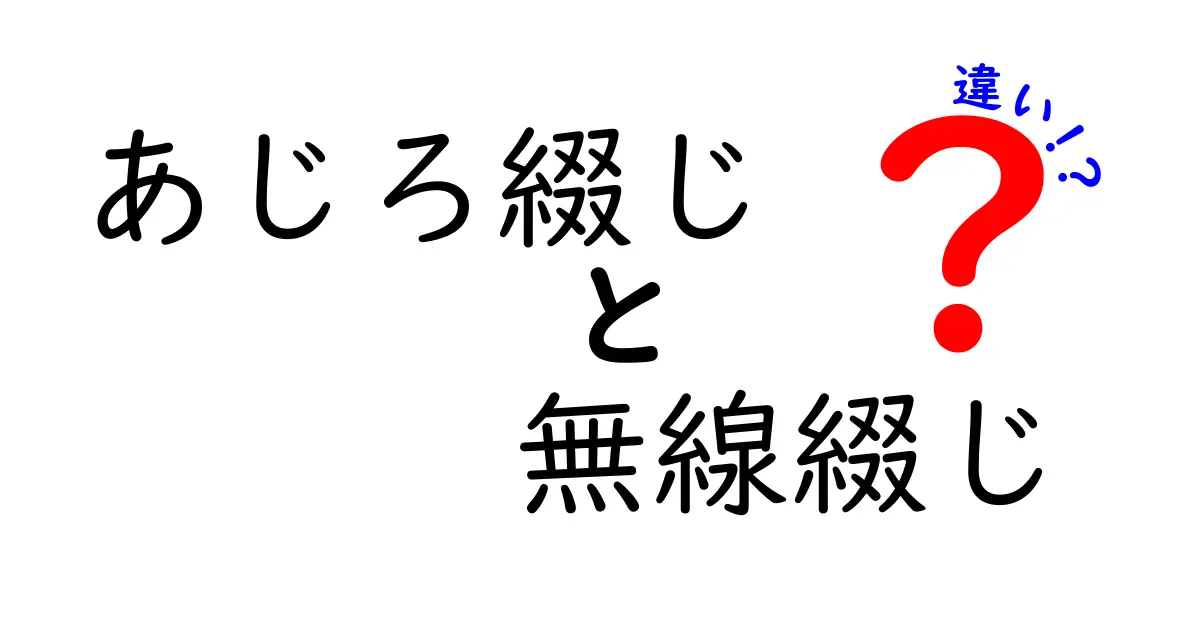

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
あじろ綴じと無線綴じの違いを知る前提
本記事は、書籍の背を綴じる伝統的な技法「あじろ綴じ」と、現代の大量印刷でよく使われる「無線綴じ」の違いを、初めて学ぶ人にも分かりやすく解説します。まず結論としてあじろ綴じは糸で背を縫う伝統的な技法で、背の部分が糸で縦に装着された状態になります。これに対し無線綴じは背に糊を使って接着する現代的な方法です。見た目の違いだけでなく、開き方・耐久性・コスト・修理のしやすさなど、さまざまな点で差が生まれます。
この差を理解するには、まず「背とは何か」「綴じの仕組みはどうなっているのか」を押さえるのが近道です。背には本文の紙を束ねる芯があり、そこに糸や糊が働きます。あじろ綴じでは背の表情に糸の縫い目が現れ、手に触れたときの温かさや伝統的な美しさを感じられます。一方、無線綴じは背を糊で固めるので、紙の束を密着させて平らな背を作ります。仕上がりの雰囲気はシンプルで現代的ですが、修理や再製作の場面では工夫が必要になることが多いです。
この章のポイントは、仕組みを理解するほど、どんな本に適しているかが分かる点です。耐久性・開きやすさ・コストといった観点を次の章で詳しく見ていきましょう。
歴史と構造の比較
あじろ綴じは江戸時代以降、日本の伝統的な製本技法として長く使われてきました。背の糸が紙の束を綴じ、時間とともに風合いが増すのが特徴です。実務としては、和紙や布カバーとの組み合わせが美しく、コレクターや美術書の制作にも用いられます。一方、無線綴じは20世紀後半の印刷技術の発展とともに普及しました。大量生産に向くように背の部分を糊で固め、機械的にページを固定します。その結果、コストが下がり、薄い本から厚い本まで幅広く対応できるようになりました。
構造の違いをさらに詳しく見ると、あじろ綴じは背の“糸の列”が背表紙を形成します。ページは小さな冊子状のユニット(シグネチャ)を縫い合わせ、全体としては柔軟性を保ちながら連結します。無線綴じはシグネチャをすべて糊で固定し、背の部分が平滑な棒状になるため、机の上で広げやすいという特徴があります。
用途と選び方のポイント
実際に本を作るとき、どちらを選ぶべきかは「用途」と「予算」で決まります。美術書・詩集・限定版など、背を見せたデザインが大事で、手にとって楽しむ要素が強い場合はあじろ綴じが好まれます。教科書・雑誌・普及本のように大量に作られ、コストを抑えたい場合は無線綴じが一般的です。選び方のコツは以下の点です。開き方の角度、耐久性、修理の容易さ、そして見た目の印象です。長い期間使う予定がある本は耐久性を重視してあじろ綴じを選ぶと良いでしょう。
また、表紙素材や糊の種類にも注意してください。粘度が高い糊を使うと背が硬くなり、開き方に影響します。逆に低粘度の糊だと背が崩れやすくなることがあります。
総じて、使い道と予算を天秤にかけ、デザインと機能のバランスを考えた判断が大切です。
実例と表で見る特徴
以下の表は、実務でよく比較されるポイントを簡潔に整理したものです。実際の書籍を選ぶときに役立つ基準として覚えておくと便利です。
この表を見れば、どんな場面に向くかの目安がつくはずです。開きの角度を重視するなら無線綴じ、伝統美と長期の修理性を重視するならあじろ綴じが適しています。最後に、本文の要点をまとめておきます。
結論として、教育用・芸術的な価値を重視する本にはあじろ綴じ、コストと大量印刷を重視する本には無線綴じが一般的です。必要に応じて、製本職人に相談して、最適な組み合わせを選ぶと良いでしょう。
小ネタとして『あじろ綴じ』の名前の由来を少しだけ。網代綴じは江戸時代から続く伝統的な技法で、背の糸が“網の目”のように見えることからこの名が付いたとされます。実際には背の穴や袋状の芯を使い、糸を交差させて丁寧に綴じます。単なる装飾ではなく、開いたときの背のしなりや紙の反り方を支える工夫が含まれており、使い込むほど風合いが増すのが特徴です。
前の記事: « 中綴じと袋とじの違いを徹底解説|読み物の背と特典の秘密を知ろう





















