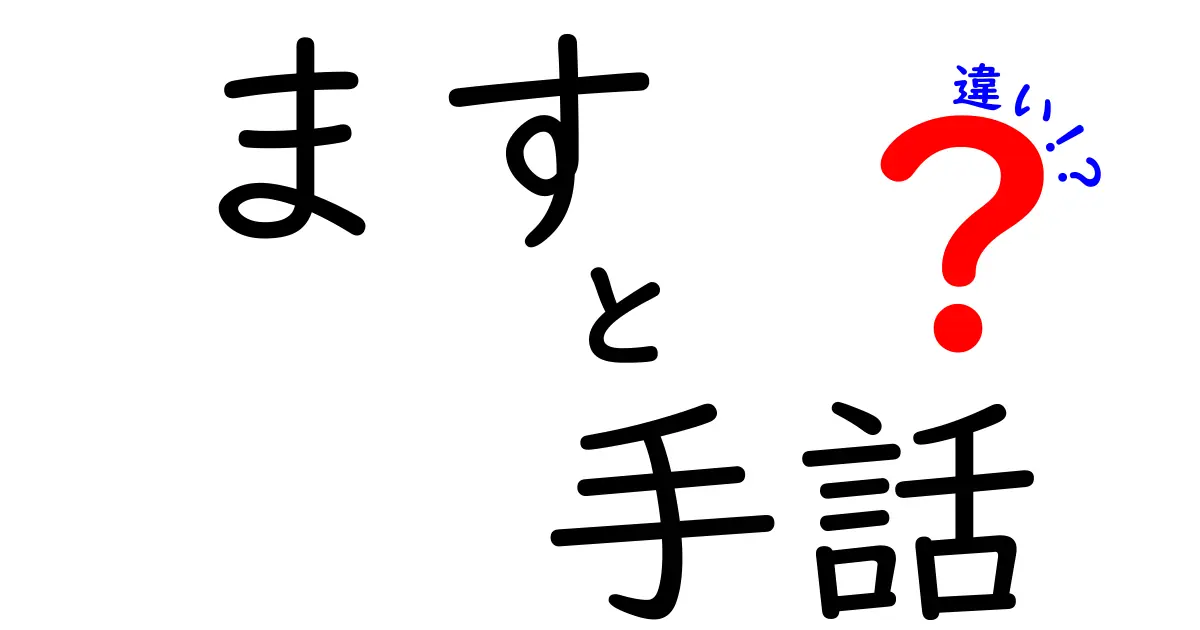

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ますと手話の違いを理解する基本ポイント
まず基本的な点として、ますは日本語の動詞の活用形であり、手話は言語としての体系を持つ視覚的なコミュニケーション手段です。「ます」は話し言葉や書き言葉の丁寧さを示す語尾で、動詞の語幹に接続します。
手話にはこのような語尾変化は基本的にはありません。手話は言語であり、語順や非手話的表現、顔の表情、体の動きなどを使って意味を表します。
例えば「食べます」は丁寧な表現であり、会話の場面、目上の人、初対面の相手などで使われます。一方、手話では意味を示す最小単位は手の形のサイン、手話独自の語順、そして顔の表情や動作の強さで決まります。日本語の「ます」をそのままサインに置き換えることはできません。
この違いを理解することは、聴者と聴覚障害者の双方がスムーズにコミュニケーションをとるための第一歩です。丁寧さは手話では「丁寧なサイン」と「間の取り方」「視線の使い方」などで表現します。
また、語彙の意味だけでなく、表情・体の動き・場所の配置といった非言語要素が意味を決定づける点も忘れてはいけません。
| 項目 | ます | 手話 |
|---|---|---|
| 役割 | 丁寧さの語尾・文法的要素 | 意味・関係性・感情を表すサインと非手話的表現 |
| 表現主体 | 音声言語・文字表現 | 手の動き・顔の表情・視線・空間配置 |
| 文法の性格 | 形態的変化が中心 | 独立した言語体系・語順も重要 |
聴覚と視覚の違いがもたらす使い方の差
手話は視覚を中心とした情報伝達の体系です。話す代わりにサインを使い、顔の表情・眉の動き・口の動きなどの非手話的信号が意味を変えます。
この非言語的情報は意味を強く左右するので、同じサインでも表情のニュアンスで意味が変わることがあります。
日本の手話には地域差や個人差があり、同じ意味のサインでも地域やグループで微妙に違うことがあります。聴覚情報が不足している場面で視覚情報だけに頼ると誤解が生じやすいので、相手の反応をよく見ることが大切です。誤解を減らすには、手話を使う人と話すときにゆっくり分かりやすく話し、相手が理解しているかを確認する習慣が役立ちます。
教室や学校の場面を想像すると、先生が口頭で話すだけではなく、手話通訳者が介在する場合、受け手は通訳者と話すことになります。通訳者がいるときは、通訳者を直接話しかけず、サインを理解する際には表情や体の動きと合わせて読むようにしましょう。これらの点は「言語としての手話」を理解するうえで欠かせません。
手話を学ぶときは、辞書だけを見ず、実際の会話の流れや場面ごとの表現を重ねて練習することがコツです。
日常場面での誤解と正しい使い方
よくある誤解の一つは「手話=手で話すこと」だという点です。手話は音声の代替ではなく、別の言語体系です。手話はサインと表情、体の動き、目線の配置などを組み合わせて意味を伝えます。単語の意味だけを追うと意味が取り違えやすいので、実際の会話の流れを意識して練習しましょう。
場面に応じた正しい使い方の工夫として、相手が誰か、聴覚障害があるかどうかを事前に確認することが大切です。「手話を使いますか? 書き言葉の方がいいですか?」と尋ねるとよいです。手話が難しい場合はメモや字幕、翻訳アプリを使うとコミュニケーションがスムーズになります。
会話の場では、話す人とサインを送る人の視線が分散しないよう配慮します。手話を使う相手の表情を見ながら、適切な速さでサインを返す練習をすると、誤解が減り会話が楽になります。練習時には現実の場面を想定し、学校・家庭・地域の場面別の表現を増やしていくと良いです。
このような工夫を続けると、ますと手話の違いを自然に受け入れられるようになります。
A: ねえ、最近学校で『ますと手話の違い』を学んだんだけど、手話は別の言語体系で、丁寧さを表す方法も文法も日本語とは違うんだ。B: へえ、そうなんだ。手話はサインと表情と視線の組み合わせで意味を表すんだよね。A: そう。たとえば『食べます』は日本語の丁寧さを示す語尾だけど、手話では同じ意味を表現するのに別のサインと表情の組み合わせを使う。B: なるほど。つまり、同じことを伝えるにも言語が違えば伝え方が変わるんだ。A: その通り。手話は独立した言語で、敬語っぽいニュアンスはサイン自体と表情の取り方で表現される。こうした違いを知ることで、相手に合わせたコミュニケーションが自然にできるようになるんだ。





















