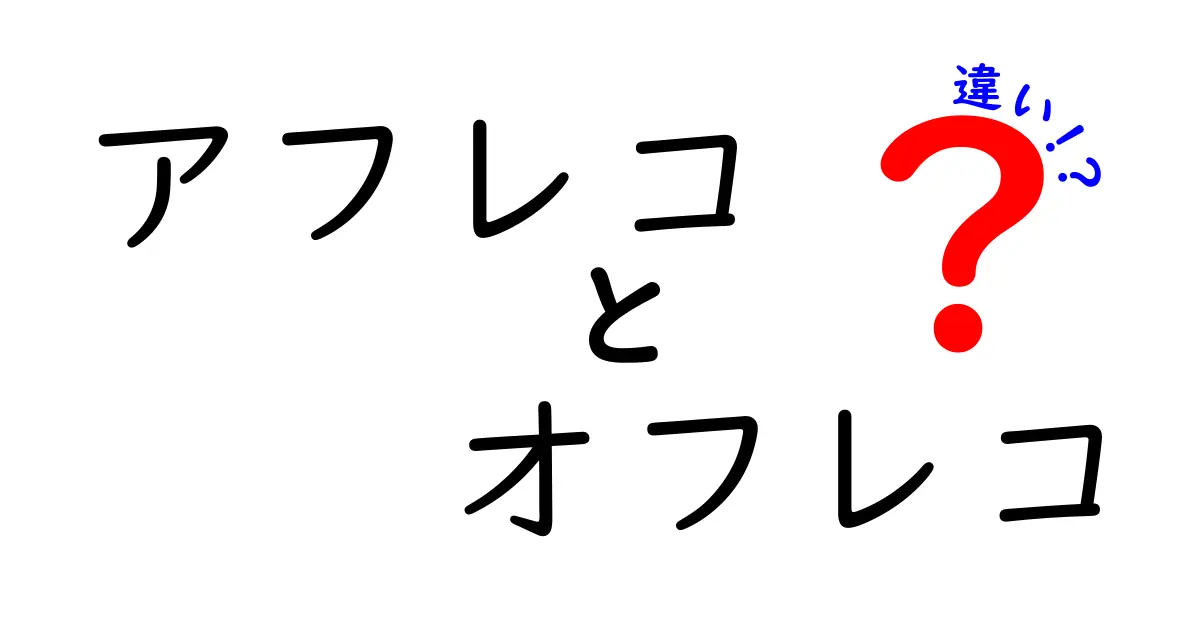

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アフレコとは何か?基本を学ぼう
アフレコは日本語でアフレコ、英語では dubbing に近い作業です。映像を見ながら声を付ける工程で、声優がマイクの前で演技を行い、セリフのニュアンスやタイミングを映像にぴったり合わせます。アフレコの現場では、原作の音声がない、あるいは別の声質を使いたい時に新しく声を録音します。たとえば外国映画の日本語吹替えや、アニメの再録音、ゲームの演出音などが挙げられます。
この作業には演技力だけでなく、口の動きや喉の空気の使い方、マイクの距離や音量の調整、編集時のノイズ処理など、技術的な要素が多く関係します。
アフレコは通常、映像のスケジュールに合わせて進み、監督や演出家が演技のニュアンスを指示します。だからこそ、同じセリフでも声の強さや表情の変化が少し違うだけで作品の印象が大きく変わることがあります。
このため、アフレコの台本には「間の取り方」や「息の使い方」まで細かく指示が書かれることがあり、声優はそれを読み解く力が必要です。子どもたちが映画を見ているとき、違和感を感じるのは演技と映像のズレが理由の一つです。だからこそ、アフレコの現場には長時間のリハーサルや練習、そして多数のトライアルが存在します。
アフレコと見比べるときに覚えておきたいのは、アフレコは「作られた声の世界」を作る作業であるという点です。映像が完成している状態で、それに声を乗せる作業です。実際の現場では、収録中のミスをすぐ修正して、後日別の日に再録することもよくあります。こうした作業の積み重ねによって、作品の雰囲気が決まっていきます。
また、アフレコは技術と芸術の両方を必要とする分野です。マイク前での演技は、普段の会話とは少し違って、音としての美しさを優先します。そのため、演技の自然さと音のクリアさのバランスをとることが求められます。結局のところ、アフレコは視聴者にとってのリアリティを作る大切な工程なのです。
オフレコとは何か?理解を深める
オフレコは一般には情報の公開を控えること、あるいは記録として残らない発言の意味で使われます。ニュースの現場で「これはオフレコだから報道しないでほしい」と言われると、記者はその場の情報を自分の資料や記事には載せません。オフレコの扱いは業界ごとに微妙に違い、場合によっては背景情報を理解するための手掛かりとして使われることもあります。したがって、オフレコの情報は公式な引用には使えない、あるいは後で背景としてのみ扱われると覚えておくとよいです。
オフレコの考え方を正しく理解するには、記者と情報提供者の信頼関係が大切です。信頼があると、提供者は有益な背景情報を共有できますが、それは公開されず、報道の本体には現れません。その結果、読者や視聴者は公式発表と背景情報の間にある差を理解することができ、物語の全体像を把握する手助けになります。
ここでのコツは、オフレコという言葉が示す「公開の自由度の制限」を正確に理解することです。たとえば、ある研究者が新しい治療法の発見過程を話してくれても、それをそのまま記事に載せると研究者の信用を傷つけたり、規制上の問題を引き起こしかねません。したがって、オフレコは倫理と法的な観点からも大切なルールとして機能します。
オフレコが日常会話にも影響を与えるケースがあります。例えば学校の先生や友人との会話で、授業の進路相談や個人的な体験談などを話すとき、話の内容をSNSや公開の場で共有する場合には配慮が必要です。オフレコの精神は、相手を傷つけず、適切な場でのみ情報を共有することです。私たちが取り扱う情報の扱い方を意識することで、信頼を損なわず、円滑なコミュニケーションを保つことができます。
ねえ、アフレコって知ってる? 実は現場の声と画の合わせ方には秘密があるんだ。監督が微妙な呼吸の長さや言い回しを指示すると、声優はその指示を声の抑揚やリズムに変換していく。何度もテイクを重ねるうちに、映像の動きと声の波形がぴったり噛み合う瞬間が生まれる。その瞬間を見逃さないように、作品を観るときは声の強弱や間の取り方にも注目してみよう。そうすることで、ただ見ているだけの視聴体験が、声と言葉の力で深く豊かなものになることを実感できるはずだよ。
前の記事: « 劇作家と脚本家の違いを徹底解説|中学生にもわかる3つのポイント
次の記事: VFXと特撮の違いを徹底解説:映像の作り方がこう違う! »





















