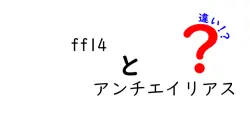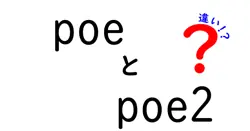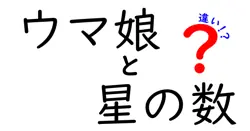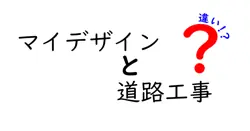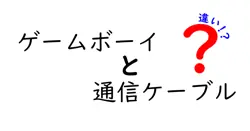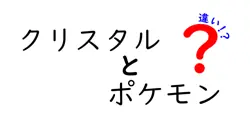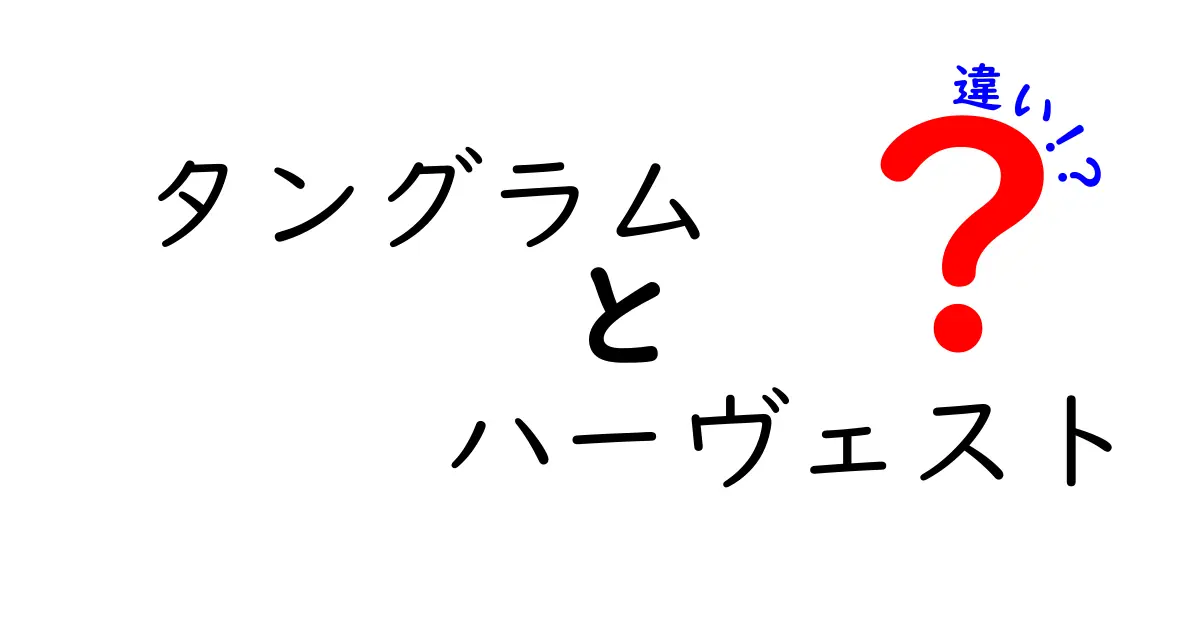

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
タングラムとハーヴェストの違いを明確に知ろう
この二つは見た目がパズルのブロックという点で似ていますが、成り立ちや使い方、学習効果には大きな違いがあります。以下では、まずタングラムの基本、次にハーヴェストの特徴を整理し、それぞれの長所と向いている人、そして授業での活用例を比較します。タングラムは七つのピースだけで、シンプルなルールが魅力です。ピースの形はすべて三角形・正方形・平行四辺形などで、自由に組み合わせて図形を作ります。学習では空間認識、手と脳の協応、粘り強さ、創造力が鍛えられます。一方、ハーヴェストはブロックの形や色、ストーリーが設定され、教科横断的な活動に適しています。テーマに沿って規則やゴールがあるため、協力して取り組む場面が増え、コミュニケーション能力や問題解決のプロセスを観察するのに向いています。ここでは、具体的な遊び方の例、難易度の調節ポイント、家庭での取り入れ方、授業での導入ポイントを、わかりやすく並べていきます。
まずは道具の違いを理解しましょう。
タングラムとは何か?特徴と遊び方
タングラムは中国発祥の知的パズルで、7ピースを使って様々な形を作ります。出発形は大きな正方形で出てくることが多く、ピースは大小の三角形、ひし形、長方形、正方形などの基本形です。遊び方はとてもシンプル。七つのピースをすべて用いて、同じ大きさの正方形を作るのが基本形。そこから、動物、乗り物、人物などの図を作る創作課題へ移行します。
学習効果としては、空間認識能力、図形分解と再構成の思考、手の巧緻性、集中力、そして失敗から学ぶ反復性が挙げられます。難易度はピースの大きさや与えられる図の複雑さで調整可能で、初心者は基本の正方形を作る練習から始め、徐々に複雑な形へ進みます。家庭での使い方としては、タイマーを使って競争するより、完成までの過程を観察して声掛けをするのがおすすめです。
ハーヴェストとは何か?特徴と遊び方
ハーヴェストは季節や物語をテーマにしたパズル系の教材やボードのことで、色と形の組み合わせだけでなく、課題のストーリーを達成することを目標とします。カードやボードに描かれた絵の通りにブロックを配置したり、ブロックを動かして形を作ったりします。遊び方は「テーマ付きミッション」をこなす形式が多く、学習の目標を明確に提示します。子どもたちは仲間と協力して正解を探す過程で、コミュニケーション能力と協調性を高めます。難易度はパズルの枚数、色の使い方、時間制限の有無、ストーリーの難易度で調節できます。家庭ではテーマの話を事前に共有すると、想像力が豊かになり、授業での発表練習にもつながります。
このように、タングラムとハーヴェストは「遊びの形は違うが、育てたい力は補完し合う」関係にあります。家庭でも学校でも、目的に合わせて使い分けることで、子どもの創造性と協調性を同時に伸ばすことができます。
友達とおしゃべりしていて、タングラムの話題になりました。私はこう言いました。『タングラムは7ピースで作る基本の形遊びだけど、その奥には空間認識という頭の筋トレがあるんだよ。図形を分解して組み合わせるとき、どのピースがどこに入るかをイメージする力が自然と鍛えられる。ハーヴェストはそれに対して物語と協力を追加する。みんなで役割を分担してミッションをクリアする楽しさがある』。こう語ると友達も納得して、次の課題をみんなで考え始めました。結局、難易度を上げるほど思考の深さが増します。私は、タングラムを日常のちょっとした時間に取り入れるだけで、空間感覚はもちろん、友達と話す力も自然と高まると感じています。
次の記事: 光飛びと白飛びの違いを徹底解説!露出ミスを減らす写真初心者ガイド »