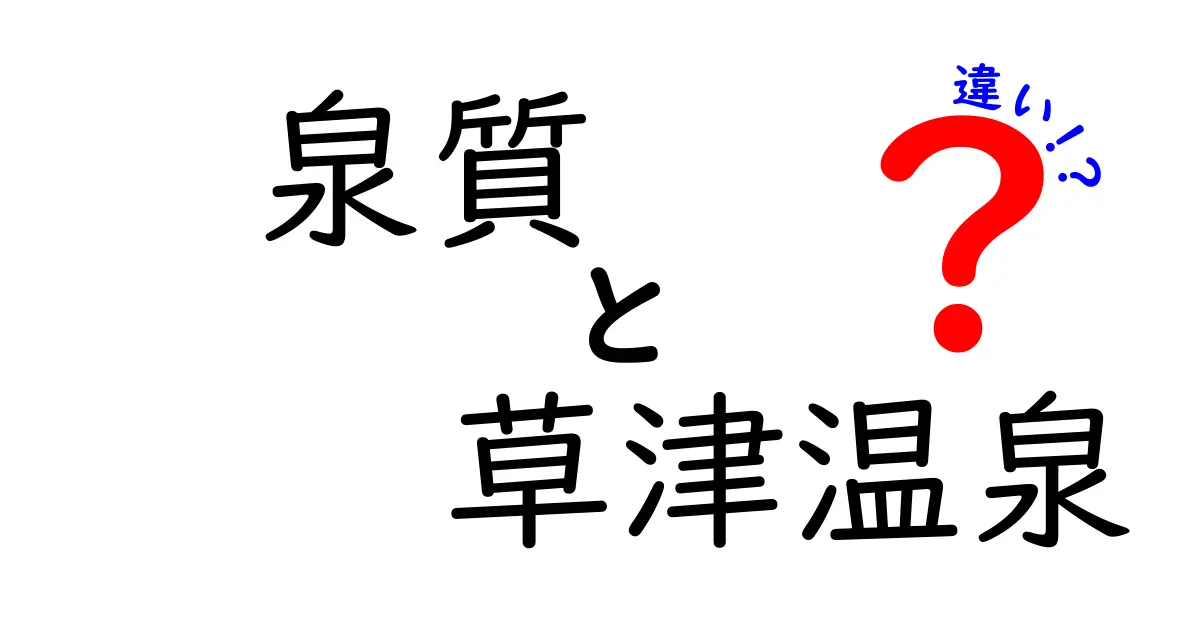

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
泉質の違いがわかると温泉選びが楽になる
温泉の「泉質」とは、温泉水に含まれる成分のことを指し、pH、成分名(硫黄、炭酸、水素、塩化物など)、そして温度も関係してくる。
日常でよく耳にする「硫黄泉」「酸性泉」「中性泉」などの用語は、その温泉の肌ざわりや効能を大きく左右する要素なんだ。草津温泉は特に有名で、酸性・硫黄泉として知られている。冷え性や美肌、関節の痛みなどに効くとされる理由も、泉質の成分が体に働く仕組みに関係している。
この記事では、草津温泉の泉質が他の温泉とどう違うのか、実際の成分と体感の違いを分かりやすく解説する。
草津温泉の泉質の特徴と成分の実際
草津温泉の源泉は主に「酸性硫黄泉」と呼ばれ、pHが低めで強い酸性を持つ。
この性質は、肌の角質を取り除くような「角質除去作用」を持つと言われ、長く温泉に入るほど肌がすべすべになるクチコミが多い。
また、硫黄の香りが強く、白い湯の花が舞うことも草津の湯の特徴のひとつ。硫黄の成分が体の新陳代謝を活性化させる可能性があり、筋肉痛や冷え性の改善を期待する人が多い。
しかし、酸性が強い分、敏感肌の人は入浴時間を短くしたり、温度を低めに設定するなどの対策が必要になる場合がある。ここからは具体的な成分と効能を見ていこう。
主な泉質成分と期待される効能を表で比較
下の表は、草津温泉を代表する泉質成分と、それぞれの効能の目安をまとめたものだ。実際の効能は個人差があることを念頭に置いて読んでほしい。
入浴の前に、季節や体調に合わせた利用が大切だ。
草津温泉の「泉質の違い」を理解すると、旅の計画も変わってくる。
例えば同じ草津エリアでも、宿ごとに温泉のタンクや源泉の温度が微妙に異なり、同じ泉質名でも肌触りが少し違う体験を味わえることがある。
さらに、草津温泉は湯畑周辺で湯を使って熱交換をする伝統的な工程を見学できる場所もあり、観光としての楽しみが増す。
草津温泉の効能と入浴時の注意点を詳しく解説
効能の観点から見ると、酸性硫黄泉は「温熱効果と血行促進」が特に強く感じられることが多い。
体が温まるまでの時間が短く、ポカポカ感が長く続くタイプの人もいれば、敏感肌の人には刺激を強く感じやすいことがある。
そのため初めて草津温泉を訪れる人は、ぬるめの温度から入り、入り方を分割して体を段階的に慣らすのが無理なく続くコツだ。
また、長風呂を避けるために、最初は10分程度、様子を見ながら段階的に時間を伸ばすと良い。
体調が悪い日や空腹時、アルコールを摂取した直後などは避けるべきだ。
友だちと草津の町を歩いていると、ふと『硫黄泉って実際どういうものなの?』と聞かれた。私は『硫黄泉は温泉水に硫黄の成分が多く含まれていて、入ると肌がつるつるになるという人もいるけれど、酸性度が高いので入浴時間を守るのが大事だよ』みたいに答えた。硫黄泉には古くからの効能伝承があり、神経痛や冷え性、血行促進などの話があるけれど、現代の科学では人それぞれ。大切なのは自分の体と相談して、徐々に体を慣らすこと。そんななか、草津の湯は薬の匂いのような香りと白い湯花が特徴で、観光として楽しむのも良い。次回は宿の泉質を事前に比べて、短時間入浴の練習もしてみたいと思う。





















