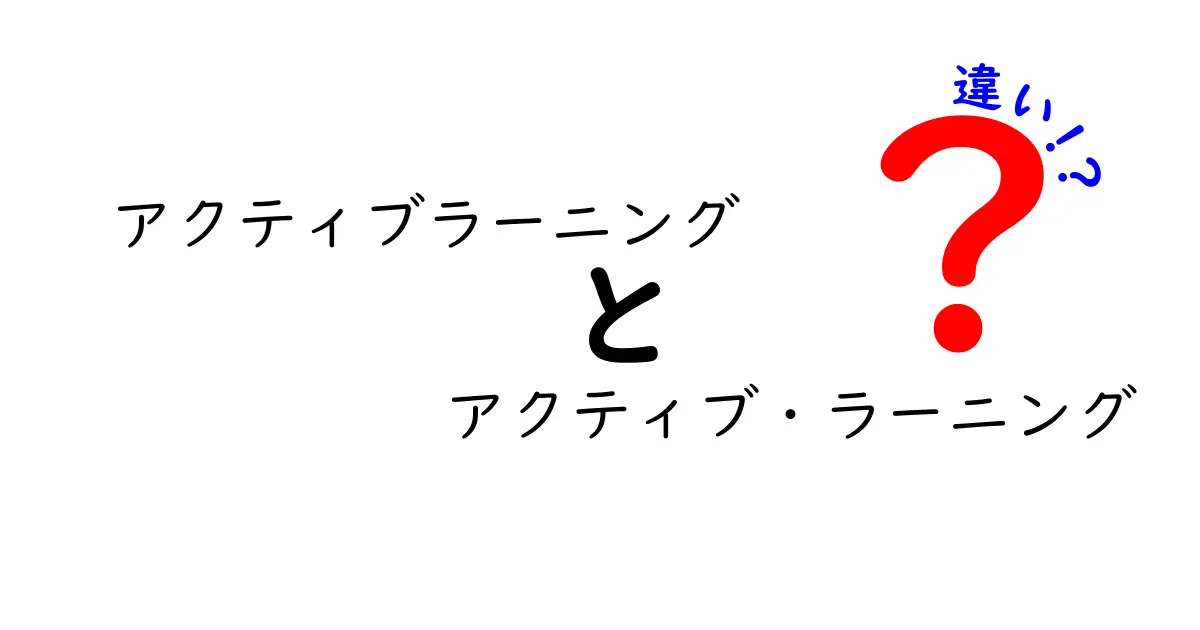

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アクティブラーニングとアクティブ・ラーニングの違いを理解するための前提
現代の授業には、学習者が自分で考え、調べ、発表し、他の人と協力して答えを見つける機会を増やす動きが取り入れられています。この動きを日本語では主に「アクティブラーニング」と呼ぶことが多いです。一方で、教育現場の政策文書や教育実践の現場では「アクティブ・ラーニング」という表現も頻繁に使われます。実は同じようにも使われることが多いのですが、語源・使い方・目的の立て方で微妙な違いがあるのです。ここでは中学生にもわかる言葉で、3つのポイントに絞って違いを整理します。まず大事なのは、どちらも「受け身の学習を減らして、主体的に学ぶこと」を目指している点です。
この考え方は、授業時間をただ埋めるだけでなく、学習者が「自分で答えを探す力」を身につけることを目的としています。
また、授業の設計や評価の仕方を見直すことで、学習の質を高めようとする意図が共通しています。
1) 名前の混乱を招く理由と語源の違い
名前の混乱の原因は、英語の Active Learning の直訳と、日本の教育政策で使われる語が混在することにあります。アクティブラーニングは、授業設計の考え方や方法論を指すことが多く、学習者の自発性・協働・反省を重視します。アクティブ・ラーニングは、教育委員会や文部科学省が推進する枠組み・制度の名前として使われることが多いです。言い換えると、「アクティブラーニング」が実践の考え方、 「アクティブ・ラーニング」が制度や枠組みの言葉、と覚えるのが分かりやすいです。
この区別を理解すると、授業計画や資料の作成、説明のときに混乱を避けやすくなります。語源と使われ方の違いを意識するだけで、説明の精度が上がるのです。
さらに、現場ではしばしば両方の用語が同じ意味で使われることもあります。そうした場合でも、「アクティブラーニング」は“方法論・実践の考え方”としての意味合いが強いのに対し、「アクティブ・ラーニング」は制度・方針の文脈で使われることが多いという点を覚えておくと混乱を減らせます。
教育現場の資料作成時には、目的に応じてどちらの語を選ぶかを明記すると伝わりやすくなります。
2) 実際の授業での使い方の違い
授業での実践の違いは、役割分担、活動の設計、評価の仕方に現れます。アクティブラーニングは学習者が主体的に考え、調べ、発表する過程を重視する設計思想、アクティブ・ラーニングは制度としての運用を意識した枠組みと捉えると整理しやすいです。授業では、グループワーク・ディスカッション・発表・振り返りを組み合わせ、学習者が自分の言葉で説明できるようにします。
また、教師はファシリテーターとして、質問を工夫し、学習者同士の相互作用を促します。結果として、理解の定着だけでなく、学習のプロセスを評価する仕組みが必要になります。評価は、知識の暗記だけでなく、協働や問題解決の過程、発表の質、反省の深さを含めて行うことが重要です。
授業設計の観点から見ると、課題の設定が明確で、学習者が自分で道筋を選べる柔軟性があると効果的です。教師は、適切なサポートを用意しつつ、過度な介入を避け、学習者が自分で道を切り拓く体験を作ります。さらに、授業後の振り返りを定着させるために、次の授業計画へつながる改善点をメモしておくと良いでしょう。
3) 学習効果と評価の観点での違い
評価は、知識の暗記だけでなく、プロセス・協働・発表の質を評価する方向へシフトします。成果物の質はもちろん、課題解決に至る思考過程、試行錯誤の回数、仲間との協働の様子、最終的な結論の妥当性が重視されます。これにより、生徒は自分の学習を「見える化」しやすく、自己評価・他者評価の訓練にもつながります。
学校全体としては、授業計画の作成時点で評価指標を明確にし、授業後には反省会を開くなど、継続的改善のサイクルを回すことが重要です。評価はプロセスと成果の両方を重ねることが肝心です。
まとめと表での比較
ここまでのポイントを整理します。
以下の表は、用語と特徴を並べて見比べるための簡易表です。表を読むだけで違いが拾えるよう、要点を強調しています。
先日、友だちのミキとカフェで雑談していたときのこと。彼女が「アクティブラーニングって何が違うの?」と聞いてきたので、私はこう答えました。「要点は2つ、まず自分で考える時間を増やすこと。次に仲間と意見を出し合い、最終的に結論をみんなで確認していくこと。この流れが根底にあると、学ぶ意味がぐんと深まるんだ」と話しました。話を続けるうちに、自分で解く経験と仲間と協働する経験の両方が学びを豊かにする理由が見えてきました。私たちはこの日、身近な課題を例に取り、どう進めれば自分ごととして関与できるかを考えました。そんな雑談は、授業にもきっと活かせるはずです。





















