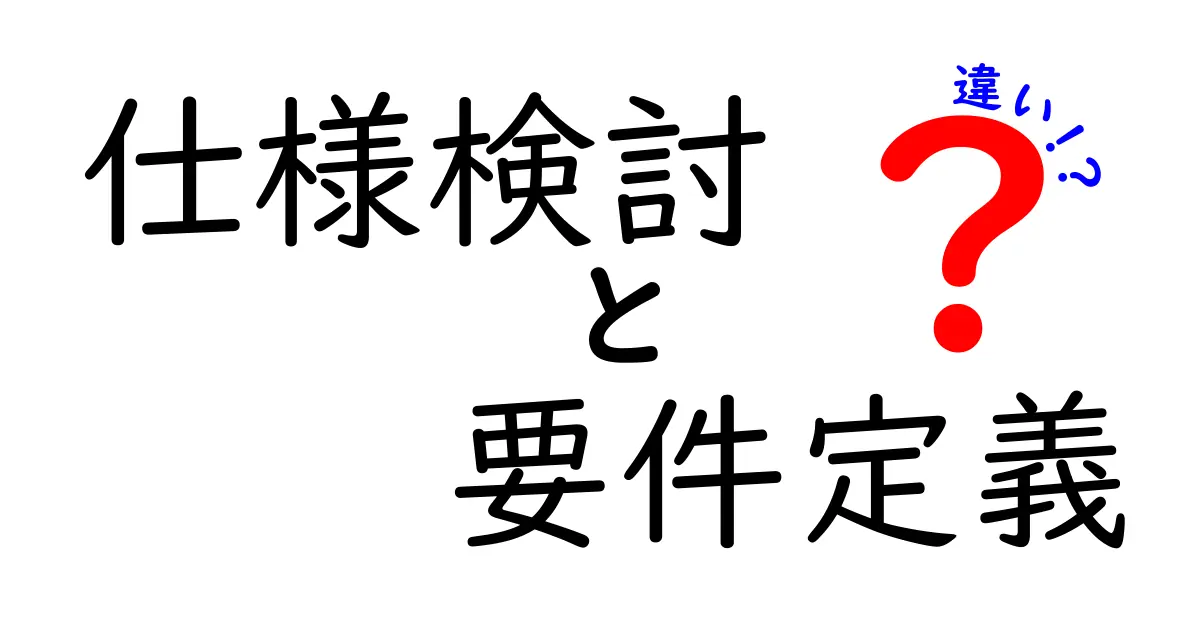

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仕様検討と要件定義の違いを徹底解説:後悔しないプロジェクトの基礎を作ろう
本記事では、ソフトウェア開発や新規プロジェクトでよく混同されがちな「仕様検討」と「要件定義」の違いを、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。まず前提として、どちらも“作ろうとしているものが機能し、使いやすく、目的を達成するための道筋を決める作業”という大枠は同じですが、着目する対象と成果物が異なります。仕様検討は現実的な実現方法や技術的制約を探るプロセスであり、要件定義はユーザーのニーズを具体的な機能として形にする作業です。ここを間違えると、開発の途中で方向性がブレたり、完成時の成果物が価値を持たなくなることがあります。以下の章で、それぞれの意味、進め方、アウトプット、そして実務での違いを、例え話を交えながら詳しく見ていきます。
まずは基本を押さえましょう。-仕様検討-は「どう作るか」を検討する段階で、技術選択、データ構造、インターフェースの仕様化、セキュリティやパフォーマンスの目標設定などを含みます。-要件定義-は「何を作るべきか」を決める段階で、ユーザーの課題、機能の優先順位、非機能要件(信頼性、拡張性、保守性、法令遵守など)を明確化します。これらは連携しながら進み、互いに影響し合います。
次の章から、それぞれをもう少し具体的に見ていきましょう。
仕様検討とは何かを詳しく掘り下げる
仕様検討は、技術的な現実性と実現可能性を検討する作業です。ここでは「どの技術を使うべきか」「どの程度のパフォーマンスを確保するのか」「システム全体のアーキテクチャはどう設計するのか」という問いに答えます。仮に新しいアプリを開発する場合、どのプログラミング言語が最適か、データベースはどの種類か、外部サービスとどう連携するか、UIはどう設計するか、などを技術者・デザイナー・運用担当者が協力して決めていきます。ここでのアウトプットは“実現方法の羅針盤”であり、技術選択の理由、前提条件、リスク、代替案などを明確にします。
仕様検討の成果物の例としては、技術仕様書、アーキテクチャ図、データモデルの設計案、インターフェース仕様(APIの仕様・入力/出力の形式)、性能要件の仮案などがあります。これらは後の要件定義へ橋渡しをします。
要件定義とは何かを詳しく掘り下げる
要件定義は、ユーザーやビジネス上の課題を“何を作るべきか”という形で明確にする作業です。ここでは、誰が使うのか、どんな場面で使われるのか、どの機能が本当に必要かを具体化します。機能だけでなく「いつまでに」「どの程度の精度で」「どの程度の信頼性が必要か」といった非機能要件も同時に定義します。要件定義の成果物には要件リスト、ユーザーのストーリー、受け入れ criteria(受け入れ基準)、優先順位、検証方法などが含まれ、開発チームや顧客と共有されます。ここでの要点は、不確実性を減らし、後工程の混乱を最小化することです。
要件定義は、ビジネス価値を守る“契約のような文書”ともいえ、仕様検討で決めた技術的な前提を踏まえつつ、現実の利用者視点と市場ニーズを結びつける役割を果たします。
仕様検討と要件定義の違いを整理する
両者は似たゴールを持ちながら、焦点とアウトプットが異なります。仕様検討は技術と現実性を評価する作業であり、成果物は「どう作るか」という道筋(技術仕様、アーキテクチャ、データモデルなど)です。一方、要件定義は何を作るべきかを決める作業であり、成果物は「何をつくるか」という機能・非機能の要件リスト、受け入れ基準、利用者ストーリーなどです。プロジェクトを成功させるには、両者の連携が不可欠です。仕様検討で現実的な選択をし、要件定義でその選択がユーザー価値に結びつくことを確認します。
違いをまとめるポイントとして、作業の起点(企画 vs 実装案)、焦点の対象(技術実現性 vs ユーザー価値)、成果物の性格(技術仕様 vs 要件リスト)を意識することが重要です。これらを混同すると、開発が迷路に入り、途中で方向転換が難しくなります。
要件定義って、ただ機能を箇条書きするだけじゃないんだよ。実は、使う人の視点・現場の制約・将来の拡張性を全部一緒に考える雑談の中で形にしていく過程なんだ。たとえば、保守性を高めるために設計を分割する話、レスポンス時間を優先してキャッシュ戦略を追加する話、など。最終的には、開発メンバー・運用担当・顧客が同じゴールを共有できる“共通言語”が要件定義には必要なんだ。
前の記事: « 機能仕様と要件定義の違いを完全解説!どっちを先に作るべき?
次の記事: 使用上の注意と添付文書の違いを徹底解説:誤用を防ぐ実践ガイド »





















