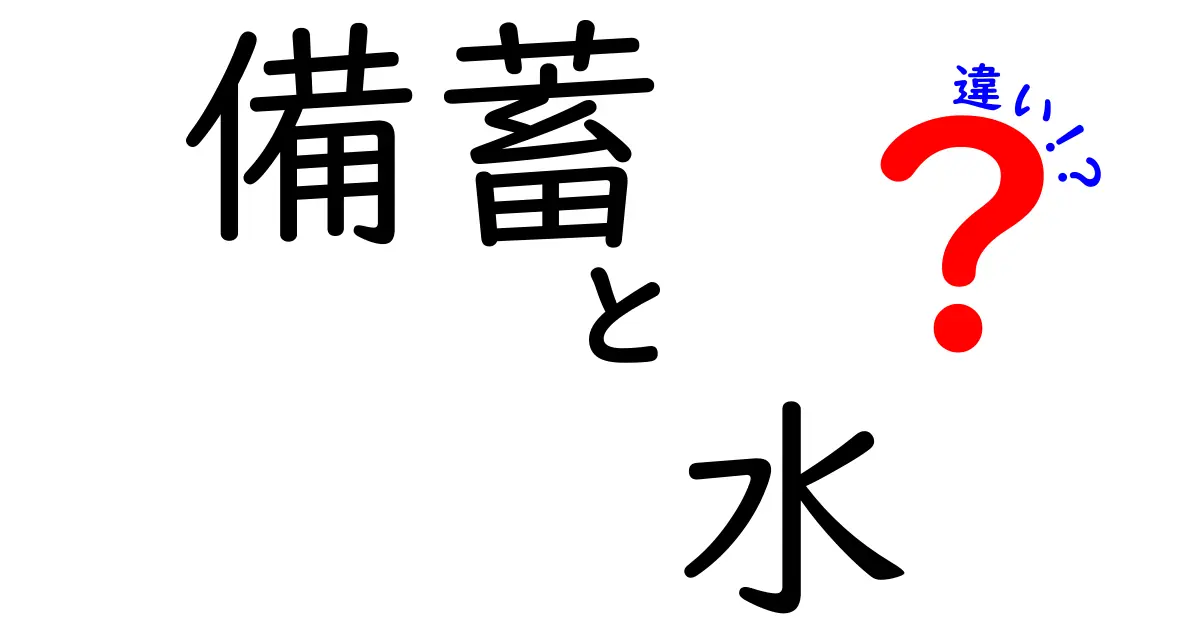

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
備蓄水と日常の水の違いとは?基礎知識を押さえよう
日常生活で使う水と、災害時や緊急時のために用意する備蓄水は、同じ「水」でも目的や管理方法が違います。
日常の水は飲料、料理、掃除などに気軽に使う普通の水です。一方、備蓄水は災害時に生活を支えるために長期間保存できるように工夫された水です。保存期間や容器の種類、置き場所にも注意が必要です。これらを理解すると、いざというときに慌てず安心できる備えになります。
備蓄水は安全に保存できる密閉容器に入れ、賞味期限や品質を守りながら用意します。また、水の量も非常時に必要な目安を知っておくことが大切です。少しの違いですが、この意識の差が生活の安心感につながります。
備蓄水の準備に必要なポイントと保存のコツ
備蓄水を準備するときに気をつけたいのは保存期間と量、容器の選び方です。
一般的に備蓄水は3年程度保存できるものが多いですが、保存場所の温度や光の影響で品質は変わります。だから定期的に入れ替えを行うことが望ましいです。
備蓄の量は1人あたり1日3リットルが目安とされており、最低でも3日分は確保したいところです。これは飲料水だけでなく調理や衛生面も考えた量になります。
容器は密閉できて直射日光を避けられる素材が理想的です。また、防災用の備蓄水は市販の専用ボトルが便利で、品質管理もされています。
水道水をペットボトルに入れて備蓄する場合は、ペットボトルを煮沸消毒し、新しい水を入れて早めに使い切ることがポイントです。
備蓄水と日常水の比較表
このように備蓄水は特別な目的と管理方法があるため、日常に使う水と区別して準備しましょう。
安心して備蓄水を用意しておくことは、いざという時のあなたや家族の命を守ることにつながります。
備蓄水を用意しつつ日常水も大切に扱うことで、日々の生活の中でも水の有難さを感じることができます。
是非、この記事を参考にして水の備えに役立ててください!
備蓄水の管理って案外知られていませんが、実は「新しい水に交換する頻度」が安全のカギなんです。水は時間が経つと品質が落ちやすいので、密閉容器であっても3年くらいを目安に入れ替えるのがおすすめです。これを守るだけで災害時に安心して飲めるんですよ!
身近なところでいうと、ペットボトルの水でも賞味期限を確認しますよね?備蓄水も同じで、定期的なメンテナンスが命を守るんです。こんな簡単なことが備蓄のポイントなんて意外ですよね。ぜひ参考にしてください。
前の記事: « 予備電源と非常用電源の違いを中学生でも簡単に理解しよう!
次の記事: これでスッキリ!指定避難所と避難場所の違いをわかりやすく解説 »





















