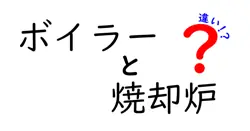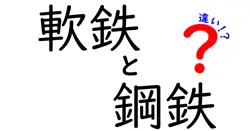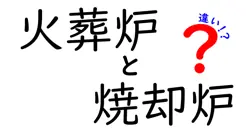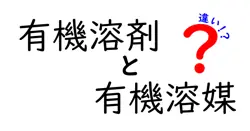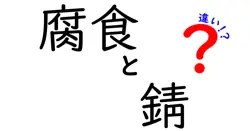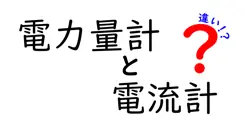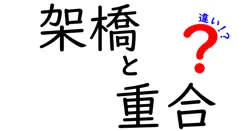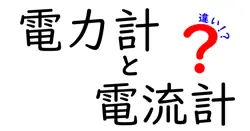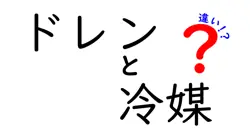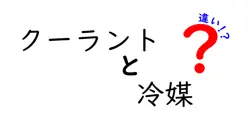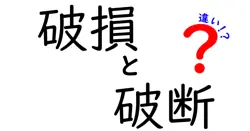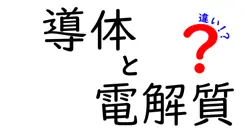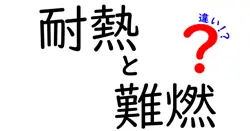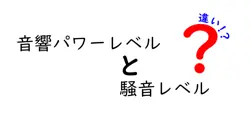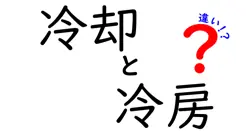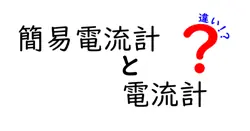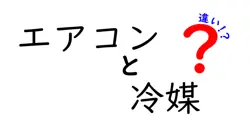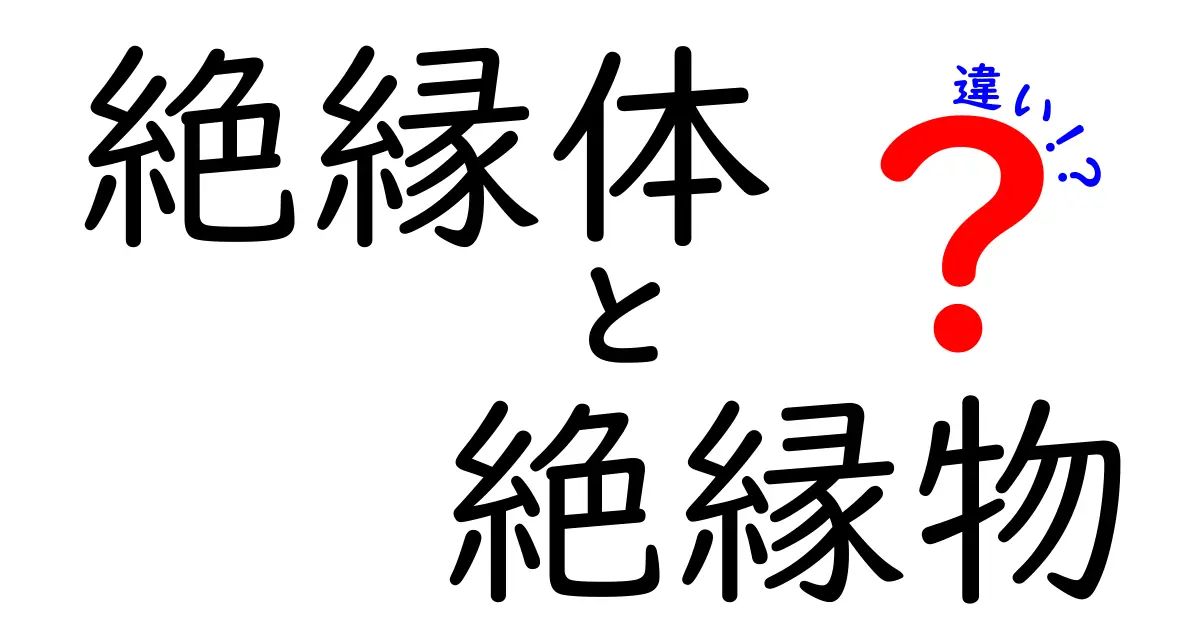
はじめに
皆さんは「絶縁体」と「絶縁物」という言葉を聞いたことがありますか?一見似ているようで、実は少し意味や使い方が違うんです。特に理科や電気の授業でよく出てきますが、わかりにくいですよね。この記事では、絶縁体と絶縁物の違いについて中学生でも理解できるようにやさしく説明していきます!
絶縁体とは?
まずは「絶縁体」についてです。絶縁体とは、電気を通さない物質のことを指します。簡単に言うと、電気を流さないもの、通させないもののことなんです。
たとえば、プラスチックやゴム、ガラスなどは絶縁体です。電線の外側を覆うカバーは大抵プラスチックでできていますね。これは感電を防ぐための絶縁体として使われています。
絶縁体は、電気だけでなく熱や音の「絶縁」としても使われますが、ここでは特に電気の意味で使われることが多いです。
電気回路の安全や機械の正常な動作には欠かせない重要な物質です。
絶縁物とは?
次に「絶縁物」について説明します。絶縁物とは、絶縁の役割を持つ物質や材料のことを広く指します。絶縁体と似ていますが、実際に絶縁の目的で使われているものを強調するときに使われます。
言い換えると、絶縁体の中でも「絶縁するために使われるもの」を絶縁物と呼びます。例えば、電線の被覆として使われているプラスチックの材料や、電気機器の中で部品の間を絶縁するパーツなどが絶縁物です。
絶縁物は、電気事故を防ぐためや機器の性能を上げるために大切な役割を果たしています。
絶縁体と絶縁物の違いをわかりやすく比較!
ここで、絶縁体と絶縁物の違いを表にまとめてみました。
| ポイント | 絶縁体 | 絶縁物 |
|---|---|---|
| 意味 | 電気を通さない物質 (例:プラスチック、ゴム、ガラス) | 絶縁の目的で使われる物質や材料 (例:電線の被覆、機器内の絶縁部品) |
| 使い方 | 主に材料の性質として使われる | 実際に絶縁用途で使われているもの |
| 範囲 | 物質そのものを指す | 絶縁の役割を持ったもの全体を指す |
| 例 | ゴムの板、ガラス板など | 電線の被覆、絶縁テープなど |
このように、絶縁体は物質の性質を表し、絶縁物は絶縁目的で実際に使われるものという違いがあります。
まとめ
今回は「絶縁体」と「絶縁物」の違いについて説明しました。
簡単にまとめると、
絶縁体は電気を通さない物質そのもの。
絶縁物は絶縁の役割で使われる物体や材料。
ということになります。
どちらも電気の安全や機器の性能を守る上でとても大事なもの。日常生活の中でも電線や家電製品でよく触れる言葉なので、しっかり理解しておくと役立ちますよ!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「絶縁物」って聞くと、ちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、実はすごく身近なんです。例えば、家の中のコンセントや電気コードの外側に使われているプラスチックも絶縁物なんですよ。これがなかったら、触るだけで感電してしまう危険が高まりますよね。だから絶縁物は私たちの安全を守るすごく大切な役割をしているんです。ちなみに、絶縁物は電気だけじゃなくて、熱を通しにくいものも含めて考えることもあります。面白いですよね!