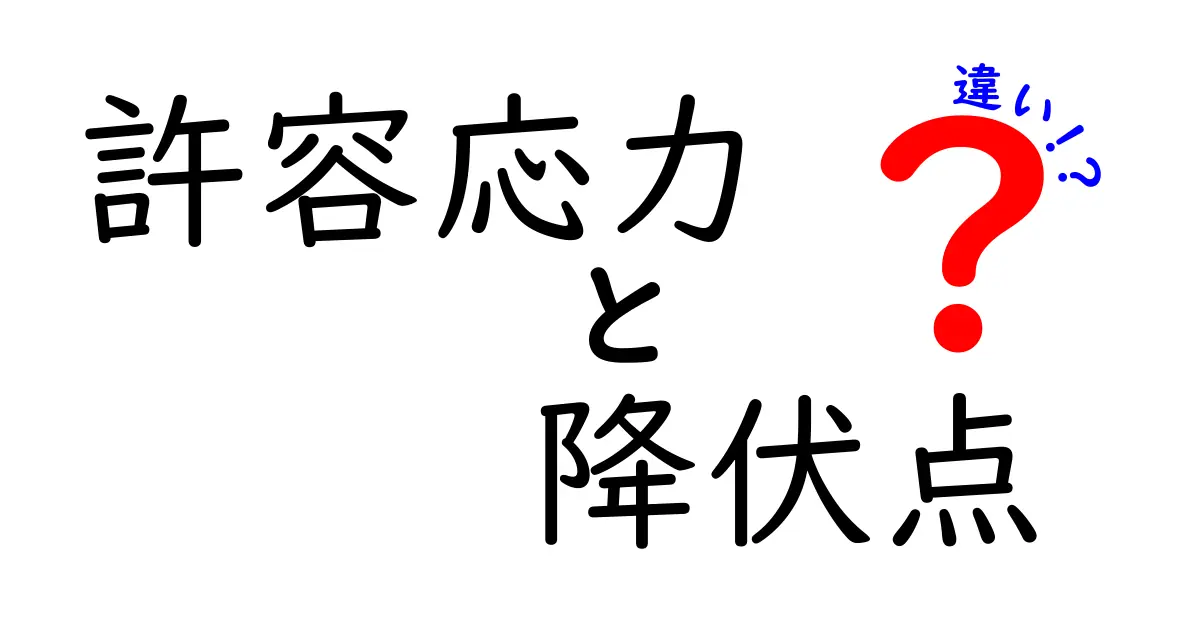

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
許容応力とは何か?
材料や部品を設計するときによく出てくる言葉に「許容応力」があります。これは簡単に言うと、「材料が安全に使える最大の応力」です。
応力とは、物に力を加えたときにその物の中に生じる圧力のようなもので、たとえば引っ張ったり押したりすると材料の中には応力が発生します。
許容応力は、材料が壊れたり変形してしまわないために、使う人が守るべき最大の応力の値です。これは材料自体の強さや安全係数などを考慮して決められており、実際の設計ではこの値を超えないように製品が作られます。
では許容応力はどんな風に決まっているのでしょうか?
それは材料の性質はもちろん、使う環境や目的によって変わるので、設計基準や規格が決めることが多いんです。
例えば、自動車の部品と橋の部材では安全係数が異なり、それに伴い許容応力も変化します。
つまり、許容応力は実際に安全に使うためのルールのようなものと言えます。
許容応力は「安全な限界」なので、これを超えてしまうと部品が曲がったり壊れたりする危険があります。だから設計者は慎重にこの値を設定し、製品が壊れないようにしています。
降伏点とは?材料が変形を始める目安
次に「降伏点」について説明します。材料に力を加えると、最初は少し伸びるだけで元の形に戻りますが、力が強くなると材料が永久に変形してしまいます。
その変形が始まる境目の応力値が「降伏点」です。
もっとわかりやすく言うと、降伏点は「材料がゴムのように元に戻らなくなる最小の力」です。
材料は軽い力であれば自由に戻りますが、降伏点を超えると変形は戻らず、物が曲がったり歪んでしまうのです。
降伏点も材料の種類によって異なり、鋼のような金属材料には必ず降伏点が存在しますが、プラスチックなどの一部の材料でははっきりしないこともあります。
製品設計ではこの降伏点を意識して、材料がその力を超えないように設計します。そうしないと、使っているうちに製品がだんだん変形してしまい、性能が落ちるからです。
許容応力と降伏点の違いをわかりやすく比較
「許容応力」と「降伏点」、似ているようですが、実は役割も意味も違います。以下の表で違いをまとめてみました。
| 用語 | 意味 | 目的 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 許容応力 | 材料や設計上、安全に使える最大の応力の値 | 安全を確保し、設計の基準とする | 実際の使用を考慮し、規格や安全係数を含む |
| 降伏点 | 材料が永久変形を始める応力の境目 | 材料の物理的性質を示す | 材料固有の値で変形開始の目安となる |
このように降伏点は材料の性質そのものの値なのに対し、許容応力は材料の強さと安全のための設計から決まった値なんですね。
また、許容応力は降伏点より必ず低く設定されるのが一般的で、これは万が一の材料の疲労や不均一な力にも対応できるようにするためです。
つまり許容応力は「安全ストッパー」の役割、降伏点は「壊れ始めるボーダーライン」の役割を果たしています。
まとめ:材料の強さを理解するポイント
ここまで、許容応力と降伏点の違いについて説明しました。
・許容応力は安全に使うために設計に取り入れる大事な値
・降伏点は材料そのものの特性を示す物理的な値
この二つの関係を理解することで、安全な製品作りや材料選びに役立ちます。
中学生にも理解しやすい材料の力学の基礎知識として覚えておきましょう。
今後、もっと詳しく材料力学を勉強するときも、まずはここからスタートしてみてくださいね。安全と強さの大切さをしっかり意識できることが、いいものづくりの第一歩です。
「降伏点」という言葉、聞くと難しそうですが、実は材料が元に戻らなくなるギリギリの境目を示しています。たとえばゴムは軽く引っ張っても元に戻りますが、ある限度を超えるとはもう元には戻らないですよね。その限度が降伏点です。材料の性質を表す大事な値なので、建物や乗り物などの安全設計でとても役立っているんですよ。材料が変形しないように設計者は降伏点を超えない力で使うように気をつけています。意外に身近な現象なんですね。
次の記事: TDSと硬度の違いとは?水の質を簡単に理解するためのポイント解説 »





















