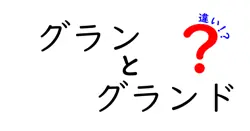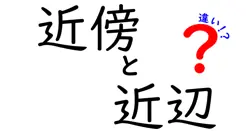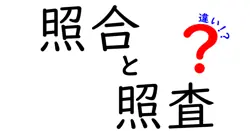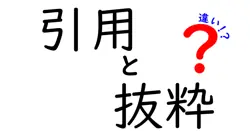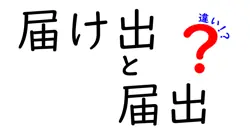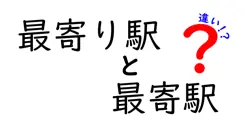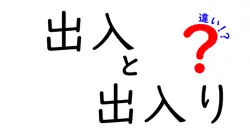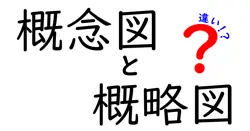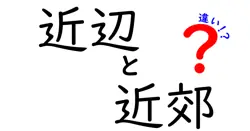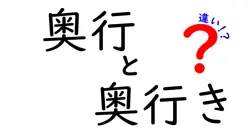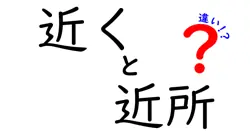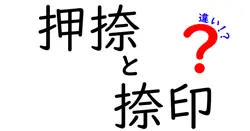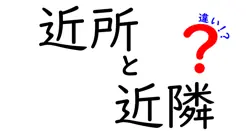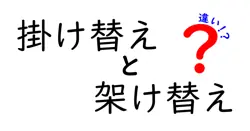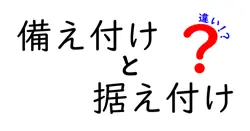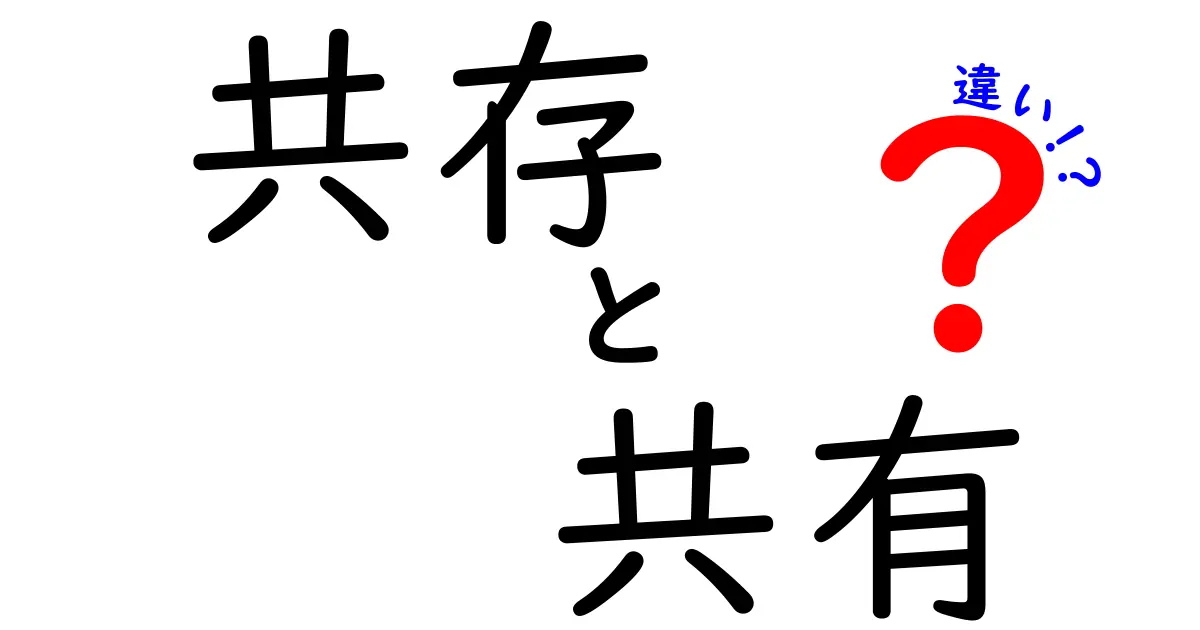
共存と共有の違いを理解しよう
日常生活で「共存」と「共有」という言葉はよく聞きますが、実は意味が少し違っています。共存とは、異なるものが互いに影響し合いながら一緒に存在することを意味します。一方、共有とは同じものを複数の人や物が分け合って使うことを指します。
たとえば、自然界では動物と植物が共存しています。それぞれが異なる役割を持ちつつ、地域や環境を共有しながら生活している状態です。一方、友達とおもちゃを共有する場合は、一つのおもちゃを交代で使うことになります。
このように、共存は「異なるものがともに存在すること」、共有は「同じものを分け合うこと」と覚えるとわかりやすいでしょう。
次に、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
共存の特徴と具体例
共存は異なるものが影響しあいながら一緒に存在することです。これは単に同じ場所にいるだけでなく、お互いに関わりを持ちながら存在が成り立つことが多いです。
たとえば、森の中ではさまざまな生き物が共存しています。鳥は木に巣を作り、虫は葉を食べ、植物は光合成をして酸素を作ります。ここでの共存はお互いの存在が生態系のバランスを守っています。
また、人とペットも共存の例です。人はペットに食事や住む場所を提供し、ペットは癒しや楽しみを与えてくれます。
共存には、互いの違いを認めて調和しながら生きる姿勢が必要です。
共有の特徴と具体例
共有は同じものを複数の人や物が使うことを指します。これは「分け合う」というイメージが強いです。
たとえば、家族みんなでテレビを共有する場合、一つのテレビを順番に使うか、同じ空間で一緒に見ます。デジタル時代では、クラウドサービスを複数人で共有することもあります。ファイルや写真をインターネット上で共有し、誰でもアクセスできる状態になります。
共有は資源や情報などを分かち合い、効率的な利用やコミュニケーションを促進します。ただし、共有したものの管理やマナーも大切です。
例えば、共有の場でのルールを守らなければ、トラブルや使えなくなることもあります。
共存と共有の違いまとめ表
このように、「共存」と「共有」は似ているようで、根本の意味や使われ方が異なります。
日常生活や社会でこれらの言葉を正しく使い分けることで、よりコミュニケーションがスムーズになります。
ぜひ、この違いを覚えて使ってみてください。
「共有」という言葉は、単に物を分け合うだけでなく、デジタル時代にはクラウドサービスの利用でも重要な役割を持ちます。例えば、家族や友達で写真やファイルをネット上で共有すれば、場所を選ばずに情報を見たり編集できるのです。
でも、共有は便利な反面、セキュリティやプライバシーに注意が必要です。誰がアクセスできるのかをしっかり管理しなければ、思わぬトラブルになることもあります。
中学生のみんなも、学校でのグループ活動やオンラインでの資料共有などで、こうした共有の仕組みを使うことが増えていますよね。使い方やルールをしっかり理解して、上手に活用しましょう!