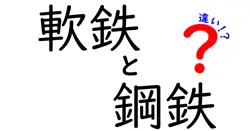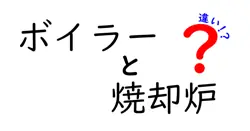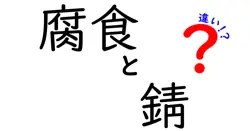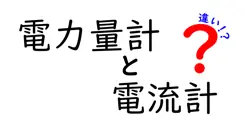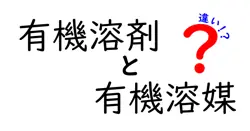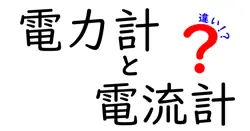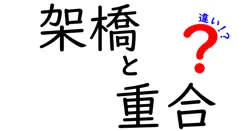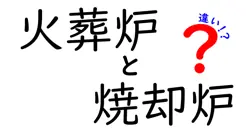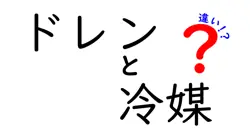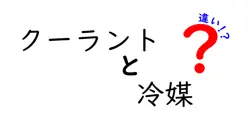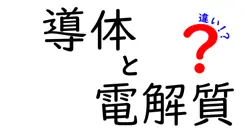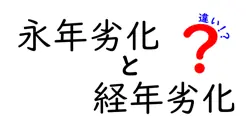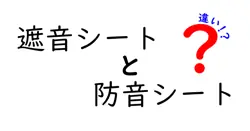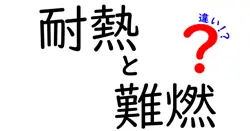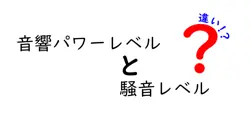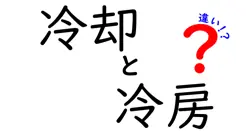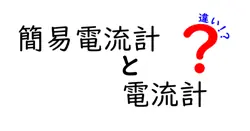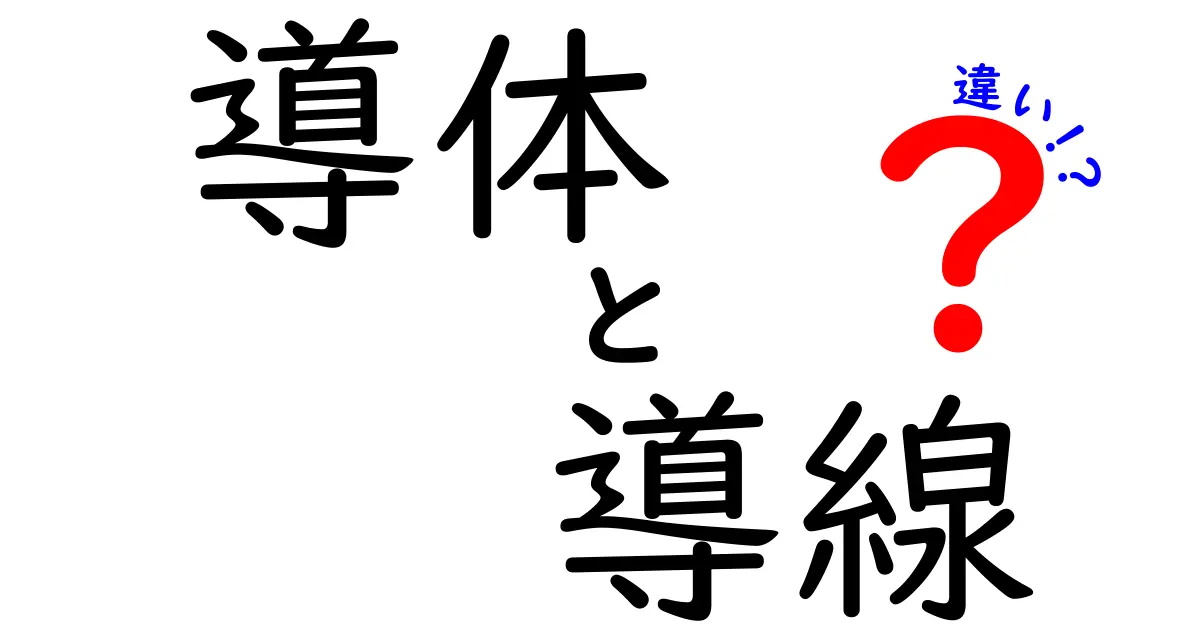
導体と導線って何?その違いを知ろう
電気に関する言葉でよく「導体」と「導線」という言葉を耳にしますよね。見た目は似ているけど、実は意味が違うんです。導体とは、電気を通しやすい物質のことを指します。例えば、銅やアルミニウムなどが代表的な導体です。
一方で導線とは、その導体を使って作られた電線のこと。つまり、電子がスムーズに流れて電気を届けるための細長い線のことをいいます。
導体は「物質の性質」、導線は「その物質から作られたもの」だとイメージすれば分かりやすいでしょう。導体は錬金術でいう魔法の素材、導線はその素材で作った魔法の杖のようなものと考えると親しみやすいですね。
電気の世界を理解する第一歩として、この二つの違いを押さえておきましょう。
導体の特徴と代表的な材料
導体は電気をよく通す性質を持つ物質で、その理由は中にある電子が自由に動けるからです。金属はほとんど導体として使われています。
代表的な導体の材料と特徴は以下の通りです。
| 導体の材料 | 特徴 |
|---|---|
| 銅 | 電気抵抗が小さく、電線に最もよく使われる |
| アルミニウム | 軽くて安価、送電線に多く使われる |
| 銀 | 最も電気を通しやすいが価格が高い |
このように導体は単なる物質ですが、電気の通りやすさが異なり、用途に合わせて選ばれます。
それぞれの特徴を理解することで、なぜ銅やアルミが一般的に使われるかがわかるでしょう。
導線の役割と種類
導線とは、実際に電気を運ぶために導体を細く延ばしたり、加工したものを指します。
電気製品や建物内の配線などで使われ、単に導体を棒状にしているだけでなく、絶縁のためにビニール被覆がされていたりします。
主な導線の種類には以下があります。
- 単線:一本の銅線をそのまま使うタイプ。固定配線に使われることが多い。
- より線:細い銅線を細かく束ねて柔らかくしたもの。家電製品の電源コードなどに使われる。
導線の太さや構造によって耐えられる電気の量や柔軟性が変わるため、用途に応じて使い分けられています。
つまり、導線は導体の特性を活かして実際に電気を送るための形に加工されたものです。
導体と導線の違いを表にまとめてみよう
ここまでの内容をわかりやすく整理するために、導体と導線の違いを表にまとめました。
| 項目 | 導体 | 導線 |
|---|---|---|
| 意味 | 電気を通しやすい物質 | 導体から作られた電気を通す線 |
| 例 | 銅、アルミニウム、銀 | 銅線、より線などの電気配線 |
| 役割 | 電気の流れを妨げない材料 | 電気を安全かつ効率よく運ぶ |
| 形状 | 固体の金属など | 細長い線状に加工されている |
| 使用場所 | 素材として色々な機器に使われる | 配線や電気製品のコード |
この違いを理解すれば、日常生活や理科の授業での電気の話がさらにわかりやすくなりますね。
まとめ:導体と導線の違いをしっかり覚えよう
最後に、今回のポイントを簡単にまとめます。
- 導体は電気を通す素材そのもので、銅やアルミニウムなどがある。
- 導線はその導体を使って細工し、電気を実際に運ぶための線状のもの。
- 導体は物質、導線は形を変えたものと思うとわかりやすい。
これらの違いを理解することで、電気の基本がよくわかり、理科の勉強や将来の技術理解にも役立ちます。
ぜひ覚えておいてくださいね!
導線の中でも「より線」というタイプに注目してみましょう。これは細い銅線を何本も束ねて作られていて、とても柔らかいんです。実は家の電気コードの多くに使われていて、曲げたり持ち運びしても切れにくいというメリットがあります。単線ではなく、この「より線」のおかげで家電製品は安全かつ便利に使えるんですよ。こんな身近な工夫があるなんて、知っていると少し科学が身近に感じられますね。