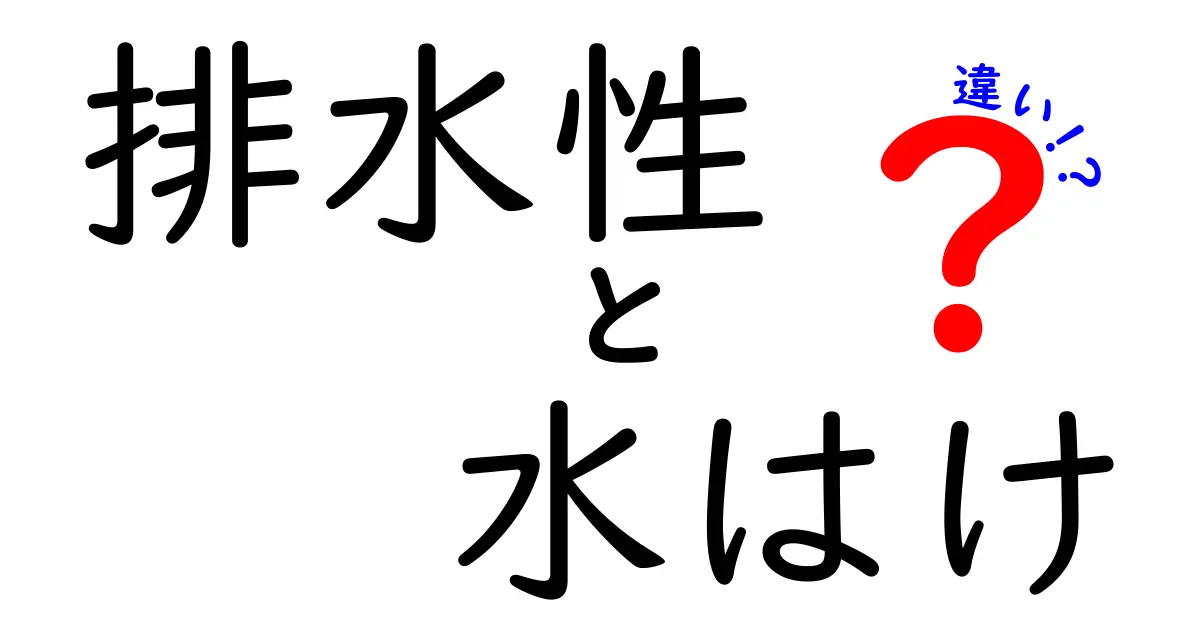

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
排水性と水はけの基本的な意味の違い
日常生活や園芸、住宅の基礎工事などでよく耳にする「排水性」と「水はけ」という言葉。
どちらも水に関する言葉ですが、実は意味が少し違うんです。
まずはそれぞれの言葉の基本的な意味を理解しましょう。
排水性とは、水がどれだけ速く、効率よく排水されるかという性質を指します。
つまり、水がたまらずにスムーズに流れ出ていく能力のことですね。
一方、水はけは主に土壌や場所の特性を表していて、地面が雨水などをどのくらい吸収して流すか、つまり水が溜まらずに自然に外へ逃げるかを言います。
言い換えると、その場所の地面の浸透性や排水能力を示す言葉です。
排水性と水はけの違いを具体例で理解しよう
例えば、庭に水がたまってしまう場所がありますね。
その理由は大きく分けて二つです。
ひとつはその場所の地面自体が水を吸収しにくい、つまり水はけが悪いこと。
もうひとつは周りの排水設備や流れる仕組みがうまく作られていない、つまり排水性が悪いことです。
例えば粘土質の土は水はけが悪く、雨が降ると水が地面に染み込みにくくすぐにたまってしまいます。
しかし排水管や溝がしっかりしていれば、その水を外に出すことができるので排水性は良いと言えます。
逆に砂利を敷いた場所は水はけが良いですが、排水口や溝が無く水の逃げ道がないと水がたまってしまい、排水性は悪い状態になります。
このように水はけは場所の性質、排水性はシステムや設備の機能と考えるとわかりやすいです。
排水性と水はけを理解するメリットと注意点
この二つの違いを知っておくと、家や庭づくりでとても役に立ちます。
たとえば雨が多い地域では水はけの良い土を選んだり、排水設備をしっかり設ける必要があります。
また農業や園芸では、水はけが良すぎると今度は水分不足になる場合もあり、バランスが大切です。
下記の表は排水性と水はけの違いをまとめたものです。項目 排水性 水はけ 意味 水をどれだけ速やかに排水できるかという能力や機能 土壌や場所の水を吸収し流す性質 対象 排水設備や仕組み、地形も含む 主に土壌や地面の特性 例 排水管・溝の有無、排水勾配 土の種類(砂・粘土など) 対策 排水設備の改善や傾斜をつける 土壌改良や土の入れ替え
知識を正しく身につけて、快適で安全な生活空間を作っていきましょう!
「排水性」という言葉、実は排水設備や仕組みの良し悪しを表すことが多いんです。
だから同じ場所でも排水管や溝をしっかり作れば排水性は良くなります。
一方「水はけ」は土や地面の性質なので、簡単には変えられません。
この違いを知っていると、雨の日でも問題なく過ごせる庭づくりのポイントが見えてきますよね。
ちょっとした工夫で水によるトラブルを減らせるのが面白いところです!
次の記事: 草と葉っぱの違いって何?簡単にわかる自然の不思議解説! »





















