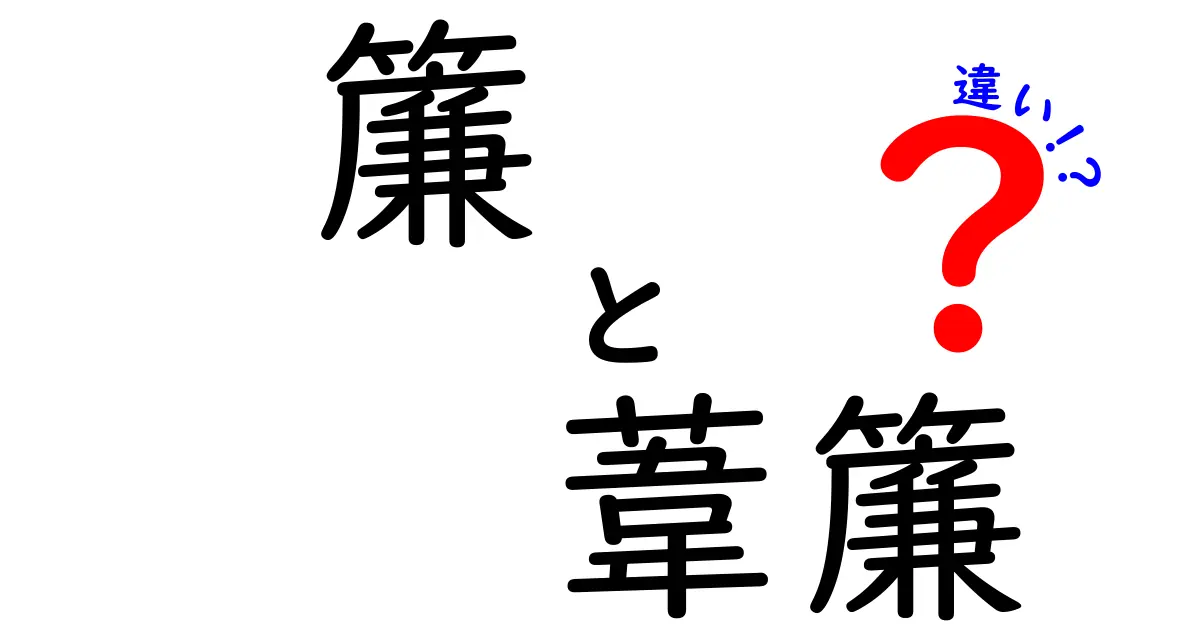

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
簾(すだれ)と葦簾(あしすだれ)の基本的な違いとは?
簾と葦簾は、どちらも夏場に使われる伝統的な日よけ・目隠しのアイテムです。
しかしこの二つは見た目や使われる素材が違い、使い方にも少し違いがあります。
まず「簾(すだれ)」は細い竹や木の小片を糸で編んだもので、軽くて通気性が良く、風にそよぐような柔らかい質感が特徴です。
日本の家屋で窓や軒先に掛けて日差しや視線を和らげるために使われます。
一方で「葦簾(あしすだれ)」は葦(よし)という水辺の植物の茎を使った簾で、
竹よりも少し太くてしっかりした見た目と手触りがあります。
自然な色合いと素朴な感じが日本の夏の風物詩として親しまれています。
葦簾は屋外の目隠しや風通しを保ちつつ日陰をつくるために使われることが多いです。
このように簾と葦簾は素材の違いが最も大きなポイントであり、それが見た目や質感、使い方にも影響しています。
簾(すだれ)と葦簾(あしすだれ)の素材の違いと特徴
簾(すだれ)は一般的に竹や細い木材を使用しています。細かく割った竹を薄くスライスして、糸で編み込むことで軽くてしなやかな素材感が生まれます。
竹は丈夫で水に強いため、屋外でも長持ちしやすいのが魅力です。
また、通気性が良く内部に熱がこもりにくいので、夏の涼しさを保つ効果もあります。
葦簾(あしすだれ)は葦(よし)という植物の茎からつくられます。葦は水辺に生える背の高い草で、茎は竹よりも太く肉厚です。
葦簾は、素材自体が柔らかいため、見た目は素朴で自然味が強く、風に揺れる様子も穏やかで美しいです。
ただし竹に比べると少し耐久性が劣ることがあります。
また葦は軽い反面、湿気に弱いので湿度の高い場所での保管には注意が必要です。
表に素材の特徴をまとめてみましょう。
簾(すだれ)の素材といえば竹が一般的ですが、実は地域や用途によって細かく分かれています。例えば岐阜県の一部では「竹の子すだれ」と呼ばれる若竹を使った柔らかいすだれが有名です。竹の種類や割き方で風合いや耐久性が変わるので、すだれ選びはちょっとした職人技の世界なんですよ。葦簾も同様に、葦の生える場所によって色や硬さが違ってきますから、素材の違いを知るとより楽しめますね。
前の記事: « たてすとよしずの違いを徹底解説!使い方や特徴、見分け方まとめ
次の記事: シェードと遮光ネットの違いとは?効果や使い方、選び方を徹底解説! »





















