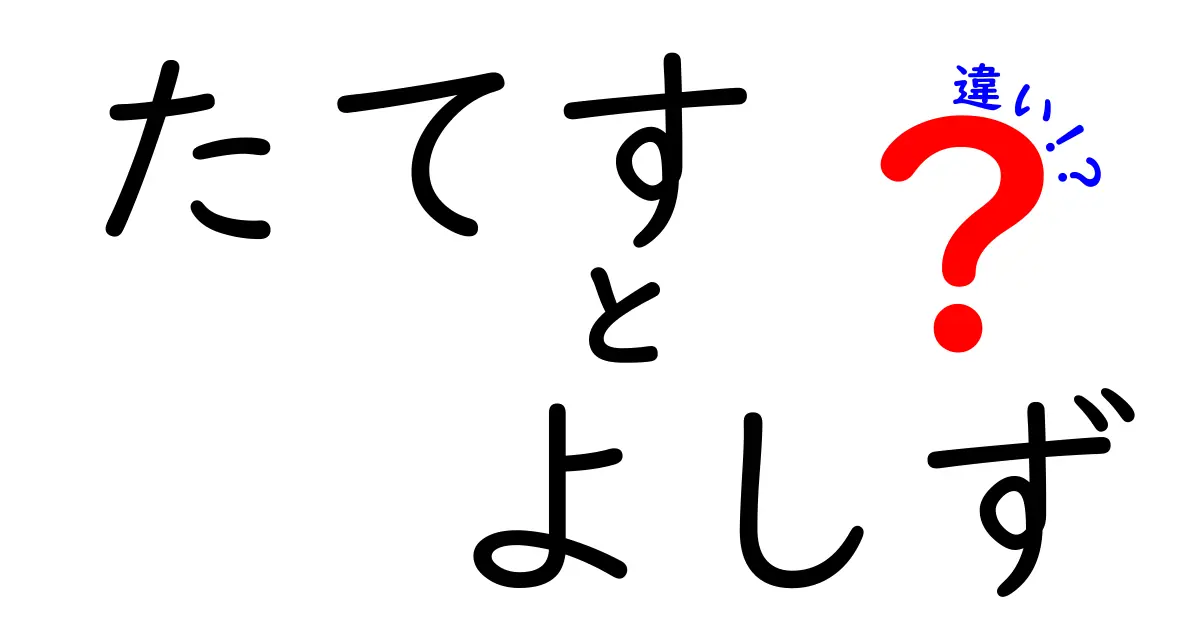

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
たてすとよしずの基本的な違いとは?
暑い夏の室内や屋外の涼しさを守るために使われるアイテムとして、「たてす」と「よしず」があります。どちらも日差しを遮る役割を持っていますが、見た目や素材、使い方に違いがあります。
たてすは細い竹や木の棒を縦方向に並べて紐でつないだもので、よりシンプルな作りが特徴です。主に窓やベランダの内側に設置されることが多く、風通しを保ちながら直射日光を遮ります。一方、よしずはよし(葦)という水辺に生える植物を使って横方向に編んだもので、外側に取り付けて庭や玄関先の日よけとして使われることが一般的です。
見た目にもたてすは細長い棒がまっすぐ並ぶのに対し、よしずは編み込み模様で柔らかい印象があります。材質の違いが使い勝手や耐久性にも影響しています。
たてすとよしずの使い方や設置場所の違い
たてすは主に室内の窓辺やベランダの内側に吊るすことで、室内の温度上昇を抑える役割がメインです。細い竹の棒が縦方向に並べられているため、風は通しやすいですが、暑い日差しをしっかり遮ってくれます。
よしずは逆に屋外の壁や庭先に立てかけたり、フレームにかぶせたりして日差しを遮るために使われます。葦の網目が細かいため、強い日差しや風雨から建物や植物を守りやすいのが特徴です。
設置方法としては、たてすはヒモやフックで吊り下げることが多く、よしずは自立させたり、柱に固定したりします。
これらの違いを知ることで、季節や用途に合わせて効果的に使い分けられます。
たてすとよしずの素材と耐久性の違い
素材面では、たてすの主材料は竹や細い木材の棒が使われ、比較的軽くて折れにくいのが特徴です。シンプルな造りで湿気に強く、扱いやすいため多くの家庭や店舗で見かけます。
一方、よしずは葦(あし)という水辺の植物で編んだものです。葦は自然素材で柔軟性がありますが、湿気や雨に弱いため長期間屋外に放置すると痛みやすいデメリットがあります。そのため、梅雨時期や雨の多い時期は注意が必要です。
耐久性ではたてすの方が丈夫で長持ちする場合が多いですが、使い方や保管方法によって差が出ます。
また、最近はプラスチック製や人工素材を使った類似品もありますが、天然素材ならではの風合いや涼感は魅力的です。
たてすとよしずの見分け方を表で比較!
まとめ:たてすとよしずは目的に合わせて使い分けよう!
たてすとよしずは似ているようで役割や素材、設置場所が異なる伝統的な暑さ対策グッズです。
たてすは室内で風通しを確保しながら日光を防ぎ、よしずは屋外で強い日差しや風雨から守る役割を持っています。
使いたい場所や必要な機能に合わせて選ぶことで、涼しさを最大限に感じられます。
夏の暑さ対策にぜひ、たてすとよしずの違いを理解して上手に活用してみてください。
たてすの材料である竹は、実は日本の気候にとても合った素材です。竹は成長が早く、細くても非常に丈夫なため、昔から建築材や生活道具に使われてきました。たてすの細い竹の棒が縦に並んでいるのは、風通しを良くして室内を涼しくするための工夫なんです。なんだか竹林の風に吹かれているような心地よさを感じるのも納得ですね!
前の記事: « 寒冷紗と遮光ネットの違いとは?初心者にもわかる徹底解説!





















