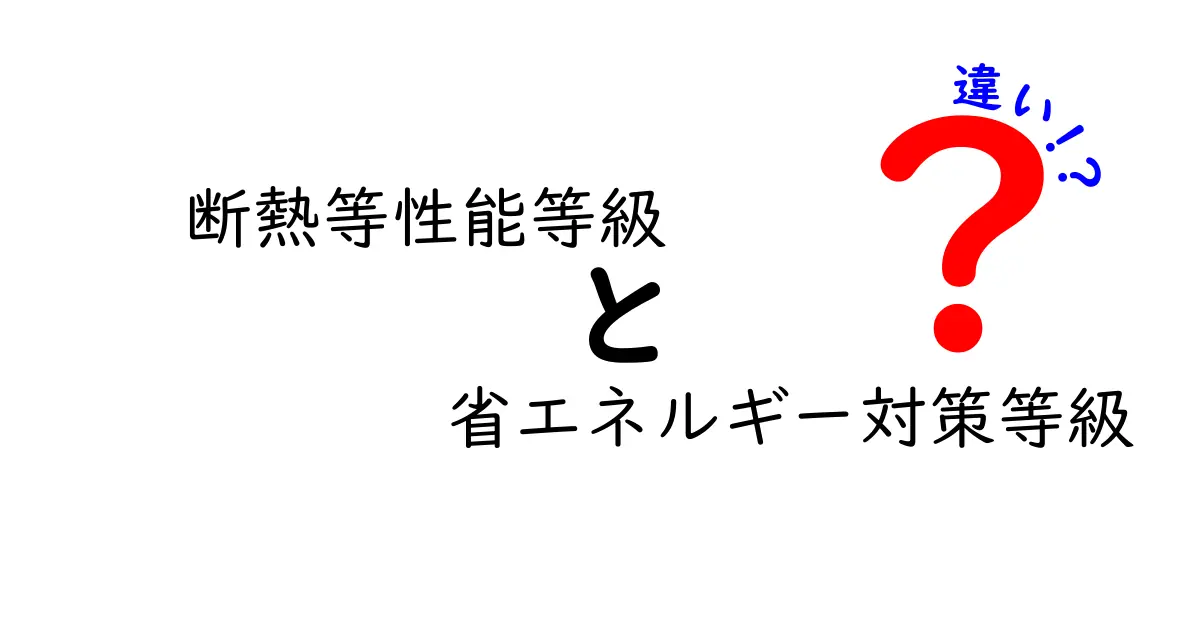

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
断熱等性能等級とは何か?
住宅の快適さを保つうえで大切なポイントの一つが「断熱性能」です。断熱等性能等級は、住宅の壁や屋根、窓などの断熱性能を数値化し、評価したものです。
この等級は日本の住宅性能表示制度の一部として定められており、1級から5級までランクがあり、高い数字ほど断熱性が優れていることを示します。
例えば、5等級の住宅は、非常に高い断熱性能を持ち、夏は暑さを防ぎ、冬は暖かさを保つことができます。これによって冷暖房の効率も上がり、光熱費の節約にもつながります。
この等級は、建材の種類や厚み、設置方法など具体的な断熱仕様を基に評価されます。
断熱性能が高い住宅は快適なだけでなく、省エネルギーの面でも優れているため、環境にやさしい住まいと言えます。
省エネルギー対策等級とは?住宅性能全体からエネルギー効率を評価
一方、省エネルギー対策等級は住宅全体のエネルギー効率を評価する等級です。断熱性能だけでなく、窓の性能や設備の効率、換気方法などを総合して判断されます。
省エネルギー対策等級は1級から5級まであり、高い等級ほどエネルギーを無駄なく使う住宅を示します。
例えば、エアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)の性能は同じでも、断熱性能が低ければ冷暖房効率は悪くなります。省エネルギー対策等級では、このような様々な要素を織り込んで、住まいの省エネ性能全体を評価しています。
また、省エネルギー基準を満たすための指標として政府も推奨しており、補助金や税制優遇の対象になることもあります。
この等級を上げるためには、断熱対策のほか、設備の更新や工夫も必要とされます。
断熱等性能等級と省エネルギー対策等級の違いを比較表で理解しよう
それでは、この二つの等級の違いをわかりやすくまとめた表を見てみましょう。
| 項目 | 断熱等性能等級 | 省エネルギー対策等級 |
|---|---|---|
| 対象 | 主に住宅の断熱性能(壁・屋根・窓) | 断熱性能+設備・換気など住宅全体のエネルギー効率 |
| 評価基準 | 断熱材の種類や厚さ、窓の断熱性能 | 断熱性能に加え、省エネ設備等の総合評価 |
| 等級範囲 | 1級~5級(5級が最高) | 1級~5級(5級が最高) |
| 評価の目的 | 快適な室内環境を作る断熱性能の指標 | 住宅全体のエネルギー消費を抑える性能の指標 |
| 補助金・優遇制度との関係 | 対応することが多い | 対応している場合が多いが設備も重視 |
つまり、断熱等性能等級は断熱の良さを示し、省エネルギー対策等級は住まい全体の省エネ性能を示しているのです。
このため、新築やリフォームの際には両方の等級を確認して、より省エネで快適な家づくりを目指しましょう。
さらに住宅性能表示制度では、これらの等級取得が性能の客観的な証明となり、住宅の資産価値向上にもつながります。
断熱性能と言うと、単に壁や屋根の断熱材の性能をイメージしがちですが、実は窓の断熱性能もとても重要です。窓は住宅の中で一番熱が逃げやすい場所で、性能の良いガラスやフレームを使うことで大きく断熱効果が変わります。だから、断熱等性能等級を上げるためには、壁だけでなく窓もポイントにすると良いんですよ。熱の「出入り口」をしっかり防ぐことが、快適かつ省エネルギーな家づくりの秘訣です。
前の記事: « たわみと曲げの違いをわかりやすく解説!基本と見分け方を学ぼう
次の記事: クイックサンドと液状化の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















