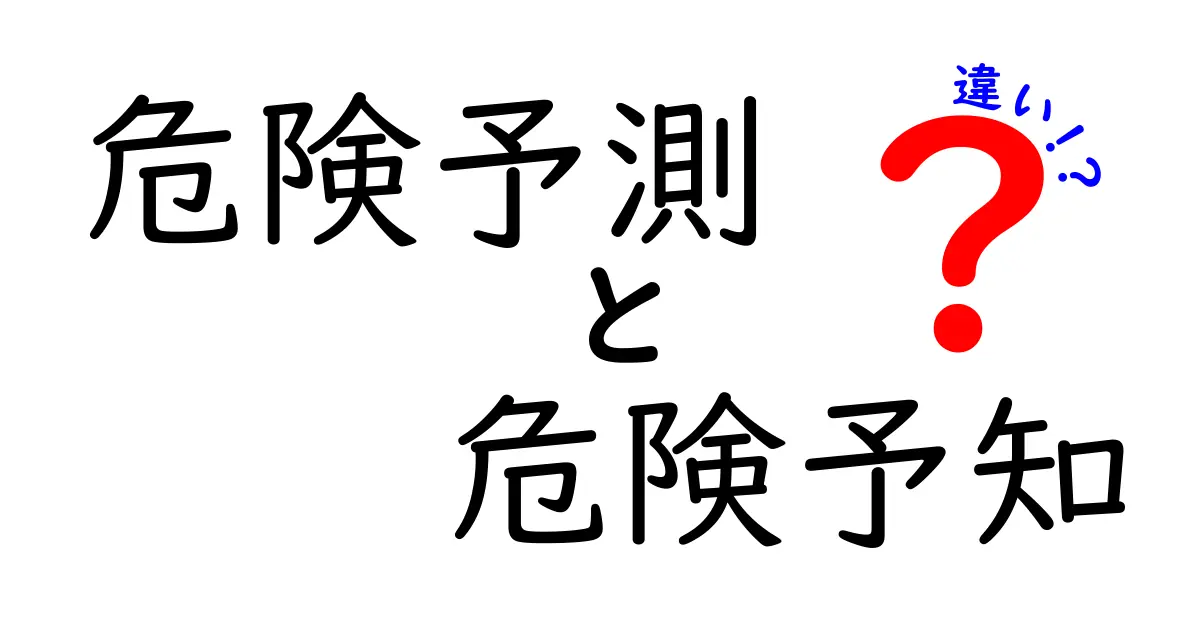

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
危険予測と危険予知とは何か?基本の違いをわかりやすく説明
仕事や日常生活の中で、事故やトラブルを未然に防ぐためには『危険予測』と『危険予知』という言葉をよく聞きます。
でも「この2つ、どう違うの?」と疑問に思う人も多いでしょう。
まず、危険予測とは、将来的に起こるかもしれない危険な出来事を予め予想することです。
例えるなら、「今日は雨だから滑りやすくなっているので足元に気をつけよう」と考えること。
一方で危険予知は、今現在の状況から潜んでいる危険を見つけ出し、事故に繋がりそうな要因を特定することをいいます。
たとえば、「床に水がこぼれているからここは滑りやすい」という具体的な危険を発見するイメージです。
このように、危険予測は未来の可能性を考え、危険予知は現在の現場での危険探しというのが基本的な違いです。
危険予測と危険予知のそれぞれの役割や使い方の違い
危険予測は、仕事や生活の中で起こりそうな危険を想像し、事前に対策を立てることで事故防止を目指します。
例えば工事現場なら「重機が動くから近づかないようにする」「雨の日は足元が滑りやすくなるので注意する」などです。
これに対して、危険予知は目の前の作業や環境を見て、危険要因を見つける活動に使われます。
実際に現場で「配線がむき出しになっている」「資材が不安定に積んである」といった具体的な危険を探し出し、対策を立てます。
両者は安全管理にはどちらも重要で、危険予測が事前準備としての役割、危険予知が当日の現場安全確認としての役割を持っています。
つまり、未来を想定して準備しつつ、今の危険を見逃さないという2段階の安全対策なのです。
危険予測と危険予知の違いを表にまとめて比較
以下の表に、危険予測と危険予知の違いをわかりやすくまとめました。
使い分けを考える参考にしてください。
| ポイント | 危険予測 | 危険予知 |
|---|---|---|
| 意味 | 未来の危険を予想する | 現在の危険を発見する |
| タイミング | 作業前や事前準備段階 | 現場や作業中 |
| 対象 | 可能性のある危険な状況全般 | 具体的な危険要因や場所 |
| 目的 | 事故予防の計画立案 | 即時の安全対策実施 |
| 例 | 雨で滑るかもしれないから注意する | 床に水がこぼれているので滑る |
まとめ:危険予測と危険予知を両方使いこなして安全を守ろう
危険な状況を回避するためには、危険予測と危険予知両方の考え方がとても大切です。
まずは未来に起こるかもしれないリスクを考えて備えを行い、その上で現場の状況をしっかりと観察し、具体的な危険要因を見つけ出します。
この両方をうまく使いこなすことで、事故を未然に防ぎ安全な環境をつくることが可能になります。
仕事やプライベートで安全意識を高めたい人は、ぜひこの2つの違いを理解して「危険予測」と「危険予知」を日常の安全対策に役立ててください。
安全はみんなの努力で守られている、と言えますね。
仕事の現場では『危険予知』の取り組みで、毎朝現場のスタッフが集まってどんな危険が潜んでいるか話し合います。これを『KYT』と呼び、頭文字は「危険予知トレーニング」。ただ危険を知るだけでなく、みんなの意見を共有することが事故防止にとても役立っています。意外と毎日違う危険があるので、みんなで話すことが大切なんです。





















