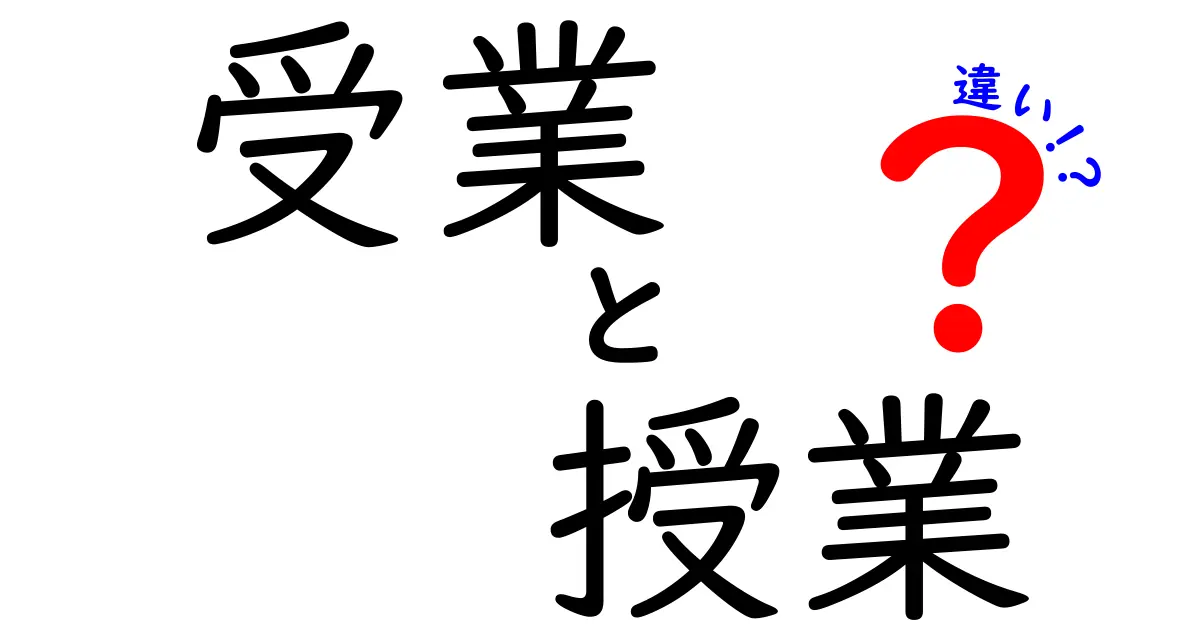

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
「受業」と「授業」の基本的な違いとは?
まずは「受業」と「授業」という言葉の基本的な意味から解説します。
授業(じゅぎょう)は、学校や塾などで先生が生徒に教える活動や時間のことを指します。教科書を使ったり、説明や質問が行われたりする教育の時間全般を意味します。
一方で受業(じゅぎょう)は実は一般的な言葉としてはほとんど使われていません。辞書でもほとんど見かけず、漢字の意味だけから推測すると「受ける業(わざ)」つまり「何かの行いを受ける」という意味合いになりますが、教育現場では使われません。
つまり授業は教える側と学ぶ側が関わる教育の一場面を表し、「受業」は誤用か極めて限られた文脈でしか使われない言葉なのです。
この違いは非常に重要で、正しい言葉としては「授業」を使うことが圧倒的に一般的です。
なぜ「受業」はほとんど使われない?漢字の意味と歴史的背景
「受業」という言葉が一般的に使われない理由を少し掘り下げます。
「受(うける)」は「もらう」「引き受ける」などの意味があります。
「業(わざ・ごう)」は「行い」「仕事」「業績」などを意味します。
しかし「受業」という言葉は日本語の語彙として定着していません。これは漢字を組み合わせただけの造語に近いからです。教育の現場では「授業」が定着しており、教師が「授ける(さずける)」という意味の「授」を使っているため「授業」という言葉になっています。
江戸時代の寺子屋などから続く教育文化の中で「授業」は主に師匠が弟子に教えを授ける場を示していました。
このような歴史的な背景から「授業」は正しい言葉で、「受業」に意味や用法の明確な裏付けはありません。
もし「受業」を見る機会があれば、それは誤字か変わった用法の可能性が高いと覚えておくとよいでしょう。
授業の役割と受ける側の姿勢について考えよう
「授業」は単なる時間や機会だけでなく、先生が知識や技術を伝え、生徒がそれを受け止める双方向の活動です。
ここで重要なのは「授ける」側と「受ける」側の関係です。
授業では生徒側は積極的に学ぼうとする姿勢が求められます。
この意味で「受ける」というのは単に座って聞くだけでなく、理解しようと努め、質問したり復習したりする能動的な行動を指します。
したがって、授業を「受ける」と言うことは自然な表現ですが、これを名詞化して「受業」とすることは正しくありません。
言葉の使い方を間違えるとコミュニケーションに支障が出ることもあるので、「授業」を正しく理解し、積極的に参加することが望ましいのです。
「受業」と「授業」の違いが一目でわかる表
| 言葉 | 読み方 | 意味 | 使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 授業 | じゅぎょう | 先生が生徒に教える活動や時間 | 学校、塾、教育全般 |
| 受業 | じゅぎょう | (一般的には使われない。漢字の意味から考えると「受ける業」) | ほぼ見られない。誤字や特殊な文脈 |
このように「授業」と「受業」は意味や使い方に大きな違いがあります。
日常生活や勉強の場面では必ず「授業」を使うことが基本です。
ぜひ正しい言葉を使い分けて、より良いコミュニケーションを心がけてください。
「授業」という言葉はよく使われますが、その中で「授ける」という漢字が使われているのは意外と気づかれにくいポイントです。実は「授業」の「授」は、先生が知識や技術を「授ける」行為から来ています。つまり授業とは、単に情報を提供するだけでなく、先生が生徒に何かを正式に与える、特別な価値ある時間といえるんです。こんな風に漢字の意味を深堀りしてみると、言葉って面白いですね!
前の記事: « 学級と特別支援学校の違いとは?子どもに合った学び方を理解しよう
次の記事: 処方箋薬と市販薬の違いとは?安全に使い分けるための完全ガイド »





















