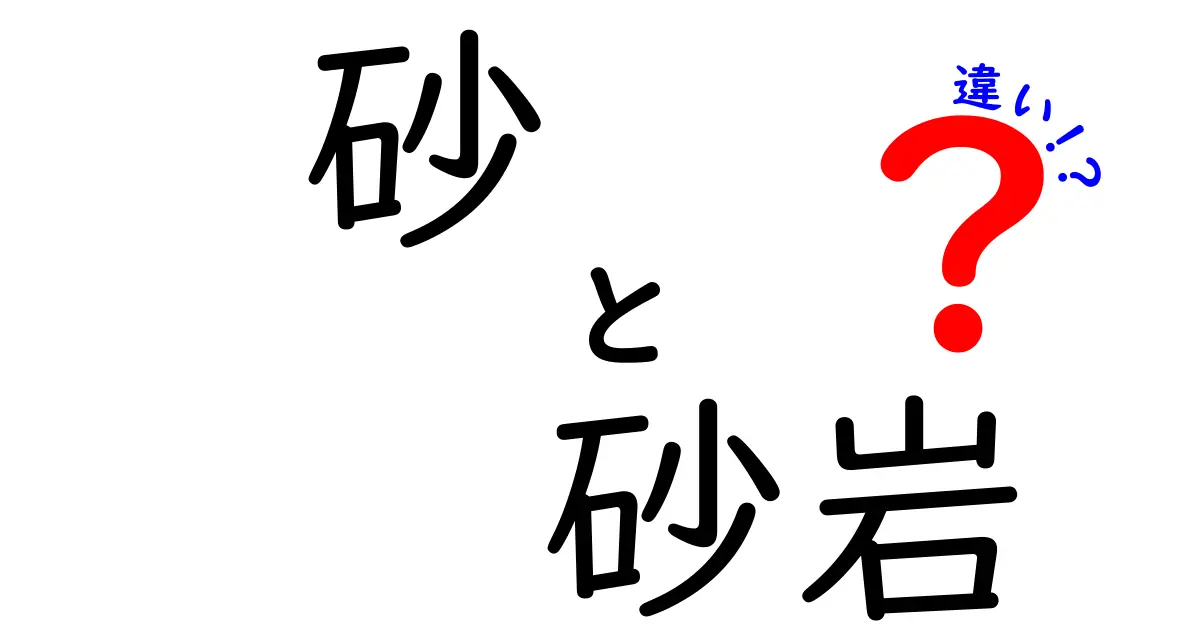

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
砂と砂岩は似ているけど何が違うの?
みなさんは、「砂」と「砂岩」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも自然の中でよく見かけるものですが、実は意味も性質も全然違います。
簡単に言うと、砂は小さな粒の集まりで、砂岩はその砂の粒が長い時間をかけて固まった岩石です。
ここでは、砂と砂岩の違いを中学生にもわかりやすく、詳しく説明します。
まずはそれぞれの特徴から見てみましょう。
砂とは?
砂はごく小さな石や鉱物の粒で、主に水や風で運ばれてできたものです。
例えば海の砂浜や川の川底にあるザラザラした粒が砂です。砂は石のかけらで、ひとつひとつはバラバラで固まっていません。
砂の粒の大きさは、0.06mmから2mmまでの間とされています。それより小さいものはシルト、さらに小さいものは粘土と言います。
砂は水はけが良くて、植物を育てる土の中に入っていることも多いです。しかし単独では固まっていないので、触るとザラザラと手に残ります。
砂の主な成分は石英(せきえい)という鉱物で、そのため色は透明に近かったり白っぽかったりします。
砂岩とは?
砂岩は砂の粒が長い年月をかけて圧力やセメントのような物質によって固まったものです。つまり、砂が一体化して硬い石になった状態です。
砂岩は岩石の一種で、建築材料や石材として用いられることもあります。自然の力で砂同士が接着剤の役割をする鉱物でくっつき、しっかりとした岩を作ります。
砂岩の見た目はザラザラしていることもありますが、触ると固くて崩れません。色は砂の種類や中に含まれる成分によって、赤茶色や灰色、黄色がかった色など様々です。
砂岩の質感や強さは、砂粒の大きさや接着している物質の種類によって変わります。
砂と砂岩の違いを表でまとめてみよう!
粒の大きさは0.06~2mm
固く一体化している
まとめ – なぜ違いを知ることが大切?
砂と砂岩は、砂は単なる粒子の集まりで
砂岩はその砂が固まってできた岩であることから
その性質や使い道も違います。
身の回りの自然や地理、建築材料を学ぶときに
この違いを理解しておくことで、もっと自然を身近に感じられるでしょう。
また、砂岩がどうやってできるのかを考えることで、地球の歴史や自然の働きにも興味がわいてきます。
自然科学の基本を楽しく学びたい方にぜひ参考にしてほしい内容です!
砂の粒はとても小さいですが、実はその大きさによって名前が変わるって知っていましたか?
砂は0.06mmから2mmまでの粒のことで、それより小さい粒は「シルト」、さらに小さな粒は「粘土」と呼ばれます。
この分類は地質学でとても大切で、土壌の性質や水はけなどにも関係しています。
家の庭や公園の砂を見ると、細かい粒の違いを想像してみると面白いですよね!





















