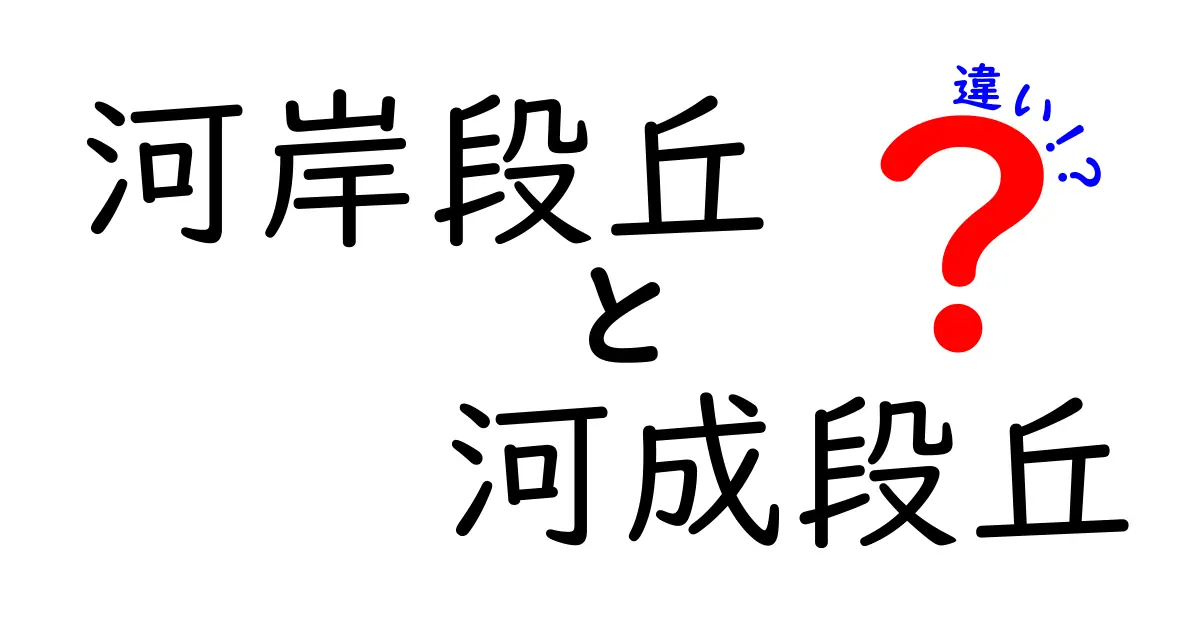

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
河岸段丘と河成段丘の違いを理解しよう
みなさんは「河岸段丘(かがんだんきゅう)」と「河成段丘(かせいだんきゅう)」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも地形の名前ですが、実は意味やでき方が少し違うんです。
今回は地理の勉強として、河岸段丘と河成段丘の違いについてわかりやすく解説します。中学生でも理解できるように、簡単な言葉で説明していきますね。地形に興味がある人はぜひ読んでみてください。
河岸段丘(かがんだんきゅう)とは?
河岸段丘は、川のわきにある階段状の段が幾つも重なっている地形のことを言います。川が削った地面が少しずつ下がったり、川の位置が変わったことでできる場所なんです。
具体的には古い川の土手(河岸)が何段も積み重なったように見えるのが特徴です。河岸段丘はたとえば日本の有名な川の周辺にも多く見られます。川の流れが変わったり、水位が下がったりしたことで、以前の川の跡が段になって残っているわけですね。
河成段丘(かせいだんきゅう)とは?
河成段丘川の堆積物(たいせきぶつ)がたまってできた地形のことなんです。
川が流れるたびに砂や土が川の中や川岸に積もり、それが時間をかけて階段のようになった地形です。
すなわち河成段丘は、川による「土砂の堆積」が作り出した段丘ということになります。これは川が運んだ土や岩が川の流れの変化などによって積もってできるため、地面が階段状に見えるのが特徴です。
河岸段丘と河成段丘の違いを表で比較
浸食作用の強い場所
まとめ ~なぜ違いを知ることが大切?~
河岸段丘と河成段丘は、どちらも川と関係がありますが、でき方や成分が違うため、地形としての意味や役割も少し異なります。
地理や自然の勉強だけでなく、例えば川の近くでの土地利用や防災対策を考える時にも、この違いを知っていると役立ちます。
ぜひ今回の内容を参考に、地図や実際の川の近くを見ながら違いを考えてみてくださいね。
それぞれの段丘を理解すれば、自然の力や時間の流れを感じられて、地球って面白いなと感じられるはずです!
「河成段丘」という言葉、初めて聞いた人も多いかもしれません。実はこれは川が運んだ砂や土が長い時間をかけて積もってできた段丘のことなんですが、驚くのはその”積もる”仕組みです。
川の流れが変わると急に土砂が堆積しやすくなる場所ができ、そのたまった砂や土が何層にもなって階段状の地形になります。
これを知らないと、ただの土手かと思ってしまいそうですが、地形の成り立ちを掘り下げると川の歴史や気候の変化まで見えてくるんですよ。自然の力ってすごいですね!
次の記事: 砂礫と礫の違いとは?見た目や成り立ちからわかりやすく解説! »





















