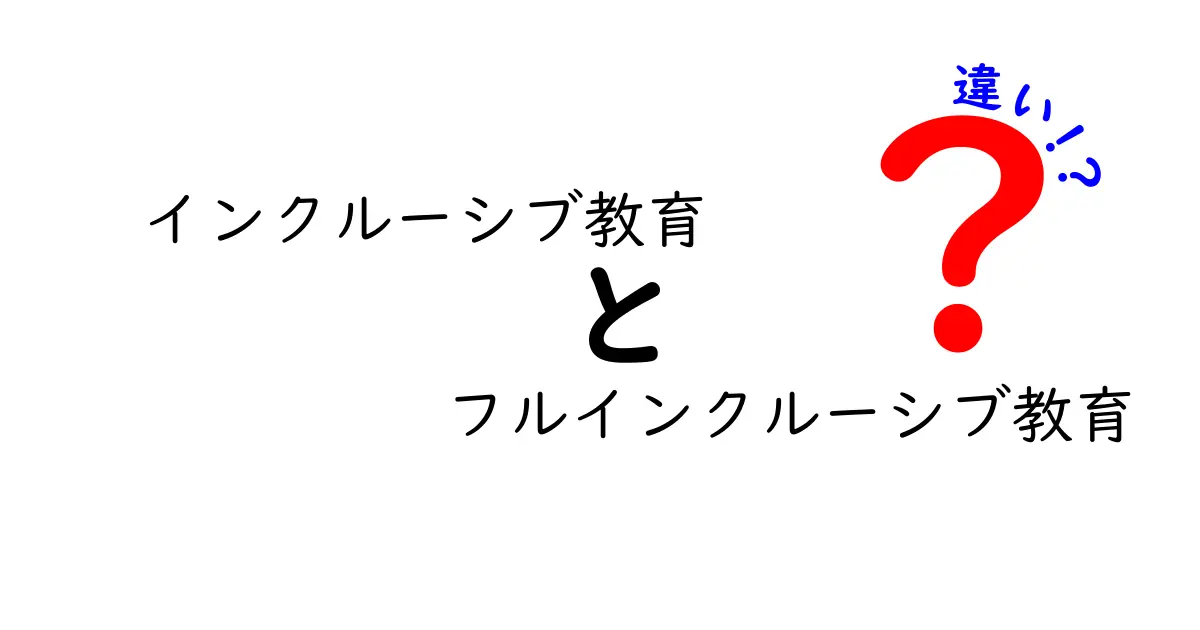

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インクルーシブ教育とは何か?
インクルーシブ教育とは、障がいのある子どももない子どもも一緒に学ぶ教育の方法です。この考え方は、みんなが同じ学校で勉強し、お互いに理解し合いながら成長することを目指しています。
特徴的なのは、障がいがあっても別の特別な場所に行かず、できるだけ通常のクラスで学ぶことを推奨する点です。そのため、学校や先生は個々の子どものニーズに合わせて支援を行います。
インクルーシブ教育は、単に同じ場所で学ぶだけでなく、みんなが尊重される環境を作り出すことを大切にしています。子どもたちがお互いの違いを認め、協力しあうことが目標です。
例えば、視覚障がいのある子どもが普通教室で音声教材を使ったり、学習支援員がサポートしたりするなど、支援の形は様々です。
こうした取り組みは、子どもたちの自信や社会性を育む助けとなります。
しかし、学校や教師の準備が必要であり、場合によっては特別支援教育とのバランスを考える必要もあります。
フルインクルーシブ教育とは?
フルインクルーシブ教育は、インクルーシブ教育をさらに進めた形態です。
文字通り「フル(完全な)」インクルージョンを目指し、あらゆる子どもが一切の隔たりなく同じ環境で学びます。
つまり、すべての学習や活動が一緒に行われ、どの子どもも区別されることなく参加できることが理想とされています。これは障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが最大限に交流し、学び合う場を提供することを意味します。
たとえば、課外活動やクラブ、遠足なども一緒に計画され、別々に分けられることがありません。教育カリキュラムも柔軟に変更し、みんなが参加しやすいように工夫されます。
さらに、フルインクルーシブ教育では、子ども一人ひとりの特性が尊重され、多様な学びのスタイルやニーズを全面的に受け入れる環境が整えられます。そのため、教師やスタッフ全体の力量や、地域や社会の協力が欠かせません。
フルインクルーシブ教育はまだ実践例が少なく、理想の形として議論されていますが、その社会的意義は大きいと期待されています。
インクルーシブ教育とフルインクルーシブ教育の違いまとめ
| ポイント | インクルーシブ教育 | フルインクルーシブ教育 |
|---|---|---|
| 目的 | 障がいのある子どもも共に学ぶこと | すべての子どもが完全に区別なく共に学ぶこと |
| 実施方法 | 主に通常学級での学習支援を行う | 学習以外の活動も全部一緒に行う |
| 支援の形態 | 個別の支援や特別な配慮がある | 全員が溶け込める環境づくりが徹底される |
| 現状の普及度 | 広く普及しつつある | 理想形であり実践はまだ少ない |
このように両者は似ていますが、フルインクルーシブ教育はより一歩踏み込んだ「完全な共生」を目標にしています。
それぞれの学校や教育現場で採用される形態は様々ですが、どちらも子どもたちの多様性を認め合う点では共通しています。
社会全体が多様な個性を大切にしながら成長するためには、こうした教育の広がりが不可欠です。
今後の教育環境改善の議論や実践にぜひ注目してみてください。
「フルインクルーシブ教育」という言葉を聞くと、なんだか完璧なインクルージョンのように感じませんか?実は、フルインクルーシブ教育はインクルーシブ教育の中でも「完全な共生」を目指す教育方法です。
通常のインクルーシブ教育は授業が一緒でも、放課後活動などは分けて行うこともありますが、フルインクルーシブ教育はすべての学びや遊びを一緒に体験します。
これは実現が難しい面も多いですが、みんなが違いを超えて助け合う社会のモデルとも言えますね。将来的にはもっと広まっていくかもしれません。
次の記事: PBLと探究学習の違いとは?中学生にもわかるポイント解説! »





















