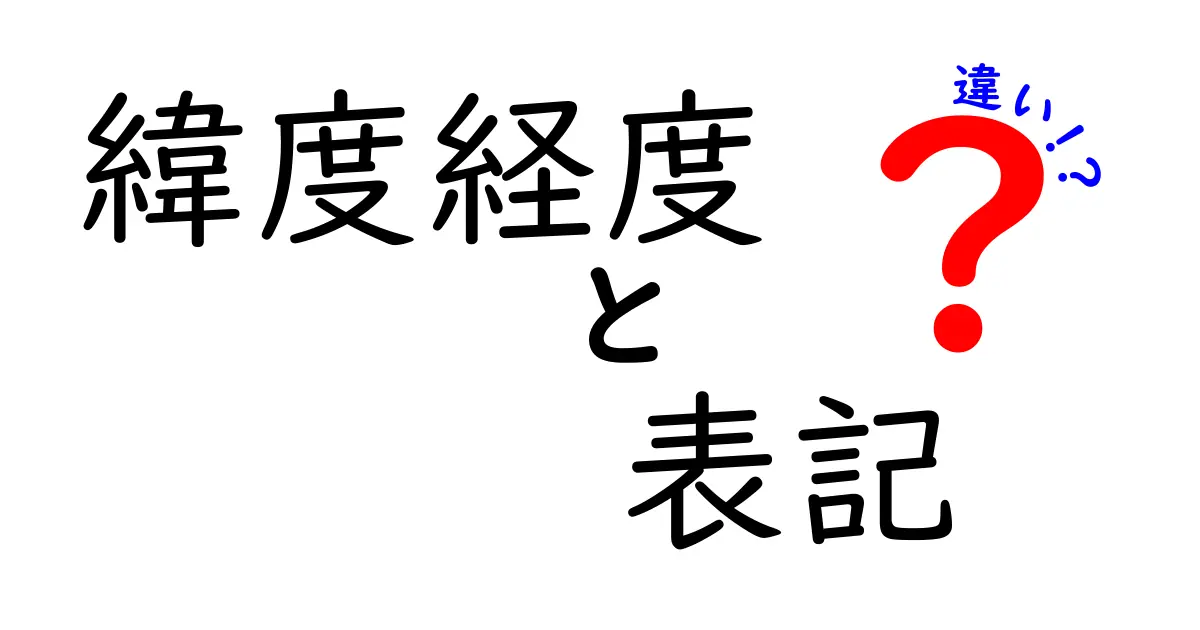

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
緯度経度の表記の違いを理解する基本
緯度と経度は地球の位置を表す座標系の核心です。緯度は赤道を基準に北半球を正、南半球を負で表し、経度は本初子午線を基準に東方向を正、西方向を負で表します。座標の表記には主に二つの形式があります。ひとつは度分秒表記のDMSで、度 分 秒の順に値と記号を並べます。もうひとつは十進法表記のDDまたはDD.ddddで、小数点以下の桁数で正確さを表現します。地図データやGPSの出力はDD表記が一般的ですが、論文の図表や紙の古い地図ではDMSが使われることもあります。
表記を理解するうえで大切な点は、記号の有無やスペースの有無、北緯南緯のN Sの表示、東経西経のE Wの表示が地域やソフトウェアによって異なることです。例えば東京の位置をDDで書くとおおよそ 35.6895, 139.6917 となり、DMSで書く場合は 35°41′22.2″N 139°41′30.1″E のようになります。どの形式を使うかは用途次第で、データの加工や地図ソフトの要件、印刷物の体裁に合わせて選ぶとよいです。
特徴的な違いをまとめると、DDは扱いやすさとデータ処理向き、DMSは読みやすさと伝統的な地図表現向きという点です。国際的な標準としてはWGS84座標系が広く用いられ、その中でDDが広く使われますが、地域資料ではDMSの表現が残っていることがあります。デジタルと紙の間で表記を統一するには、元データの座標系と注記を確認することが重要です。
表記の種類と使い分けの実務ガイド
実務の現場では、いくつかの場面で表記を使い分けます。データベースやプログラムに格納する場合はDDが基本で、検索やフィルタリング、地図APIの利用時に自然に扱えます。論文や資料作成時にはDMSが直感的で見た目の理解を助けます。印刷物には見た目の揃いを整えるためDMSを採用することも多いです。地図サービスを使うときはURLのクエリパラメータの形式に合わせる必要があり、DDかDMSかを事前に確認しておくと混乱を防げます。
例として東京駅周辺の座標を挙げると、DDでは約 35.681236, 139.767125 となり、DMSでは 35°40′52.46″N 139°46′01.65″E となります。厳密な四捨五入の違いがくる場合があるので、桁数を決めて揃えることが大切です。
見かけ上の違いだけでなく、半径や投影の情報、座標系の単位を読み解くことも重要です。データを共有する相手がどの表記を求めているかを事前に確認し、注記として座標系や参照系を明記しましょう。
- 用途に応じた表記を選ぶ
- データベースやプログラムはDDを優先
- 紙地図や資料はDMSで可読性を重視
- 地図APIやソフトウェアの仕様を確認
この小ネタはDMS表記の現場あるあるを雑談風にたどる話です。友達と地図アプリの座標をいじるとき、DMSとDDの混同で目的地を違う場所に指し示してしまい、現場は大笑い。DMSは度分秒の三要素を正確に並べる必要があり、秒の小数点まで揃えないと微妙なズレが生じます。そんなときは出典の座標系やソフトの仕様を再確認するのが鉄板です。こうした小さな誤解は地理の学びを深めるきっかけにもなり、正しい表記を覚える楽しさにつながります。
前の記事: « 緯度経度 緯線経線 違いを徹底解説!地図の謎を解く3つのポイント





















