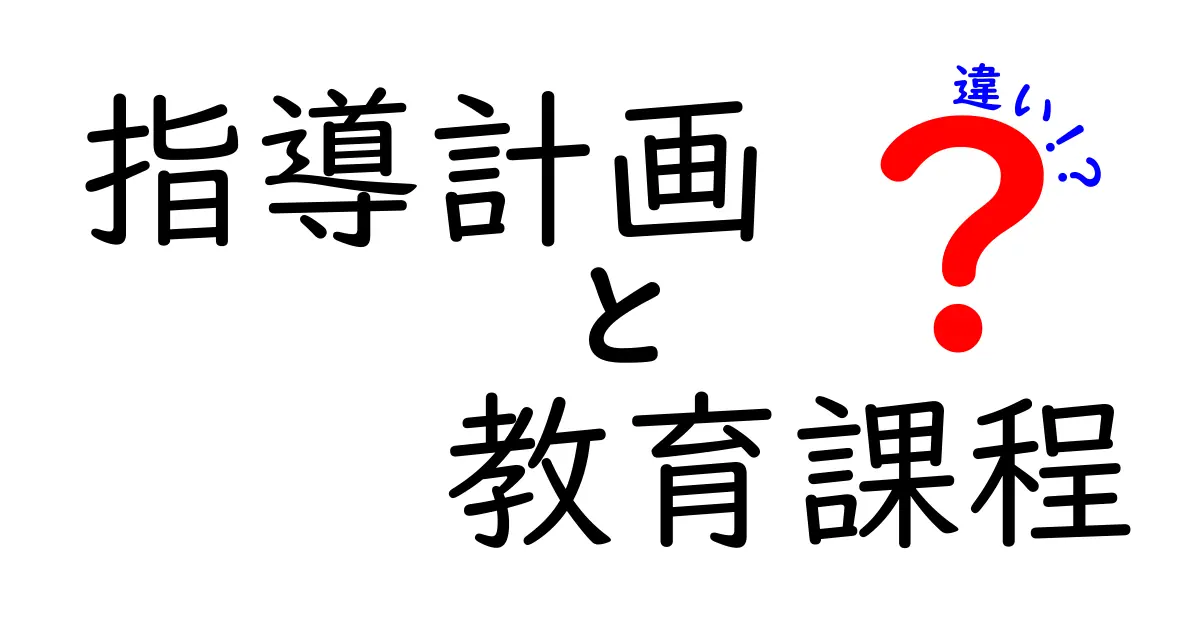

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指導計画と教育課程の違いとは?基本から理解しよう
学校教育では「指導計画」と「教育課程」という言葉がよく使われますが、この2つの意味や役割の違いを明確に理解している人は意外と少ないです。
指導計画と教育課程はどちらも学校での学びにかかわる重要なものですが、その目的や使い方、作成する人や内容などで大きく異なります。
この記事では、中学生でもわかりやすいように指導計画と教育課程の違いを丁寧に解説していきます。これを読めば学校での学びがもっとクリアにイメージできるはずです!
教育課程とは?学校全体の学びの基本となる計画
教育課程とは、文部科学省が定めた「学習指導要領」に基づいて、学校が提示する学習の大枠のことです。
教育課程は主に、どの教科をどれだけの時間で学ぶか、年間の学習内容の配分や順番を設定したもので、学校ごとにその地域やレベルに応じて作られます。
たとえば小中学校で何年生の時に何の勉強をどのくらいやるか、全体の時間や流れがわかる計画です。
学校全体の基本方針として、長期的に学びの全体像を示すものであり、児童や生徒に継続的に深めていく学習の道しるべとなります。
教育課程の特徴
- 文部科学省の学習指導要領に基づく
- 学校全体で共有する長期的な学習計画
- 1年間を通じた教科ごとの授業時間数や内容の配分を決める
- 児童・生徒全体の学習の流れを示す
指導計画とは?先生が作る具体的な授業の手順
指導計画は、教育課程をもとにして、先生が実際の授業でどのように教えるかを細かく考えた計画です。
1つ1つの授業内容や順序、使う教材や目標を具体的に決めたものが指導計画です。
例えば、社会の歴史の授業なら、どの時代の話を何時間使って、どんな資料や板書を使うかを決めます。
つまり指導計画は、先生が日々の授業で使う実践的な計画で、子どもたちの理解度に合わせて工夫したり、修正したりすることもあります。
教育課程が大きな枠組みだとすると、指導計画はその中身を細かく具現化したものというイメージです。
指導計画の特徴
- 教育課程を基にして作られる
- 先生が授業ごとに作成する具体的な計画
- 教材や教え方、時間配分、課題など詳細を含む
- 児童・生徒の理解度に応じて変更可能
教育課程と指導計画の違いを比較!表でわかりやすく解説
まとめ:指導計画と教育課程の違いを押さえて学びを深めよう
今回は「指導計画」と「教育課程」の違いについて詳しく解説しました。
教育課程は学校全体で決める1年間の学習の基本枠組み、指導計画は先生が授業単位で作る具体的な教え方の計画と考えるとわかりやすいです。
この2つがうまく連携することで、学校での学びがスムーズに、子どもたちに合わせて効果的に進んでいけます。
ぜひ今回の内容を参考に、日々の学校生活や勉強をより理解しやすくしていきましょう!
指導計画って、先生が授業ごとに細かく作る計画なんですが、実は子どもたちの理解度によって柔軟に変えられるのがポイントなんです。
たとえば、算数の授業でみんながまだ分からなかったら、先生は次の授業で説明を増やしたり、違う教え方を試したりします。
こうやって日々調整しているから、指導計画は「生きた計画」と言われることもあるんですよ!





















