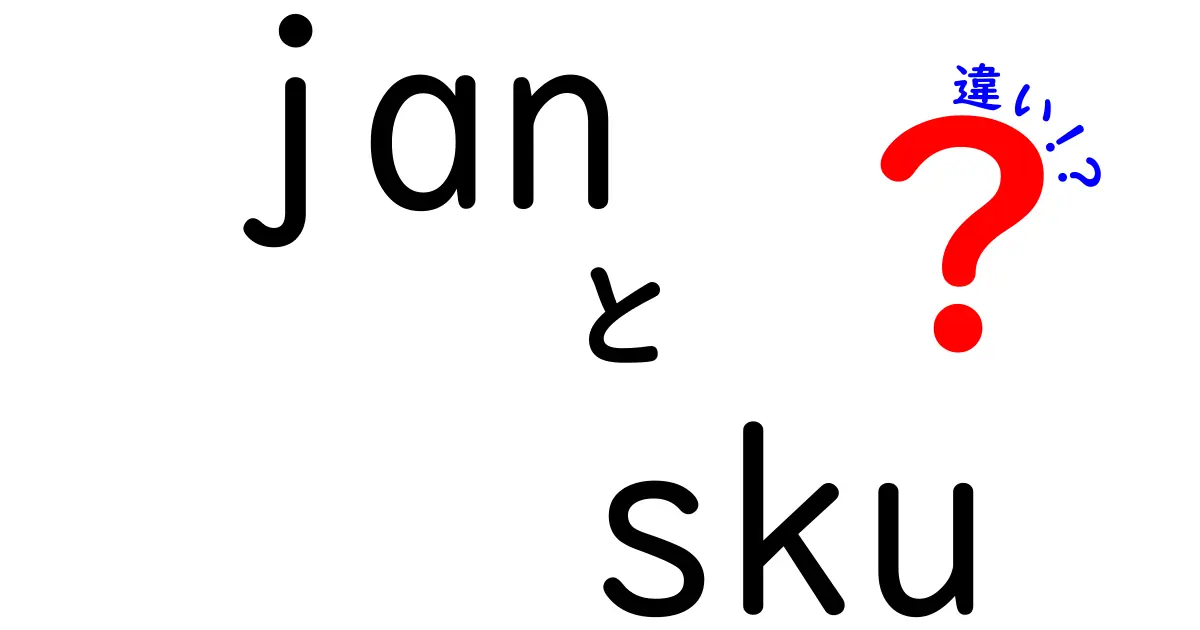

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
JANコードとは何か?基本のしくみを理解しよう
皆さんは商品を買うとき、パッケージに印刷されているバーコードを見たことがありますか?
そのバーコードに含まれる番号の一つにJANコードというものがあります。JANコードは「Japanese Article Number」の略で、日本をはじめ世界的に使われている商品の識別番号です。
主にスーパーマーケットやコンビニ、ドラッグストアなどの商品管理や販売管理に使われています。
JANコードは13桁または8桁の数字で構成されていて、
最初の数字は国コード、次に製造会社コード、そして商品コード、最後にチェックデジットという計算で求められる検査番号がついています。
これにより、世界中で一意の商品識別ができ、店舗や工場でのトレーサビリティや売上分析に役立っています。
SKUとは?JANコードとの違いを詳しく解説
SKU(Stock Keeping Unit)は、商品や商品の属性を管理するための番号のことをいいます。
SKUは、在庫管理や販売管理の目的で企業独自に付ける番号です。
JANコードが国や製造者レベルで共通の番号なのに対して、SKUは小売店や企業が自分たちのシステム内で管理しやすいよう自由に設定できる番号となっています。
例えば、同じTシャツでも色やサイズが違えばそれぞれにSKUが割り当てられます。
つまりJANコードは商品単位の識別であり、SKUは商品の細かいバリエーションごとの管理コードとイメージするとわかりやすいです。
SKUは数字だけでなくアルファベットを組み合わせて作成されることも多く、企業によってフォーマットが異なります。
JANコードとSKUを表で比較してみよう
| 項目 | JANコード | SKU |
|---|---|---|
| 正式名称 | Japanese Article Number | Stock Keeping Unit |
| 目的 | 商品を国際的に一意識別する | 企業内で在庫や販売管理をしやすくする |
| 付け方 | 国際ルールに従い管理機関が割り当て | 企業が自由に設定可能 |
| コードの長さ | 8桁または13桁の数字 | 企業によって異なる。数字や英数字混合が多い |
| 管理単位 | 1商品単位 | 商品の色やサイズなど細かいバリエーション単位 |





















