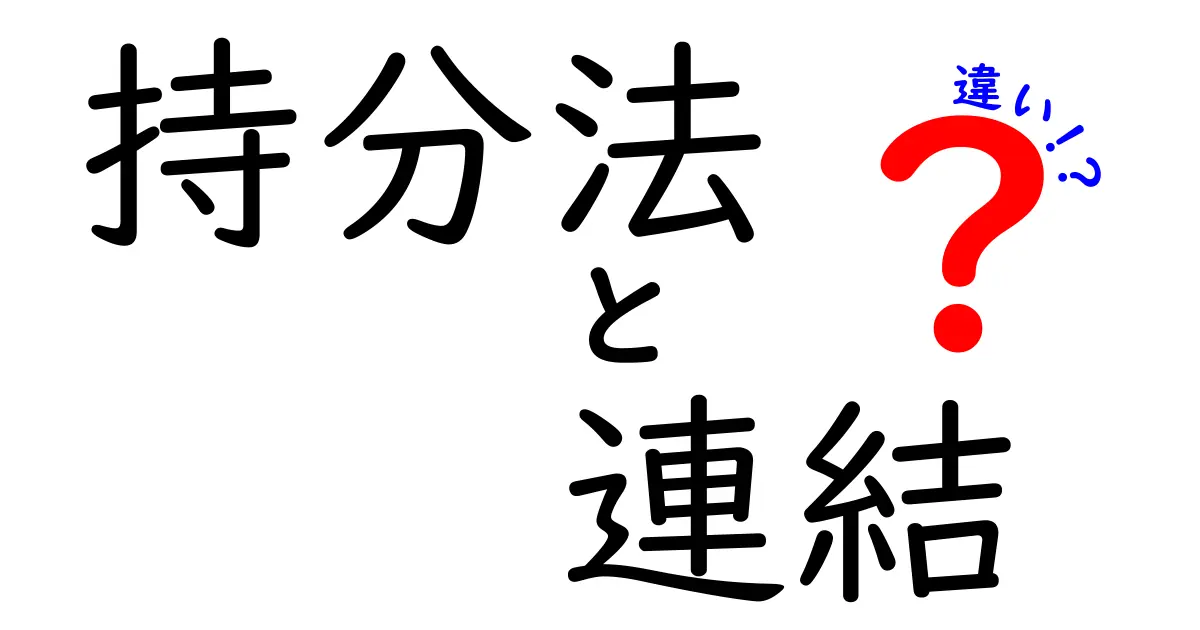

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
持分法とは?基礎から知ろう
まずは持分法について説明します。持分法は、企業が他の会社の株式を一定以上持っている時に使う会計の方法です。たとえば、ある会社が他の会社の株を20%から50%程度持っている場合、その会社の利益や損失の一部を自分の会社の利益や損失として計算します。
具体的には、持分法では被投資会社の純利益に応じて、投資した会社の帳簿価額(投資価額)が増減します。これにより、単なる株式の値動きだけでなく、被投資会社の業績変動が投資会社に反映されるのです。
持分法は、お互いにビジネスで影響を持ち合う関係を表しますが、完全に支配しているわけではありません。なので、財務情報の一部を共有しつつも、独立した経営がなされている場合に使われます。
連結会計とは?グループ全体で見る財務情報
次に連結会計についてです。連結会計は、ある会社が他の会社を50%以上支配しているときに使われます。この時は、親会社と子会社は「一つの会社のグループ」として扱い、財務情報をまとめて作ります。
つまり、親会社と子会社の資産や負債、売上や費用を足し合わせて、一つの大きな会社のように報告します。これにより、外部の人もグループ全体の経営状態を正確に把握できるようになります。
連結会計は、完全な支配関係に基づいた会計処理方法であり、親会社が子会社の経営に強く影響を持つ場合使われます。子会社の損益や資産負債は親会社のものとして全て合算されることが特徴です。
持分法と連結会計の違いを表で比較!わかりやすくまとめ
ここまで読んできて、持分法と連結会計の違いがまだイメージしにくいかもしれません。そこで、下の表で両者の違いをまとめます。
このように、持分法は部分的に影響を持つ会社の利益を反映するのに対し、連結会計は支配関係にある全ての会社の財務情報をまとめる点で大きく異なります。
なぜ違いが大切?ビジネスや投資での意味
会計処理の方法によって会社の財務状況の見え方が変わります。
持分法は、影響力はあるけれど完全な支配はない会社の価値や利益を適正に反映するため、投資先の実態を理解しやすくなります。
一方で、連結会計はグループ全体の経営状態を把握するのに欠かせない方法です。例えば大企業が子会社を多数持つ場合、連結会計で一体の企業グループとして財務情報を報告しないと、実態が見えにくくなります。
投資家や株主、銀行などはこれらの数字を元に経営判断や投資判断をします。だから会計の違いを知ることは、ビジネスで失敗しないためにも大切なのです。
持分法はよく「20%以上保有している会社で使う」と言われますが、実はこの20%という数字は法的な決まりではなく、企業の経営にどれだけ影響を与えられるかという実態に基づいて判断されています。だから、20%未満でも重要な影響力が認められれば持分法が使われることもあるんですよ。こうした実態重視のルールって会計の面白さの一つですね!





















