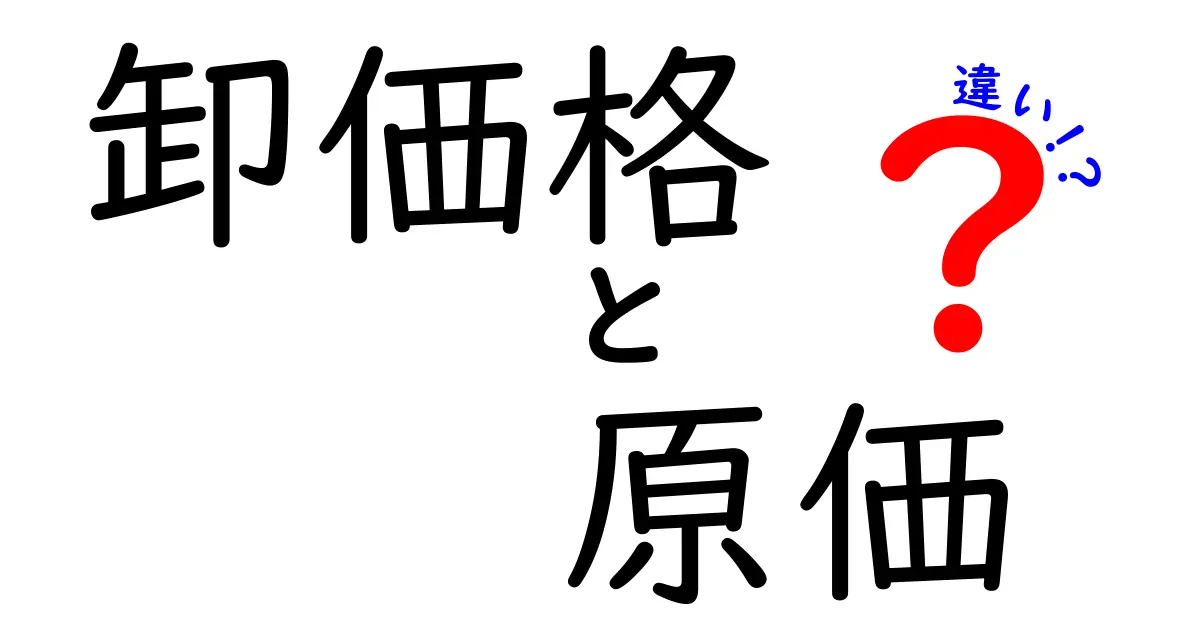

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
卸価格と原価の基本的な違いとは?
ビジネスの世界でよく使われる言葉に「卸価格」と「原価」があります。
どちらも商品の値段に関わる言葉ですが、意味は全く違います。
今回はこれらの言葉の違いを中学生でもわかりやすく解説します。
まず原価とは、商品を作るのにかかった費用のことを指します。
材料費や人件費、設備費など商品の製造に必要な直接的な費用が含まれます。
例えば、パンを作る場合、小麦粉や砂糖、バター代、それを作る職人の給料が原価にあたります。
一方卸価格は、メーカーや生産者が小売店などに商品を売る際の販売価格のことです。
つまり、卸売業者が小売店に商品を提供する値段で、原価に利益や流通コストを加えた価格になります。
これを踏まえると、簡単に言うと原価は商品を作るのにかかる費用、卸価格は売るために設定された値段という違いがはっきりします。
卸価格は原価よりも高く設定されるのが普通です。
具体例でわかる卸価格と原価の違い
たとえば、あるお菓子工場で1個のお菓子を作るのに原価が100円だったとします。
この100円には、材料費、包材費、製造にかかった人件費などが含まれています。
工場はこのお菓子をスーパーに売るとき、利益や流通費用を考慮して卸価格が150円に設定されることがあります。
スーパーは卸価格の150円で商品を仕入れ、お店で販売するときには更に利益を乗せるため小売価格は200円にすることも多いです。
ここで重要なのは、原価は工場側の製造コスト、卸価格は工場がスーパーへ売る値段、そして小売価格はスーパーが消費者に売る値段と役割が明確に違うことです。
このように価格が段階ごとに変わることで、売る側も買う側もそれぞれの利益や費用をカバーできる仕組みになっています。
卸価格と原価、知っておきたいポイント一覧
| 用語 | 意味 | 含まれる費用 | 価格の特徴 |
|---|---|---|---|
| 原価 | 商品を作るための費用 | 材料費、人件費、設備費など | 製造コストが中心で利益は含まれない |
| 卸価格 | メーカー・生産者が小売店へ売る値段 | 原価+製造者の利益+流通コスト | 原価より高いことが普通 |
この表を見れば、どんな違いがあるのかひと目でわかりますね。
まとめると、原価は商品の作り手がかけた費用、卸価格は商品を次の販売者に売るための値段ということです。
価格体系を理解することはビジネスの基本になるので、ぜひ覚えておいてください。
「卸価格」って意外と幅があるって知ってましたか?
同じ商品でも取引先や数量、時期によって変わることがあります。
例えば大量に買うときは卸価格が安くなることもあって、小売店にとってはかなり重要なポイントです。
だから“卸価格は固定の値段”というイメージだけでなく、実際には交渉や契約内容によって変動することがあると覚えておくといいですよ。
これがビジネスの面白さの一つだったりします!





















