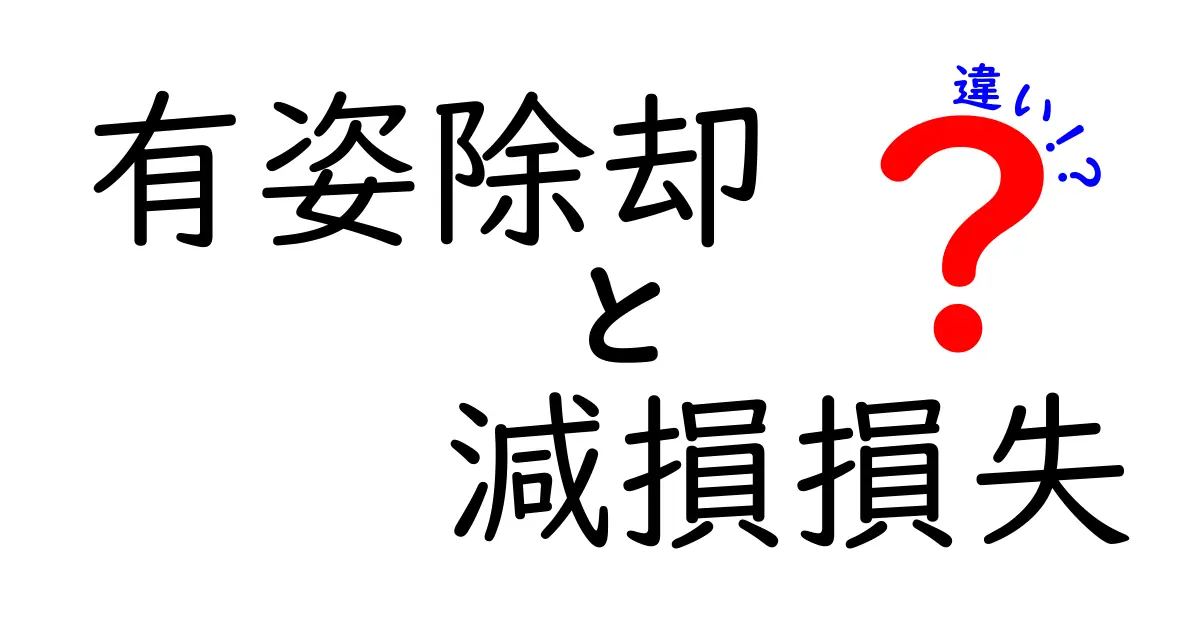

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
有姿除却と減損損失とは何か?基本の説明
会計の世界には難しい言葉がたくさんありますが、その中でも「有姿除却」と「減損損失」は特に耳にしにくい言葉かもしれません。
まずはそれぞれの用語の意味から簡単に説明しましょう。有姿除却とは、企業が所有している資産が使えなくなった時や取り壊すとき、その資産を帳簿から取り除く処理のことを言います。資産が形としてまだ存在している状態で、使えなくなったものを取り除くイメージです。
一方、減損損失とは、資産の価値が大きく下がってしまった場合に、その価値の下がった分を損失として計上することです。つまり、資産はまだ存在していますが、実際の価値が帳簿上の価値よりも低くなった場合に行います。
このように、どちらも資産に関わる処理ですが、使えなくなって除くのか、価値が下がった分だけ損を計上するのかが大きな違いです。
有姿除却と減損損失の具体的な違いをわかりやすく比較
ここからは、有姿除却と減損損失が具体的にどう違うのか、もっと詳しく見ていきたいと思います。
まず、有姿除却は資産が完全に取り除かれる時に使う処理です。例えば工場の機械が壊れて動かなくなり、もう直せない場合、その機械を帳簿から外すために有姿除却を行います。形としてはまだあるけれど、使えないものを除くのがポイントです。
一方、減損損失は資産がまだ使えるけど、価値が下がった分だけ損失を計上することです。例えば建物の市場価値が急に下がった場合、帳簿上の価値もそれに見合った金額に減らすための処理です。
下の表で違いをまとめてみましょう。
| ポイント | 有姿除却 | 減損損失 |
|---|---|---|
| 対象 | 使用不能になった資産の除去 | 価値が下がった資産の価値減少 |
| 処理内容 | 資産の帳簿からの削除 | 資産価値の減少分を損失計上 |
| 資産の状態 | 実物はまだあるが使えなくなる | 実物はあるが価値が減る |
| 発生タイミング | 資産を取り壊す時など | 市場価値の下落などで価値が著しく下がった時 |
このように、処理の目的やタイミングで使い分けることが大切です。
実務での具体例と注意点について
では、実際の企業の会計処理ではどのように使い分けられているのでしょうか?
例えば、工場の老朽化した機械を撤去する場合は「有姿除却」によって、その機械を資産から除きます。廃棄によって資産が減るけれど、新たな損失計上は基本的にありません。
一方で、例えば自然災害や技術の進歩によって建物や設備の価値が落ちた場合には、その価値減少分を「減損損失」として計上します。これは、企業の資産価値を正しく反映するために重要です。
また、減損損失はきちんと調査を行い、価値下落が本当に大きいかどうか判断する必要があります。単なる一時的な価値低下ではなく、長期的な価値の下落が認められた場合にだけ行います。
これらの処理は、企業の財務状況を正確に伝えるためのものであり、誤った処理は信用問題にもつながるため注意が必要です。
今回は「有姿除却」についてちょっと面白い話をしましょう。
この言葉、聞き慣れないかもしれませんが、実は「形のあるものを取り除く」という意味から来ています。つまり、動かなくなった機械や設備を会計上で棚卸し、と言う意味合いで取り除くわけです。
ここで面白いのは、まだ物理的には存在するのに『価値がない』と認められてしまう点。まるで、使えなくなったラジオが部屋に置いてあっても、会計上は『もうないもの』として扱われるんです。
ちょっと心情的には寂しい気もしますが、企業にとっては効率的に資産管理を行うための大切なルールなんですね。
次の記事: 減価償却と減損損失の違いをスッキリ解説!初心者でもわかる基礎知識 »





















