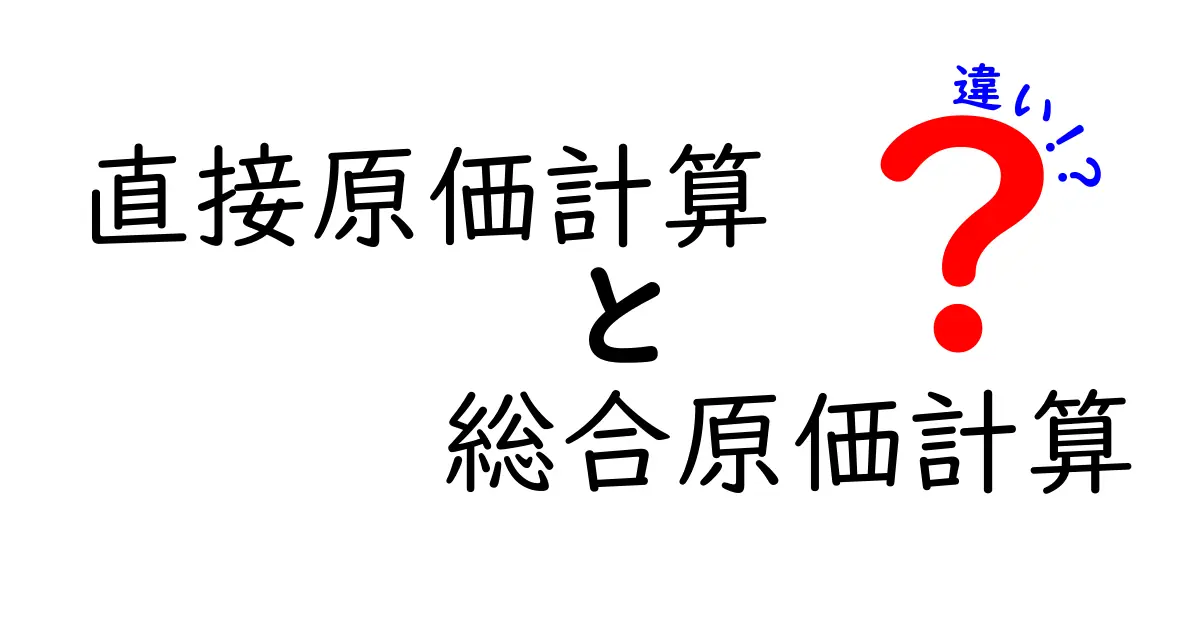

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
直接原価計算と総合原価計算とは?
ビジネスや工場でモノを作るとき、どれくらいお金がかかっているのかを計算することはとても大切です。
その中でも「直接原価計算」と「総合原価計算」は、製品のコスト(費用)を計算する方法の代表的な2つです。
でも、名前が似ているので「何が違うの?」と悩む人も多いです。
ここでは直接原価計算と総合原価計算の違いを、中学生でもわかるようにやさしく説明していきます。
まずはそれぞれの意味を確認しましょう。
直接原価計算とは?
直接原価計算は、製品を作るために直接かかった費用だけを計算する方法です。
たとえば、自動車を作る場合、「エンジンの部品」や「タイヤ」など、直接使われた材料費や直接関わった人の労務費だけを考えます。
これに対して、工場の電気代や工場全体の管理費などは含めません。
この方式の良いところは、コストがはっきりと分かりやすいことです。
例えば、「1台の車を作るのに直接かかった材料費はいくらか?」とすぐ答えられます。
総合原価計算とは?
一方、総合原価計算は製造に関わった全ての費用を合計する方法です。
直接材料費や直接労務費だけでなく、工場の光熱費や機械の減価償却費、管理者の給料などの間接費も含まれます。
この方法は、どれだけお金が全体でかかったかを正確に知るのに役立ちます。
たとえば、多品種をたくさん作る工場で、「全ての費用を合計して平均のコストを出す」用途に向いています。
直接原価計算と総合原価計算の違いを表で確認!
ここで、両者の違いを表にまとめてみます。
| ポイント | 直接原価計算 | 総合原価計算 |
|---|---|---|
| 計算対象の費用 | 直接材料費・直接労務費のみ | 直接費+間接費(工場全体の費用) |
| 目的 | 製品単位の直接コスト把握 | 全体の正確な製造コスト把握 |
| 製造間接費の扱い | 費用として期間で処理(固定費を含めないことも) | 製品に配賦して計算 |
| 使う場面 | 利益管理や意思決定用 | 財務会計や決算用 |
| 特徴 | コストがシンプルで早い 利益分析に便利 | 全ての費用が反映される 在庫評価に適切 |
まとめ
直接原価計算と総合原価計算は、費用の含め方と使い方が違う計算方法です。
直接原価計算は「直接かかった費用だけ」を考え、経営の判断や利益分析に向いています。
一方の総合原価計算は「間接費も含めたすべての費用」を計算し、会計や報告に使います。
どちらも大切な計算方法で、目的に応じて使い分けることが望ましいです。
理解を深めて、仕事や学びに役立ててくださいね!
直接原価計算でよく話題になるのが「固定費」です。実は、固定費は期間によって変わらない費用のことですが、直接原価計算ではこの固定費を製品のコストに含めないことが多いんです。これは「製品を作るごとにかかる直接費だけを見たいから」という考え方で、利益や経営判断がスムーズになるからです。ちょっと不思議ですよね?経費なのに製品に入れないのは、経営を助けるための工夫なんですよ!
前の記事: « 完了品と完成品の違いとは?中学生にもわかるやさしい解説





















