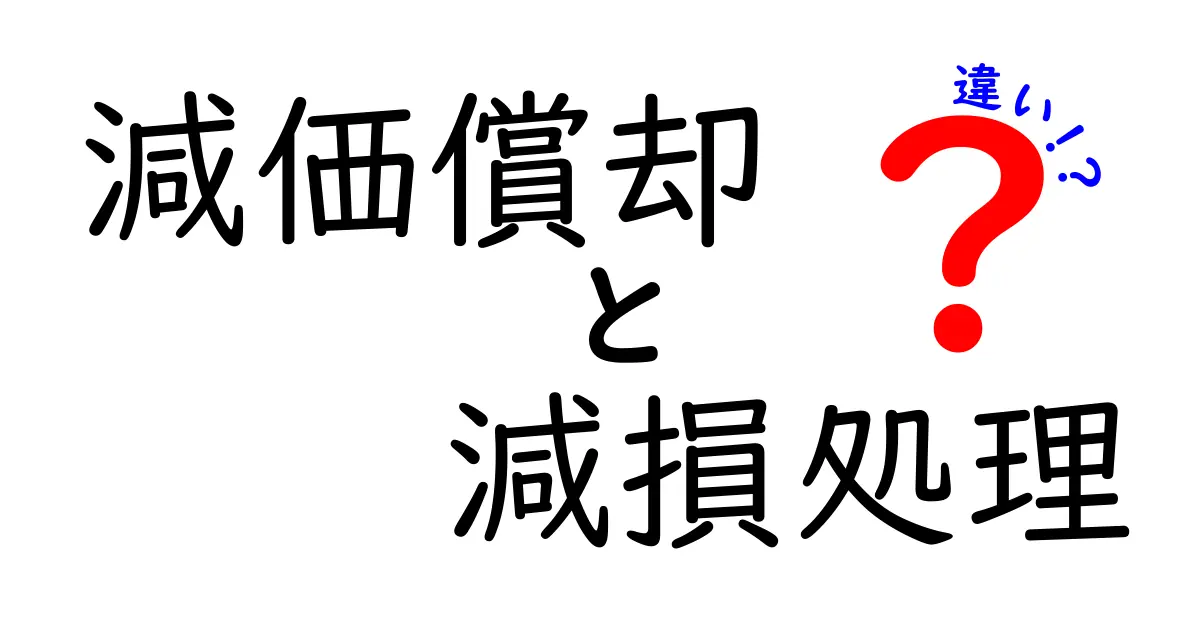

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
減価償却とは何か?
減価償却とは、会社やお店が持っている「建物」や「機械」などの長く使う物の価値が、時間と共に少しずつ減っていくことをお金の面で表す方法です。
例えば、1,000万円の機械を10年間使う予定なら、毎年100万円ずつ費用として計上します。これが減価償却です。
この方法を使うことで、会社の利益を正しく計算し、税金を適切に支払うことができるんです。
減価償却は計画的に決められていて、資産の価値を少しずつ減らしていく仕組みとなっています。
この大切な考え方は、会計や経済の基本として押さえておきたいポイントです。
減損処理とは?
減損処理は、資産の価値が急に大きく下がった場合に、その価値の下がりを帳簿にすぐに反映するための方法です。
例えば、地震や火事で建物が壊れたり、新しい技術のせいで古い機械の価値がほとんどなくなったりした場合に使われます。
減損処理は、価値の大きな下落を早めに認め、その分を費用として計上します。これによって、会社の本当の価値や経営の状態を正しく示すことができるのです。
減損処理は、突然の価値下落に対して使う特別な処理で、普段の減価償却とは違う目的があります。
減価償却と減損処理の違い
減価償却と減損処理は、どちらも資産の価値をお金の面で整理する方法ですが、使う場面や意味が違います。
具体的に違いを見るため、表にまとめました。
| ポイント | 減価償却 | 減損処理 |
|---|---|---|
| 意味 | 資産の価値を時間と共に少しずつ減らす | 資産の価値が急に大きく下がった時に減らす |
| 目的 | 資産の使用期間にわたる費用配分 | 資産の帳簿価値を実際の価値に合わせる |
| 計算方法 | 定額法や定率法などの計画的な方法 | 市場価値や回収可能額に基づいて評価 |
| 頻度 | 毎年行う一般的な処理 | 急激な価値減少があった場合のみ実施 |
| 会計上の影響 | 毎年の費用に計上 | 減損損失として一括計上 |
このように、減価償却は日常的に行う「価値の少しずつの減少」を扱い、減損処理は「急な大幅な価値の減少」に対応する特別な方法です。
どちらも会社の正しい経営状態をわかりやすくするための大切な会計の手法です。
少し難しい言葉に聞こえますが、中学生でも理解できるように例をあげて説明すると、減価償却は「スマホのバッテリーが使うにつれて徐々に弱くなること」、減損処理は「急にスマホが壊れて使えなくなること」に似ています。
こうした処理は会計のルールとして決まっていますので、会社は正しい数字を使って経営の判断を行っています。
減価償却って、ただ毎年お金の価値を減らしているだけに見えるかもしれませんが、実は経営の健康チェックにも役立っているんです。例えば、古くなった機械の価値がちゃんと帳簿に反映されていると、その資産がいつまで使えるか、次にどれくらいの投資が必要かを予測しやすくなります。だから減価償却は、ただの数字の調整だけでなく、未来の計画作りに欠かせないんですよ。
急に壊れた場合には減損処理が必要ですが、普段はこの減価償却が会社の資産の健康状態を見守っている感じですね。意外とすごい仕組みだと思いませんか?
前の記事: « 初心者必見!減損処理と評価損の違いをわかりやすく解説





















