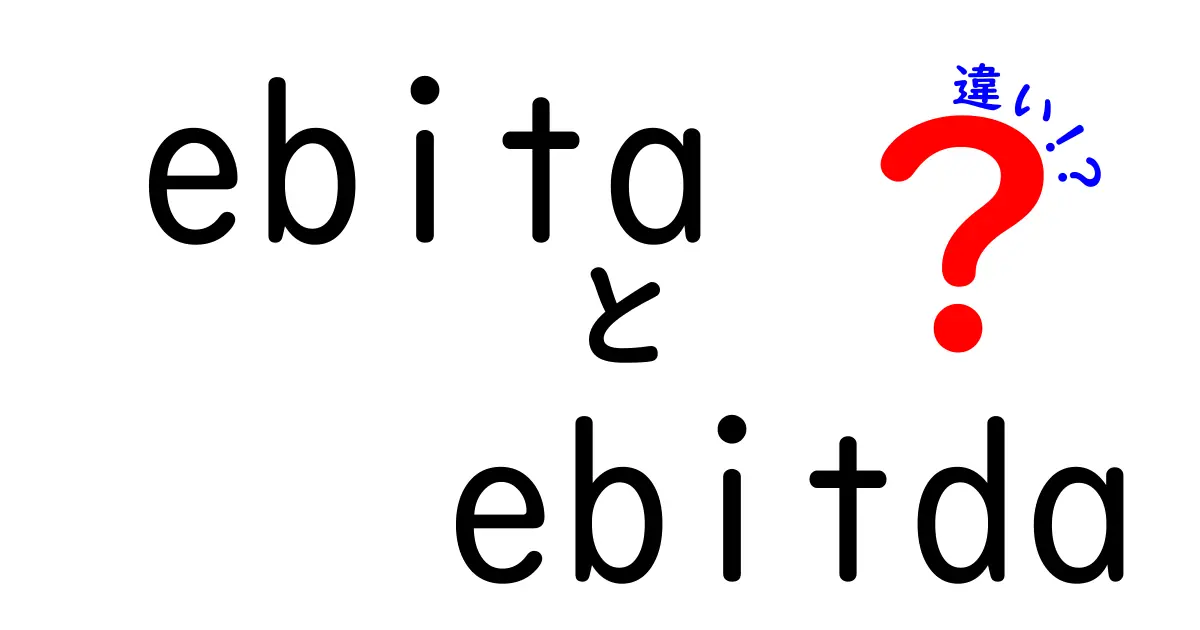

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
EBITAとEBITDAとは何か?基本から理解しよう
企業の経営状況や収益力を知るために使われる指標として、EBITAとEBITDAがあります。
まずは、この2つの言葉の意味を簡単に説明しましょう。EBITAは「Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization」の略で、「利息・税金・償却費控除前利益」となります。一方、EBITDAは「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization」の略で、「利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益」です。
この2つは企業の稼ぐ力を見るうえで重要な指標ですが、混同しやすいので違いをしっかり理解することが大切です。
ここからは、それぞれの特徴と違いについてわかりやすく解説します。
EBITAとEBITDAの主な違いとは?表で比較してみよう
EBITAとEBITDAの大きな違いは、「減価償却費が含まれるかどうか」です。
具体的には、EBITAは減価償却費を差し引いたあとですが、EBITDAは減価償却費を含めていません。つまり、EBITAはEBITDAから減価償却費を引いた数値となります。
下の表で比較してみましょう。
つまり、EBITDAはキャッシュの動きを重視し、EBITAは減価償却を考慮して企業の利益力を見る特徴があります。
特に設備投資が多い業界ではEBITDAの方が実際のキャッシュ収支を表すため注目されやすいです。
なぜEBITAとEBITDAの違いを知ることが重要なのか?
この2つの指標を見ることで、企業の実態をより正確に把握できます。
例えば、減価償却費は過去の設備投資に関わる経費なので、現金の流出はすでになされた費用になります。だから、EBITDAは企業のキャッシュを生み出す力を示しやすいのです。
一方でEBITAは減価償却費も考慮しているため、会社の利益率をより保守的に見るのに適しています。
投資家や経営者はこれらの違いを理解して、業績比較や投資判断の際に使い分けています。
また、業界によってどちらの指標を使うべきかも変わるため、基礎知識として抑えておくと役立ちます。
まとめ
EBITAとEBITDAはどちらも企業の利益を示す重要な指標ですが、減価償却費の扱いに大きな違いがあります。
EBITAは減価償却費を含むため、より保守的な利益を示し、EBITDAは減価償却費を除くことで現金の動きに近い利益を表します。
両者の違いを理解することで、財務諸表の読み方が深まり、企業の実態を正しく評価できるようになるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、EBITAとEBITDAの違いをしっかり押さえてください。
EBITDAは企業の現金の動きに近い利益を示す指標ですが、実は減価償却費だけでなく、償却費という無形資産のコストも除外しています。例えば、特許やソフトウェアなどの無形資産は償却によって費用化されますが、これが実際の現金支出を伴わないことが多いため、経営状態を把握するときに重要な調整項目となるのです。だからEBITDAを使うときは無形資産の業種かどうかも考慮すると、より適切な分析が可能になります。
次の記事: EBITとEBITDAの違いとは?中学生でもわかるやさしい解説 »





















