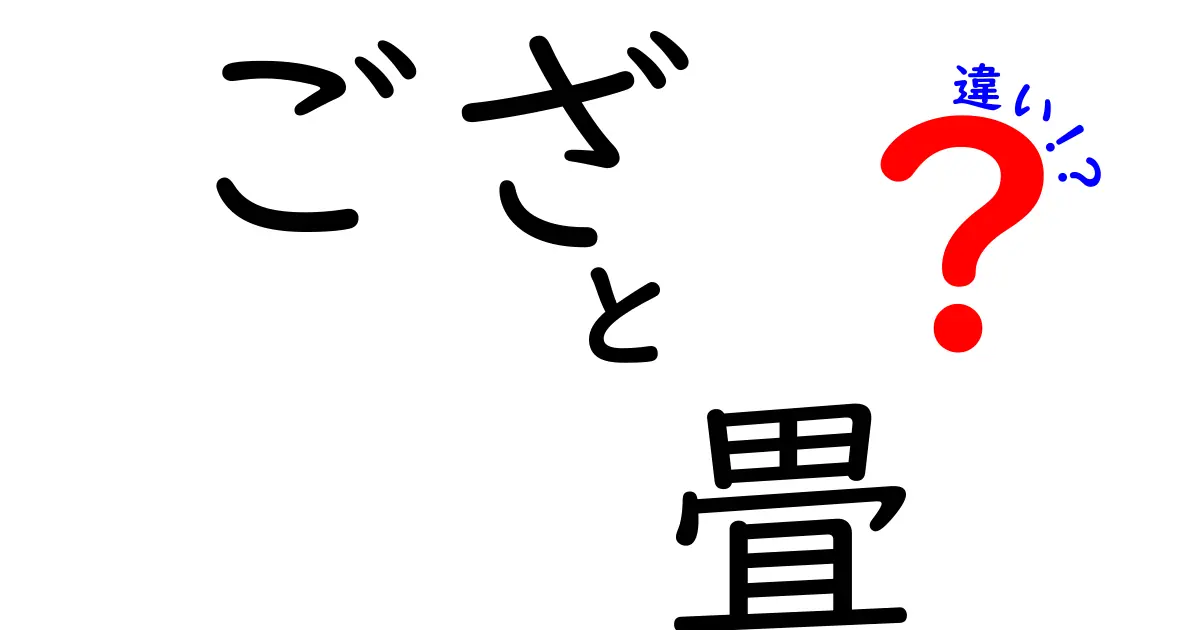

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
「ござ」と「畳」の基本的な違いとは?
「ござ」と「畳」は、どちらも日本の床に使われる伝統的な素材ですが、その使われ方や意味にははっきりとした違いがあります。
まず、「ござ」は主に稲わらやイグサを編んで作られた敷物のことを指します。薄くて軽く、持ち運びやすいのが特徴で、季節のイベントや祭り、野外の行事などで敷かれることが多いです。また、ござは場所や用途に応じて使い捨てることもあります。
一方で、「畳」は部屋の床を覆うための厚みのある床材です。框(かまち)という木の枠で縁取られ、芯材には圧縮された藁やウレタンフォームが使われることが多いです。
畳はお家の生活空間の一部として固定され、室内の快適さや断熱性、音の吸収などにも優れています。
このように、ござは持ち運びやすい薄い敷物、畳は固定された厚みのある床材という違いがあるのです。
素材や製法の違いについて
「ござ」と「畳」は、どちらも主にイグサ(葦の一種)が使われていますが、細かい製法や構造に違いがあります。
ござはイグサを平たく編んで作られ、織物のような薄いシート状です。細かく編まれることで丈夫さと柔軟さを兼ね備えています。扱いやすいので、さまざまな大きさにカットして使えます。
畳の場合は、イグサの上にしっかりとした芯材(稲わらの固まりやウレタンフォーム)があり、厚みと強度を持たせるために縁で包まれています。表面のイグサはござのように編まれていますが、畳用のイグサは長くて太く、耐久性が高いです。
このように、ござは軽量で薄く、畳は重厚で厚い構造という大きな違いがあります。
使い方や設置場所の違い
ござは、夏祭りやピクニック、屋外のイベントなど「一時的に敷いて使う敷物」として使うことが多いです。
たとえば、花火大会で座る時に敷いたり、畳の上に敷いて直接肌に触れないように使ったりもします。また、ござには持ち運びできるサイズやロール状の製品があり、収納や運搬が簡単です。
一方、畳は住宅の和室の床材として固定されています。リビングや寝室などで長く使われており、直接座ったり寝転んだりするのに適しています。
畳は床をフローリングやカーペットから和風の落ち着いた雰囲気に変える役割もあります。
このように、ござは携帯性や一時使用が特徴で、畳は室内の恒久的な床材として使われています。
「ござ」と「畳」の違いをわかりやすく比較してみよう
| ポイント | ござ | 畳 |
|---|---|---|
| 素材 | 主にイグサを薄く編んだもの | イグサの表面+稲わらやウレタンの芯材+布製の縁 |
| 厚み | 薄い(数ミリ程度) | 厚い(数センチ程度) |
| 用途 | 敷物として一時使用、屋外イベントなど | 固定された住宅の床材・室内用 |
| 持ち運び | 簡単、軽い | 重くて固定されている |
| 耐久性 | 比較的低い | 高い(数年から十年以上もつ) |
まとめ:用途に応じて選ぶ和の床材
「ござ」と「畳」は同じイグサを使った日本の伝統的な床材ですが、作りや使われ方に大きな違いがあります。
薄くて軽い「ござ」は持ち運びしやすく、一時的に敷いて使うもの。
厚くて重い「畳」は住宅や和室の床として固定され、快適さや耐久性が重要視されます。
どちらも日本の生活文化には欠かせない存在なので、使う場所やシチュエーションに合わせて選ぶことが大切です。
「ござ」と聞くと、薄くて軽い敷物というイメージが強いですが、実は「ござ」には細かい種類もあります。例えば、“い草ござ”はイグサを編んだものですが、“竹ござ”や“麻ござ”など素材が異なるものも存在します。それぞれ見た目や感触が違い、用途も微妙に異なるのが面白いポイントです。こうした多様性は日本の伝統工芸の奥深さを感じさせてくれますよね。
次の記事: 半紙と和紙の違いは?使い方や特徴をわかりやすく解説! »





















