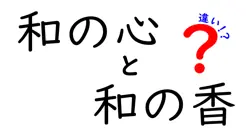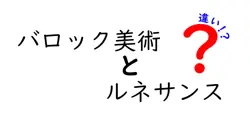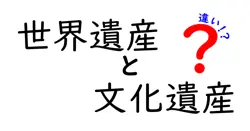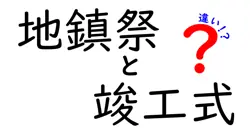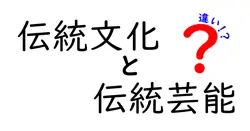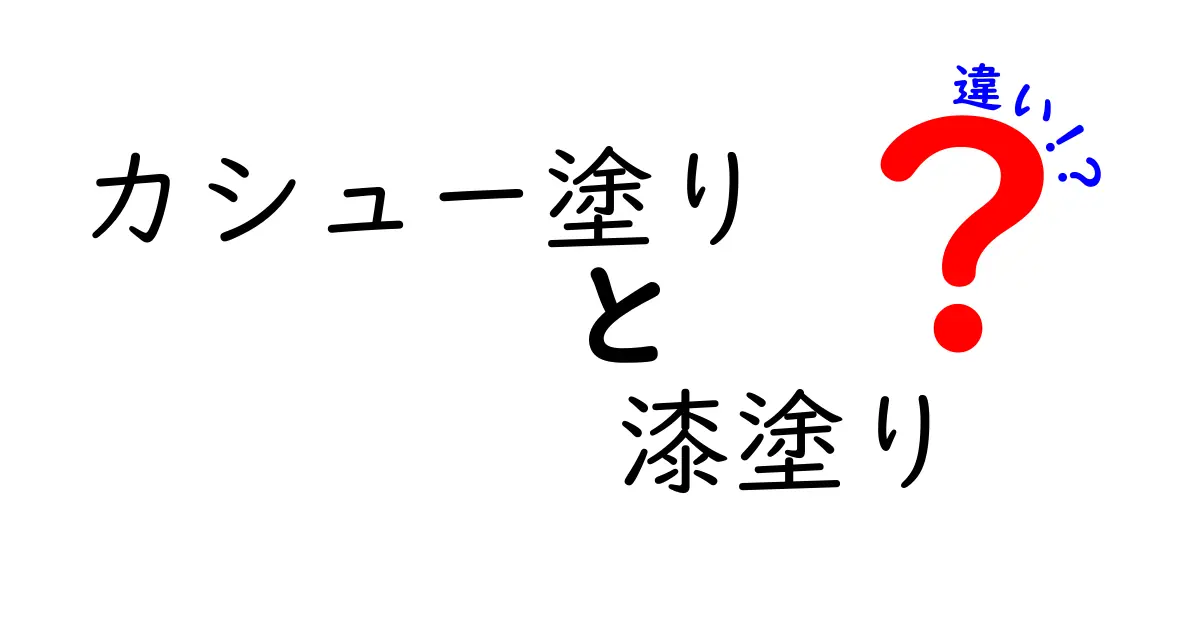

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カシュー塗りと漆塗りの基本的な違い
カシュー塗り(shellac finish)と漆塗り(urushi lacquer)は木の表面を覆い、傷や水分から守る役割を持つ伝統的な仕上げ方法です。材料と化学的な性質が根本から異なる点が大きな違いの核です。カシュー塗りはカシュー樹脂をアルコールなどの溶媒に溶かして薄く塗布します。乾燥後は透明感のある光沢が現れる一方、耐水性は漆塗りに比べて劣るため、食品容器や長時間水に触れる場所には向かないことが多いです。漆はウルシ樹脂を何度も薄く重ね塗りして、空気中の湿度と反応させて硬く強い膜を作ります。耐水性・耐摩耗性・長期耐久性に優れる一方、乾燥には時間がかかり、作業には熟練の技術と衛生管理が求められます。
さらに色味や風合いの違いも大きく、カシューは木目を活かす自然な美しさ、漆塗りは深い色と重厚感を生み、伝統工芸では加飾や蒔絵と合わせることが多いです。
見た目の違いも特徴的です。カシュー塗りは透明感のある明るい光沢を持つことが多く、木の木目を生かした美しさが出やすいです。手触りはサラリと滑らかで、再塗装や補修が比較的簡単なのも魅力です。しかし、傷ついたときには表層だけを傷めることが多く、深刻なダメージには再仕上げが必要になる場合があります。漆塗りは深みのある濃い光沢で、赤色系の染料を混ぜると朱色や黒色まで幅広く表現できます。加飾漆や蒔絵を施すことも可能で、長年大切にされてきた道具や器に多く用いられます。乾燥・硬化の過程は時間がかかりますが、完成後の耐久性は非常に高く、日常使いの道具にも耐える場合が多いです。
実務での使い分けと注意点
実務では、使用環境・目的・予算によって選択が分かれます。日常的に水分に強く、長期的な耐久性を求める場合は漆塗りが有利です。反対に、手早く仕上げたい、コストを抑えたい、または自然素材の扱いを重視する場合はカシュー塗りを選ぶケースが多いです。DIYで初めて漆を扱う際は、換気と衛生管理を徹底し、手袋・マスクを着用して作業してください。漆は皮膚刺激や呼吸器への影響があるため、子どもには触れさせないほうが安全です。カシュー塗りは下地処理が肝心で、木目を美しく出すためにはサンドペーパーと清掃を丁寧に行い、薄い層を何度も重ねて光沢を調整します。最後に、仕上がりを均一にするためには乾燥時間を守り、温度・湿度管理を行い、塗膜のひび割れを避けることがポイントです。
漆塗りを深掘りすると、ただの膜づくりではなく、日本の匠の時間と季節感が凝縮されています。私は友人と話すとき、漆を塗る前の木地の整え方や、乾燥時間の長さ、湿度の影響など、実務の現場感を共有します。カシュー塗りは手早さと簡便さが魅力ですが、漆塗りの重厚感や美しい深みにはかなわない場面も多く、用途と好みに応じて使い分けるのがベストだと思います。