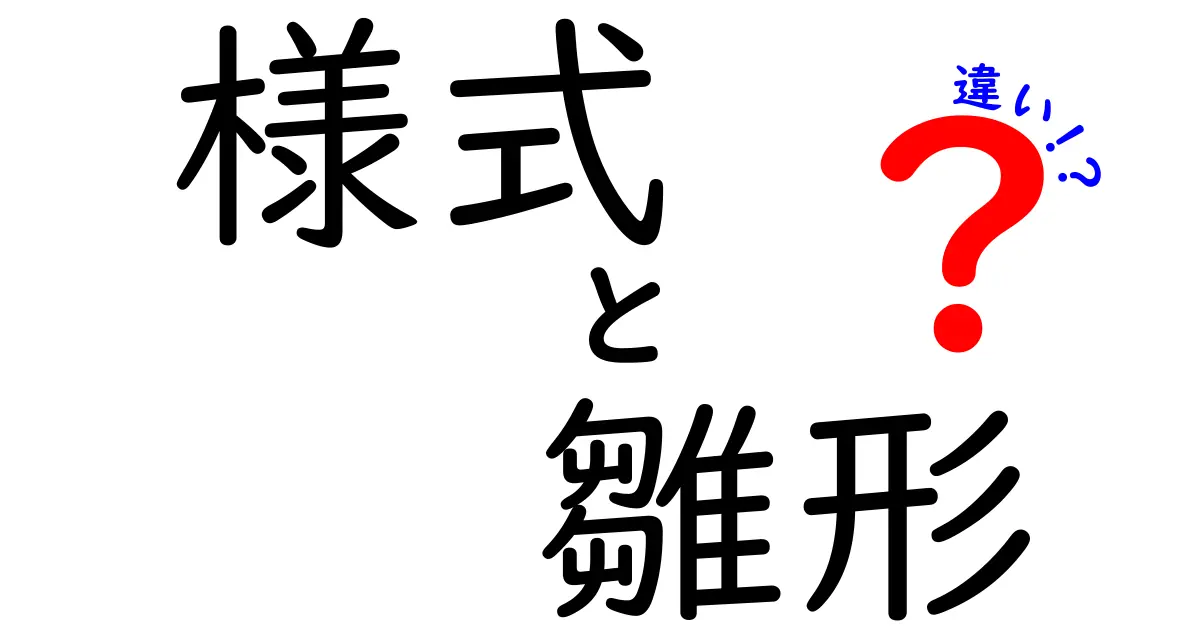

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
様式と雛形の違いを知ると得する場面とポイント
このテーマは日常のあらゆる場面で役立つ知識です。学校や仕事だけでなく、地域のお知らせやイベントの案内文など、文書を作る機会は思っているより多いものです。
この言葉の違いを理解しておくと、同じ題材でもどう作るかが変わり、相手に伝わりやすくなります。
まず大事なのは定義です。
・様式とは文書の見た目や配置を決める規則のことで、フォントの種類や文字の大きさ、行間、日付の書き方、ページの余白など、読者が読みやすく感じる視覚的要素を統一します。
・雛形とは中身の型、中身の並び方の骨格を指します。挨拶の文、本文の流れ、署名の順番など、実際の文章を作る際の土台となります。
この二つは一緒に使われる場面が多いですが、役割が違うため使い分けが重要です。
例えば学校の提出物では、様式で体裁をそろえ、雛形で内容を埋めるのが基本の進め方です。これにより、見た目の美しさと中身の正確さを同時に満たすことができます。
一方、仕事の契約書のような新しい文面を作る場面では、先に雛形を使って中身を組み立て、後から必要な様式を適用して体裁を整える方が効率的です。
要点は覚え方です。
様式は見た目の統一を作る、雛形は中身の骨格を作る、この二点を分けて考える習慣をつけましょう。
また、誤解を避けるためにも、組織の規定がある場合はその規定に合わせて改変する際のルールを確認してください。
実例で学ぶ:学校提出物とビジネス文書での使い分け
次の章では身近な場面での使い分けを具体的に見ていきます。学校では、まず雛形を使って中身を組み立て、最後に様式で見た目を整えると、初めての課題でも迷いが減ります。挨拶文の骨格、本文の展開、結びの言葉の並びといった雛形の要素を土台にして、課題のテーマにふさわしい表現を選ぶことで、読み手に伝わりやすくなります。
ビジネス文書ではさらに効果的です。大量の同種文書を作る場合は雛形を共通化しておくと効率が上がります。ただし雛形を使い回すときには、内容の正確さと相手に合わせた敬語表現を必ずチェックします。様式はこの時点で適用され、体裁を組織の規定に合わせて整えます。文書の目的が「情報の正確さ」か「印象の良さ」かで、様式と雛形の重心が若干変わる点も覚えておくとよいです。
以下の実践ステップを参考にしてください。1. 雛形を選ぶ。2. 中身を正しく埋める。3. 様式を適用して体裁を整える。4. 最後に見直しを行い、誤記や敬語の乱れを修正する。
この順序を守ると、個人の能力だけでなく、組織全体の伝え方が一段と洗練されます。
この前、友だちと校内のプリント作りをしていて雛形について話が盛り上がりました。僕らの学校では、雛形を使うとまず中身の流れが崩れず安心して書けます。たとえば挨拶の文を作るとき、雛形の骨格を借りてみんなで意見を出し合います。すると「この部分は削っていいのか」「この結びの言葉は場に合っているか」といった細かい確認が自然と進みます。さらに友人は雛形を改変する際のルールを意識していて、元の意味を保ちながら新しい文面を作るコツを教えてくれました。結局、雛形を正しく使えば初めての提出物でも落ち着いて仕上げられるという実感を得られました。
次の記事: ひな形と雛形の違いを分かりやすく解説|意味の違いと使い分けのコツ »





















